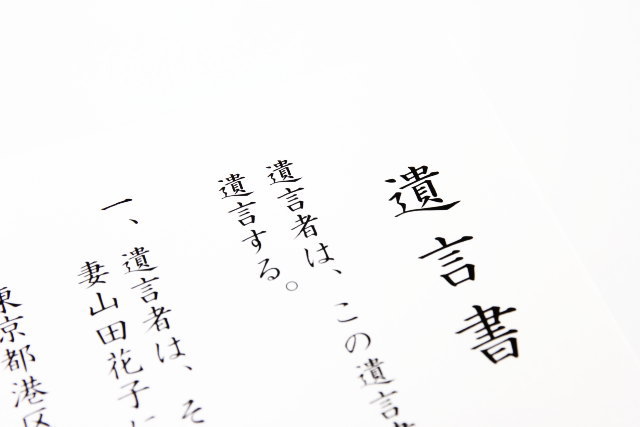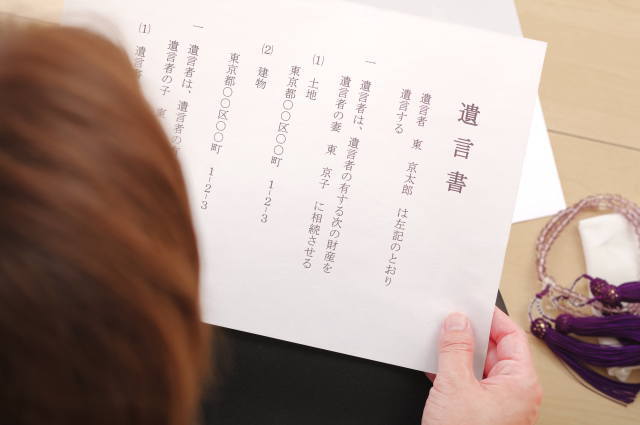・自筆証書遺言は、ご自身が自筆で書き、証人や公証人の手数料が不要なことから費用がかからず、比較的に作成しやすい遺言書になります。
その反面、日付けの不備や押印もれといった些細なミス、パソコンやワープロで印字した文書、録音テープやビデオカメラを使い口頭で遺言するといった形式的に不備がある場合は、無効となるデメリットがあります。
そこで、自筆証書遺言の作成法と書き方について具体的に解説させて頂きます。
民法改正により、自筆証書遺言の要件が一部緩和されております。(財産目録のワープロ作成等)
法務局における遺言書の保管(平成32年7月10日施行)の場合、遺言書の検認が不要になります。
※財産目録をパソコン等にて作成した場合には、その毎葉に署名押印をする必要があります。
1.自筆証書遺言の作成方法と書き方
(1)遺言書の要件(民法968条)

遺言書を作成する際は、法的に有効な要件を満たす必要があります。自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印することが求められます。また、相続財産の目録を添付することも可能ですが、その場合は目録自体に署名と押印が必要です。これらの要件を守ることで、遺言書が法的に有効となります。
自筆証書遺言については、民法第968条で下記のように定められています。参考にご覧下さい。
《 民法968条 》
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
自筆証書遺言では、遺言者が自分で手書きで書いた全文、日付、氏名が必須です。また、押印も必要となります。もし財産目録を添付する場合、目録部分は手書きでなくても良いですが、遺言者の署名と押印が必要です。このように、遺言書作成においては慎重に要件を守ることが重要です。
(2)用紙と筆記用具

・自筆証書遺言を書く際の用紙の種類や大きさ、筆記具は自由ですが、感熱紙や鉛筆だと消える恐れがあります。ボールペンや万年筆、筆といった筆記用具で書くことをお勧め致します。
遺言書を縦書きにするか、横書きにするかに、ついても決まりがありませんので、縦書き・横書きのいずれの形式でも問題ありません。
(3)表題
・遺言書の表題について決まりはありません。ご自身で自筆証書遺言が「遺言」であることを明示するためには、表題に「遺言書」または「遺言状」というように「遺言である旨」を明示する文字を記入いたします。
(4)日付
・自筆証書遺言に書く日付は、必ず正確に年月日まで記入します。「〇〇〇〇年△△月吉日」や「平成〇〇年△△月吉日」と日付が特定出来ない場合、法的に無効となります。具体的な日付(例:2025年4月1日)を記入して下さい。
(5)氏名・住所
・自筆証書遺言に書く氏名は、戸籍の氏名を書く様にしてください。住所は必須事項ではありませんが、同姓同名の人がいる場合を想定し、住所と戸籍上の氏名を書くことで、遺言者を特定でき相続手続きがスムーズになります。
(6)押印
・認印や拇印でも大丈夫ですが、実印を重要視している日本の法制度や後々のトラブルを考えると、自らの意志で遺言書を作成したと証明できるため、実印で押印した方が賢明です。
(7)自筆証書遺言サンプル
自筆証書遺言は、様々な書き方がありますが、1つの例として上げさせて頂きます。
遺 言 書
(遺言書であることを明確にするため表題を記入します。)
遺言者〇〇 〇〇は、次のとおり遺言する。
(遺言書を作成する人)
第1条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、妻 ●● ●●(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
1 土地
所在 葛飾区○○ ○○ 丁目
地番 ○○番○○
地目 宅地
地積 ○○.○○㎡
2 建物
所在 葛飾区○○ ○○ 丁目 ○○番地○○
家屋番号 ○○番○○
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階○○.○○㎡ 2階○○.○○㎡
(不動産登記簿謄本を法務局で取得し正しく記入します。)
第2条 遺言者は、遺言者の有する次の預貯金を、長男 ●● ●●(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
○○銀行 ○○支店(店番号○○○)
① 普通・口座番号○○○○○○○
② 定期・口座番号○○○○○○○
第3条 遺言者は、遺言者の有する次の預貯金を、次男 ●● ●●(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
ゆうちょ銀行
① 通常貯金 記号○○○○○○○ 番号○○○○○○○
(通帳を確認し、銀行名、支店、預金の種類、口座番号など記入します。)
※基本的には、誰にどの財産を相続させるのか、わかるように記入していきます。
第4条 遺言者は、本遺言に記載のない、その他一切の財産を、前記 妻●● ●●に相続させる。
(遺言書に記載のない財産が出てきた場合、別途協議を行うのか、だれか一人が相続するのか記入しておきます。)
第5条 遺言者は、先祖の祭祀を主宰すべきものとして、前記 長男 ●● ●●を指定する。
(お墓や仏壇など祭祀財産を承継する人を指定しておきます。)
第6条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、前記 長男 ●● ●●を指定する。
(遺言執行者は、遺言書の内容に基づいて手続など行う人。相続人または、第三者を指定する場合があります。)
付 言
例)良き妻と子に恵まれて幸せな人生を送ることが出来ました。感謝しています。これから、家族仲良く、お互いを助け合って幸せな人生を過ごして下さい。
(付言は必須ではありませんが、ここに、ご自身のお気持ちや家族に伝えたいことなどを記入しておきます。 )
令和○○年○○月○○日
住所 東京都葛飾区○○ ○丁目○番○号
遺言者 ○○ ○○ ㊞
(日付、住所、名前を忘れずに記入し押印をして下さい。)
2.財産目録の作成方法と記載内容

これまで、財産目録は遺言者が自署(手書き)で作成することが求められていました。しかし、民法改正により、財産目録の作成方法が柔軟になり、自署によらず、ワープロで作成した目録や、証明書類(通帳のコピーや登記事項証明書など)を添付することも認められるようになりました。
これにより、遺言者は手書きにこだわらず、より簡便に遺言書を作成することができるようになりました。
(1)財産目録とは
財産目録とは、遺言書に記載される遺産の詳細を示すリストのことです。遺言者が所有する不動産、預貯金、株式、保険、貴金属など財産を整理して記載します。
- 不動産:土地や建物の所在地、面積等
- 預貯金:銀行名、支店名、口座番号等
- 株式・証券:保有している株や証券の銘柄、数量、証券口座の情報等
- 車両:車名、型式、車両番号、車体番号等
- その他の財産:貴金属や美術品など、他にも遺言で指定したい財産
(2)財産目録の作成方法
財産目録は、以下の方法で作成することができます。
財産目録をパソコン(ワープロ)で作成する方法です。この場合、目録は遺言書の本文とは別のページに作成し、遺言書に添付します。作成した目録には必ず遺言者の署名と押印が必要です。
目録を作成せず、証明書類(通帳のコピーや登記事項証明書など)を添付する方法です。この場合、各証明書類に署名と押印をする必要があります。れらの証明書類は遺言書とは別のページ(別紙1、別紙2など)として添付します。
(3)財産目録サンプル
遺言書と財産目録はセットのものになります。従って財産目録を作成する場合の遺言書の書き方は、下記の様なものになります。
遺言書
遺言者〇〇 〇〇は、次のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者の有する別紙目録第1記載の不動産を、妻 ●● ●●(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
第2条 遺言者は、遺言者の有する別紙目録第2の1記載の預貯金を、長男 ●● ●●(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
第3条 遺言者は、遺言者の有する別紙目録第2の2記載の預貯金を、次男 ●● ●●(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
第4条 遺言者は、本遺言に記載のない、その他一切の財産を、前記 妻●● ●●に相続させる。
第5条 遺言者は、先祖の祭祀を主宰すべきものとして、前記 長男 ●● ●●を指定する。
第6条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、前記 長男 ●● ●●を指定する。
令和○○年○○月○○日
住所 東京都葛飾区○○ ○丁目○番○号
遺言者 ○○ ○○ ㊞
上記に合せた財産目録を作成します。
財産目録
第1 不動産
1 土地
所在 葛飾区○○ ○○ 丁目
地番 ○○番○○
地目 宅地
地積 ○○.○○㎡
2 建物
所在 葛飾区○○ ○○ 丁目 ○○番地○○
家屋番号 ○○番○○
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階○○.○○㎡ 2階○○.○○㎡
第2 預貯金
1 ○○銀行 ○○支店(店番号○○○)
① 普通・口座番号○○○○○○○
② 定期・口座番号○○○○○○○
2 ゆうちょ銀行
① 通常貯金 記号○○○○○○○ 番号○○○○○○○
遺言者 ○○ ○○ ㊞
目録を作成せずに、通帳のコピー等を利用することも可能です。その場合、それぞれの書類に署名押印がが必要になりますので、忘れない様にして下さい。
3.遺言書保管制度とは?

自筆証書遺言を法務局に預けることができる保管制度です。この制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんのリスクを減らし、相続発生時に遺言書の有無を簡単に確認できるようになります。
(1)遺言者の手続(遺言書保管制度の利用方法)
遺言書保管制度を利用するには、遺言者本人が法務局へ出向いて手続きを行う必要があります。代理申請は認められていないため、必ず本人が直接手続きを行います。
自筆証書遺言を作成し、法務局へ持参します。なお、遺言書の様式や形式については、下記の様な条件が定められています。
- A4サイズの紙を使用(上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mm以上の余白を設ける)
- 自筆で書く(パソコン作成不可。但し財産目録作成は可)
- 日付、署名、押印を必ず記載
遺言書保管制度を利用する場合は、事前に管轄の法務局に予約する必要があります。なお、遺言書は、遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地を管轄する法務局で保管できます。各法務局の管轄区域については、法務局の公式サイトでご確認下さい。
予約方法は、法務局のオンライン予約システムを利用するか、電話または窓口で予約します。
法務局での手続きには、以下の書類が必要です。
- 自筆証書遺言書(ホチキスなどで留めない)
- 遺言書保管申請書(法務局のHPからダウンロード可能)
- 住民票の写し等(本籍及び筆頭者の記載入り、マイナンバーや住民票コード記載なし)原本
- 遺言者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 手数料3,900円(現金のみ対応)
予約した日時に法務局へ出向き、手続きを行います。職員が遺言書の形式を確認(内容の審査はしない)し、問題がなければ受理されます。手数料を納付して、最後に「遺言書の保管証」を受取ります。
遺言の保管を取り止めたい場合、保管申請の撤回を行います。遺言書の内容を変更したい場合は、一度、撤回を行い、再度保管申請を行います。なお、撤回を行えるのは、遺言書の原本が保管されている保管所のみになりますのでご注意ください。
撤回は、法務局指定の用紙(撤回書)を使用し、予約をした上で法務局に行き手続きを行います。
- 撤回書(法務局のHPからダウンロード可能)
- 遺言者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
その他、下記の事項に変更が生じた場合は、遺言書が保管されている保管所に届出を行います。(郵送も可能)
- 遺言者自身の氏名、出生の年月日、住所、本籍(又は国籍)及び筆頭者
- 遺言書に記載した受遺者等・遺言執行者等の氏名又は名称及び住所等
(2)相続人の手続き
相続人は、遺言者が亡くなった後に法務局で遺言書を確認し、証明書を取得できます。
相続人の方などが、「遺言書保管事実証明書」の請求を行うことにより、遺言書保管所に遺言書が保管されているかどうかの確認をすることが出来ます。
- 相続人、受遺者等・遺言執行者等の方
- 上記の方の親権者や後見人等の法定代理人
- 相続人であることが確認できる戸籍謄本
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 手数料800円(1通)など
相続手続で遺言書の内容を証明するため、保管されている遺言書の「遺言書情報証明書」の請求を行います。
- 相続人、受遺者等・遺言執行者等の方
- 上記の方の親権者や後見人等の法定代理人
- 法定相続情報一覧図の写し、または
- 遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍)、相続人全員の戸籍・住民票
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 手数料1,400円(1通)など
相続人等は法務局で遺言書の原本を閲覧することも可能です。閲覧は、遺言書の原本を確認する方法と画像を閲覧する方法の2種類があります。なお、閲覧には、法務局所定の「閲覧請求書」と添付書類を準備し、予約をした上での閲覧となります。
- 相続人、受遺者等・遺言執行者等の方
- 上記の方の親権者や成年後見人等の法定代理人
- 法定相続情報一覧図の写し、または
- 遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍)、相続人全員の戸籍・住民票
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 手数料1,400円(画像閲覧)、1,700円(原本閲覧)など
(3)法務省サイト(自筆遺言書保管制度)
自筆証書遺言書保管制度に関する詳細は、下記の法務省サイトをご覧ください。
・法務省(自筆遺言書保管制度)はこちらから ⇒ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
4.遺言書の作成方法と書き方 まとめ

ここまで、自筆証書遺言についての作成方法や書き方、遺言書の保管制度など、ご自身で遺言書を作成される場合の役立つ知識を掲載させて頂きました。
自筆証書遺言を作成する上で、大切なことは、きちんと法律で定められて形式にて作成することです。内容に不備が有る場合、せっかく作成した遺言書が無効にになってしまう場合もあります。もし、不安がある場合は、専門家に確認してもらう方が安心ともいえます。
当事務所では、遺言書に関するサポートを行わせて頂いております。遺言書の作成で、わからないことなどありましたら、お気軽に問合せ下さい。
»» 次の記事:遺言書は、いつ書けば良いか? »»
«« 前の記事:遺言書の種類を解説!それぞれの特徴と選び方 ««
大塚法務行政書士事務所 大塚博幸

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)