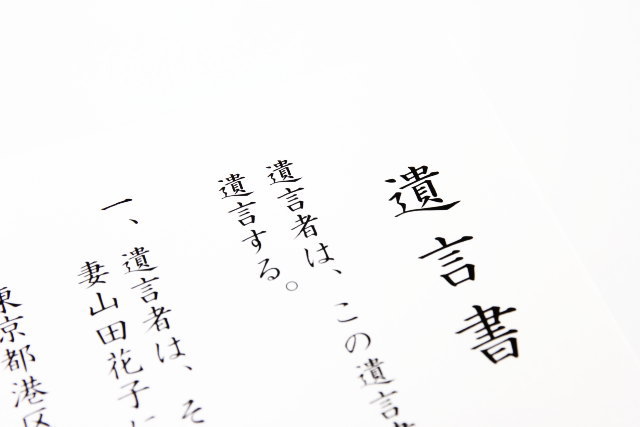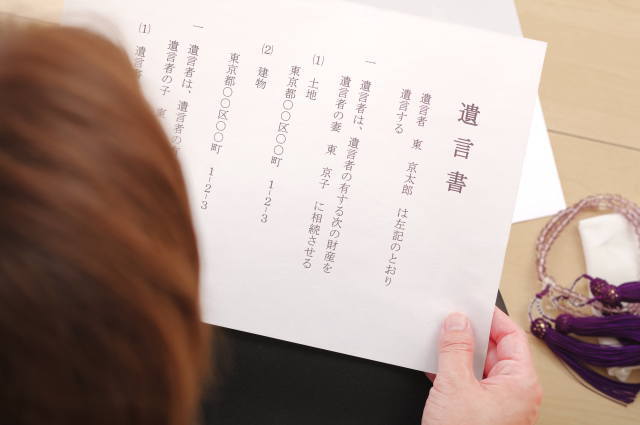・遺言執行者は、故人の遺言の内容を実現するために選ばれた人です。遺産の分割や財産の処分、債務の清算など、遺言執行者の業務は多岐にわたります。もし遺言執行者に選ばれた場合、どのような手続を行い、どのような義務を果たさなければならないのでしょうか?
この頁では、遺言執行者の行うべき義務や手続、注意点などについてわかりやすく解説いたします。もし、遺言執行者として指定された場合は、その役割を正しく理解し円滑に手続を進めるための参考にして下さい。
1.遺言執行者とは
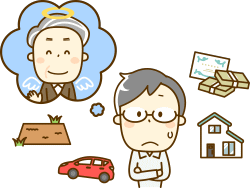
遺言執行者とは、故人(被相続人)が遺言によって指示した内容を実現するために、実際の手続きを行う人のことをいいます。遺言書の内容には、不動産や預貯金の名義変更など特定の財産を特定の相続人に渡す内容が記されていることが多く、それらを適正かつ円滑に実行する役割を担います。
遺言執行者は、相続人の代理人ではなく、独立した立場で遺言の内容を実現する責任を負います。そのため、遺言執行者には誠実かつ慎重な対応が求められることになります。
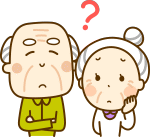
遺言執行者は、故人の遺言書によって指定される場合と、遺言書に指定がない場合に家庭裁判所によって選任される場合があります。
故人は、遺言書の中で、遺言執行者として特定の個人(相続人を含む)または法人を指定することができます。複数の遺言執行者を指定することも可能です。遺言者は、遺言執行者を指定する際、その氏名や住所などを明確に記載します。また、遺言執行者の指定を第三者に委ねることもできます。
遺言書に遺言執行者の指定がない場合や、指定された遺言執行者が就任を辞退した場合など、遺言の執行に必要な場合に、相続人などの利害関係者の申立てにより、家庭裁判所が遺言執行者を選任します。家庭裁判所は、相続関係や遺産の状況などを考慮して、適切な人物を選任します。
遺言執行者の法的な位置づけ

遺言執行者は、民法1006条~1021条に定められている法的な制度になります。遺言執行者は、相続人の単なる代行者ではなく、遺言者の意思実現という独立した目的のために職務を行います。民法1006条では、遺言者が遺言によって1人または複数人の遺言者を指定できる旨が定められています。また、その指定を第三者に委ねることも可能です。
なお、遺言執行者に指定された人は、その就任を承諾することで任務を開始します。任務開始後は、遺言の内容を相続人に通知する義務等を負うことになります。
遺言執行者の行うべき職務は、単なる形式的な作業ではなく、遺言内容の履行に関する法的義務を負った重要な役割を担うことになります。特に遺贈や認知などの法的効力が伴う行為が含まれる場合は、遺言執行者の存在は不可欠ともいえます。
遺言執行者がいると安心なケース

遺言執行者は必ずしも全ての相続で必要となるわけではありません。しかし、以下のようなケースでは、その存在が手続きの円滑化に大きく貢献し、遺言者の意思を確実に実現するために特に重要となります。
故人が遺言書で、これまで法律上の親子関係のなかった子供を認知する際、この認知の効力を発生させるためには、遺言執行者による市区町村役場への届け出が法律で義務付けられています(戸籍法第64条)。相続人や認知される子供自身がこの手続きを行うことはできません。
例えば、故人が生前に内縁の妻との間に生まれた子供を認知する遺言を残した場合などが該当し、この届け出は遺言執行者の就職の日から10日以内に行う必要があります。
故人が、法定相続人ではない第三者(友人、お世話になった人、慈善団体など)に特定の財産を遺贈する旨を遺言書に記載した場合、遺言執行者がいれば、受遺者は相続人と直接煩雑な交渉をする必要がなく、スムーズに遺産を受け取ることができます。
例えば、「〇〇株式会社に△△円を遺贈する」といった内容の遺言書がある場合です。さらに、遺言執行者がいる場合、遺贈の履行は原則として遺言執行者のみが行うことができ(民法第1012条2項)、相続人は遺贈の対象となった財産を勝手に処分することはできません。
相続人が多数いる場合や、亡くなった方の配偶者と前妻の子が相続人となるケース、あるいは代襲相続や数次相続が発生しているなど、相続関係が複雑な場合、相続人全員で遺産分割協議を行うことは困難となる可能性が高くなります。
しかし、このような状況において遺言執行者が選任されており、遺言書に具体的な遺産の分け方が明記されていれば、遺言執行者はその内容に従って淡々と手続きを進めることができます。その結果、相続人間の紛争を予防し、早期に遺産承継を実現することが可能です。
故人が、「自宅は長男〇〇に」「預金は長女△△に」というように、特定の財産を特定の相続人に直接承継させる遺言を残した場合、遺言執行者はその実現に必要な名義変更などの手続きを単独で行えます(民法第1014条)。これにより、相続人間での遺産分割協議は不要となり、スムーズな財産承継が可能です。
相続人の中に、長期間連絡が取れない行方不明者がいる場合、通常の遺産分割協議を行うためには、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうなどの煩雑な手続きが必要になります。
しかし、遺言執行者が選任されており、遺言書によって具体的な遺産の分け方が指定されている場合には、遺言執行者は遺言書の内容に従って手続きを進めることができるため、行方不明者の存在が遺産承継の妨げになるのを防ぐことができます。
不動産、預貯金、株式、投資信託、自動車、貴金属、美術品など、故人の残した財産の種類が多い場合、それぞれの名義変更や換金、引き渡し手続きは煩雑になることがあります。遺言執行者が一元的にこれらの手続きを進めることで、相続人の負担を軽減し、スムーズな遺産承継が期待できます。
相続人間で感情的な対立があったり、遺産分割について意見の不一致が予想されたりする場合、遺言執行者が中立的な立場で遺言書の内容を実行することで、紛争の激化を防ぎ、円滑な解決を促すことも可能です。遺言執行者は、相続人の利益を考慮しつつ、遺言者の意思を尊重する役割が求められます。
例えば、未公開株式の評価や譲渡、複雑な税務申告、海外にある財産の処分など、専門的な知識や煩雑な手続きが必要となる場合、遺言執行者に専門家(弁護士、司法書士、税理士など)が選任されていると、スムーズに手続きを進めることができます。
相続人の中に高齢者や病気療養中の方、遠方に住んでいる方など、ご自身で相続手続きを行うことが難しい方がいる場合、遺言執行者が代わりに手続きを進めることで、相続人の負担を軽減できます。
遺言書で祭祀承継者が指定されている場合、その指定に基づいて墓地の名義変更などの手続きを行うのも遺言執行者の役割となることがあります。
2.遺言執行者に選ばれたら
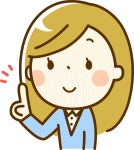
あなたが遺言執行者に選ばれた際に、具体的にどのようなステップを踏む必要があるのか、その流れと最初に行うべき重要な事項について詳しく解説していきます。故人の大切な想いを実現するために、一つずつ確認していきましょう。
遺言執行の流れの全体像
遺言執行者の仕事は、多岐にわたりますが、その全体像を把握しておくことは、スムーズに職務を遂行する上で非常に重要です。一般的に、遺言執行は以下の段階を経て進行します。それぞれの段階で、遺言執行者は様々な手続きを行い、関係者との連携を図りながら、遺言書の内容を実現していきます。
遺言書の存在を確認し、その種類と内容を把握します。遺言書の種類によって、その後の手続きが大きく異なります。
ご自身の状況を考慮し就任を決定したら、その旨を相続人に通知します。
故人の財産を調査し、目録を作成して相続人に交付します。
遺産が適切に引き渡されるまで管理します。
遺言書に従い、名義変更や財産の引き渡しなどを行います。
手続きの進捗状況や完了を相続人に報告します。
遺言執行者は報酬を請求することができます。
ステップ1:まずは遺言書を確認(開封と検認の手続き)
遺言執行者に指定されたら、まず遺言書の所在を確認し、その種類を特定します。遺言書の種類によって、その後の手続きが大きく異なるためです。
家庭裁判所における開封と検認の手続きが法律で義務付けられています。検認の主な目的は、相続人に対し遺言書の存在と形式的な有効性(日付、署名、押印等)を明確に示し、遺言書の偽造・変造を防止することにあります。
検認を経なければ、原則として遺言書に基づく遺産分割や名義変更等の手続きは行えません。ただし、検認は遺言書の内容そのものの有効性を保証するものではないことを理解しておく必要があります。遺言執行者は、これらの遺言書である場合は、速やかに家庭裁判所へ検認の申立てを行う必要があります。
遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人が作成するもので、内容と手続きが法律に従って行われるため、原則として家庭裁判所での開封や検認は不要です。これにより、遺言執行者は速やかに遺言の執行に着手できます。
遺言執行者は、まず遺言書の種類を確認し、必要な手続きを迅速に進めることが求められます。
ステップ2:就任の意思決定と相続人への通知
遺言執行者に指定されたとしても、必ずその役割を引き受けなければならないわけではありません。遺言執行は、時間や労力を要する責任の重い仕事です。そのため、指定された方は、ご自身の状況(健康状態、時間的な余裕、専門知識の有無など)を慎重に考慮し、就任するかどうかを自由に決定することができます。
就任の意思を固めたら、速やかにその旨を相続人に通知する必要があります。この通知は、書面で行うことが一般的であり、以下の内容を記載することが望ましいとされています。
- 遺言執行者に就任する意思があること
- 遺言執行者としての氏名と連絡先
- 今後の手続きの進め方に関する簡単な説明
遺言執行者は、任務を開始したら、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知する義務があります(民法第1007条2項)。遺言書の内容を正確に把握し、相続人へ速やかに伝達することは、円滑な遺言執行の第一歩となるからです。
この通知によって、相続人は遺言執行者が誰であるか、そして今後どのように手続きが進んでいくのかを知ることができます。相続人との信頼関係を築き、円滑な遺言執行を進める上で、この最初の通知は非常に重要です。
ステップ3:遺産の調査と財産目録の作成・交付
遺言執行者に就任したら、次に着手すべき最も重要な義務の一つが、故人(被相続人)が遺した全ての財産を調査し、その詳細な目録を作成することです(民法第1011条1項)。この財産目録は、遺産の種類や総額を明確にし、今後の遺産分割や遺言の執行手続きを進める上での基礎となる、非常に重要な情報となります。
遺産調査では、故人が亡くなった時点において所有していた全ての財産を把握する必要があります。
- プラスの財産: 現金、預貯金、不動産、有価証券、自動車、貴金属、美術品など
- マイナスの財産: 借金、住宅ローン、未払いの税金、損害賠償債務など
調査の結果に基づいて作成する財産目録には、遺産の種類、所在、数量、そして評価額などを、可能な限り詳しく記載する必要があります。
- 不動産: 所在、地番、種類、面積、家屋番号(登記簿謄本に基づき記載)
- 預貯金: 金融機関名、支店名、口座番号、死亡日時点の残高(通帳や残高証明書に基づき記載)
- 有価証券: 証券会社名、口座番号、銘柄、株数、死亡日時点の評価額(取引残高報告書に基づき記載)
- 借金: 債権者名、借入金額、契約内容(契約書に基づき記載)
作成した財産目録は、遅滞なく相続人に交付する義務があります(民法第1011条2項)。これは、相続人に対して遺産の状況を正確に伝え、その後の手続きへの理解と協力を得るために不可欠です。
- 徹底的な調査: 遺漏がないよう、あらゆる可能性を考慮して調査します。
- 正確な評価: 相続税申告などにも影響するため、可能な限り正確な評価を行います(必要に応じて専門家に相談しましょう)。
- 証拠の保管: 調査で得た書類(通帳コピー、登記簿謄本、契約書など)は適切に保管します。
- 相続人との連携: 情報提供を求めたり、調査状況を共有することも有効です。
遺産の調査と財産目録の作成は、遺言執行の根幹となる重要なステップです。遺言執行者はその責任を深く認識し、丁寧かつ正確に職務を遂行する必要があります。
ステップ4:遺産の管理(善良な管理者の注意義務)
遺産の調査が完了し、財産目録を作成したら、遺言執行者は、遺産が相続人や受遺者に適切に引き渡されるまで、その財産を管理する責任を負います。この遺産管理において、遺言執行者には、法律上の重要な義務である「善良な管理者の注意義務」が課せられます(民法第1012条3項・民法第644条準用)。
遺言執行者が故人の遺産を管理する際に負う、その人の立場から見て通常求められる、より丁寧な注意義務のことです。自分の物と同じように扱うのではなく、他人の大切な物を預かっているという意識で、状況に合わせて適切に管理する義務と考えると分かりやすいでしょう。具体的に何をするかは、遺産の種類や状況によって変わってきます。
- 遺産の現状把握:まず、遺産の具体的な種類、数量、状態を正確に把握することが重要です。
- 適切な管理方法の選択: 各遺産の性質に応じて、最も適切な維持・保全措置を講じる必要があります。
- 記録の徹底: どのような管理を行ったのか、その内容と日付を詳細に記録しておくことが重要です。
- 相続人への情報共有:管理の状況について、必要に応じて相続人に情報を共有することも、信頼関係を維持する上で大切です。
- 専門家への相談:遺産の管理方法に不安がある場合は、専門家に早めに相談しましょう。
遺言執行者がこの善良な管理者の注意義務を怠り、故意または過失によって遺産を減少させたり、損害を与えたりした場合、相続人に対して損害賠償責任を負う可能性があります(民法第646条、民法第709条)。
遺産の管理は、遺言執行者の重要な責務であり、相続人の大切な財産を守るために、慎重かつ適切に行う必要があります。
ステップ5:遺言内容の執行(故人の意思を実現)
遺産の調査、財産目録の作成、そして遺産の管理と並行して、遺言執行者の最も重要な任務である「遺言内容の執行」を進めていきます。これは、遺言書に書かれた故人の最終的な意思を実現するための手続きであり、遺言執行者の中心的な役割と言えます。
遺言の内容は多岐にわたりますが、主な執行行為としては以下のようなものがあります。
遺言書で特定の相続人や受遺者に不動産を相続させる旨の記載がある場合、その名義を変更する手続きを法務局で行います(相続登記)。これには、必要書類の収集、申請書の作成、法務局への申請などが含まれます。
遺言書で指定された相続人や受遺者に対して、預貯金の払い戻し手続きを行い、指定された口座へ移管したり、有価証券の名義を変更したり、引き渡したりします。これには、金融機関や証券会社への連絡、必要書類の提出などが含まれます。
相続人以外の第三者(受遺者)に特定の財産を遺贈する旨の記載がある場合、その財産を受遺者に引き渡す手続きを行います。
遺言書に特別な指示がある場合や、遺産の範囲内で相続債務を清算する必要がある場合に、債権者に対して支払いを行います。
まず、遺言書の内容を隅々まで正確に理解することが不可欠です。不明な点があれば、相続人や必要に応じて専門家に確認します。
手続きを進めるにあたっては、法務局、金融機関、証券会社、市区町村役場など、多くの関係機関との連携が必要となります。
各手続きに必要な書類を漏れなく収集し、正確に作成する必要があります。
手続きによっては期限が定められている場合があるため、注意が必要です。
執行の進捗状況について、適宜相続人に報告し、理解と協力を得るように努めます。
遺言内容の執行は、故人の最終的な意思を尊重し、実現するための重要な過程です。遺言執行者は、その責任の重さを認識し、誠実に職務を遂行する必要があります。
ステップ6:遺言執行の完了と相続人への報告、報酬請求
遺言執行者は、遺言書の内容に基づき、遺産の調査、管理、名義変更、引き渡しなどの一連の手続きを完了させることで、その任務を終えます。遺言執行が完了した際には、その経過と結果を相続人に対して遅滞なく報告する法的義務があります(民法第1012条3項・準用645条)。
遺言執行者は、全ての手続きが終了した後、速やかにその経過と結果を相続人に報告しなければなりません。この報告は、遺言執行者がその任務を適切に遂行したことを相続人に示し、遺産に関する透明性を確保するために不可欠です。報告には、一般的に以下の内容が含まれます。
- どのような遺産について、どのような執行手続きを行ったかの詳細
- 全ての遺産の最終的な状況(名義変更、引き渡しなどが完了したかの明確な説明)
- 遺産から支出された費用の内訳と金額(領収書等の証拠書類を添付することが望ましい)
- 手続きの過程でした 重要な事項や問題点、およびその対応
- 必要に応じて、関連書類の写し(登記完了後の謄本、金融機関の取引明細など)
遺言執行者は、その労力に応じて相続人に対して報酬を請求する権利を有します(民法第1018条、民法第648条等準用)。報酬額は、以下のいずれかの方法で決定されます。
- 遺言書に定めがある場合: 原則としてその金額に従いますが、不相当に高額な場合は減額請求の可能性があります。
- 相続人との協議: 遺言書に定めがない場合は、遺産の額、執行事務の内容、労力、時間などを考慮して、相続人全員と協議して決定します。
- 家庭裁判所の決定:相続人間で協議が整わない場合は、遺言執行者が家庭裁判所に報酬額の決定を申し立てることができます。
報酬を請求する時期は、遺言執行の任務が完了し、最終報告を行う際と併せて行われることが一般的です。遺言執行者は、行った業務の内容とそれに要した労力を明確に示し、相続人の理解を得るように努めることが重要です。
3.遺言執行者がおこなうべき義務(民法)

民法には、遺言執行者が具体的にどのような行為を行うべきか、その権限と義務が明確に定められており、遺言者の最終的な意思を適正に実現するための法的根拠となっています。以下に、民法に定められた遺言執行者が行うべき主な内容と、その根拠となる条文を解説します。
遺言執行者に指定された方は、その役割を引き受ける意思を明確に示し(就職を承諾)、その後は遅滞なく、遺言の内容に従った財産の管理や処分など、具体的な遺言の執行という任務を開始する義務を負います。
遺言執行者は、任務を開始した後、遺言書に何が書かれているのか、誰にどの財産が相続・遺贈されるのかといった遺言の内容を、相続人に対して速やかに通知する必要があります。通常は、遺言書のコピーを送付するなどの方法が取られます。
遺言執行者は、故人が亡くなった時点で所有していた全ての財産(不動産、預貯金、有価証券、動産など)を調査し、その種類や数量、評価額などを詳細に記載した財産目録を速やかに作成し、相続人に交付する義務があります。相続人の求めがあった場合には、相続人の立ち会いのもとで目録を作成するか、公平性を期すために公証人に作成を依頼する必要があります。
遺言執行者は、遺産が最終的に相続人や受遺者に適切に引き渡されるまで、その財産を管理する責任を負います。この管理においては、自己の財産を管理する以上に注意深く、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)をもって行うことが求められます。
遺言執行者は、相続人から遺言執行の進捗状況について報告を求められた場合には、いつでもその状況を報告する義務があります。また、遺言執行の任務が全て完了した後には、どのような手続きを行い、どのような結果になったのかを、遅滞なく相続人に報告する必要があります。
遺言書の内容を実現するために、遺言執行者は様々な法律行為や事実行為を行う義務があります。
これらを行うことで、遺言執行者は故人の最終的な意思を尊重し、その実現に向けて民法に定められた責任を果たすことが求められます。
4.遺言執行者として知っておきたい大切なこと
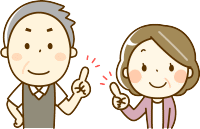
もしあなたが遺言執行者に選ばれたら、それは故人の大切な想いを託されたということです。でも、一体何に気をつけて、どう進めたら良いのでしょうか? 難しく考えずに、大切なポイントを一つずつ見ていきましょう。
一番大切なのは、遺言書に何が書いてあるかをしっかり理解することです。「誰に何を渡したいのか」「どんな願いが込められているのか」、故人の気持ちを想像しながら丁寧に読み解きましょう。もし分かりにくい言葉や内容があったら、他の相続人や専門家と一緒に確認することが大切です。
遺産を受け取る相続は、どんな手続きが進んでいるのか、ちゃんと知りたいと思っています。だから、遺言執行者は、手続きの進み具合を分かりやすく伝えたり、困っていることや疑問に思っていることを聞いたりしながら、みんなで協力して進めることが大切です。一人で勝手に進めてしまうと、「ちゃんと教えてくれなかった」と不満が出てしまうこともあります。
故人がどんな財産を残したのか、もれなくリストアップすることが大切です。預貯金、家、株、車…プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も調べる必要があります。このリスト(財産目録)は、今後の手続きの土台となる、とても大切なものです。もし調べるのが大変なら、他の相続人に協力してもらったり、専門家に手伝ってもらうことも考えましょう。
遺言執行者は、遺産を相続人や受け取るべき人にきちんと引き渡すまで、その財産を預かっている立場です。だから、自分の物以上に丁寧に、大切に管理する責任があります。例えば、空き家になっている家があれば、傷まないように気をつけたり、預金は安全な場所に保管したりする必要があります。
遺産相続の手続きには、いくつか期限があるものがあります。例えば、相続税の申告や、相続放棄をする期間などです。これらの期限を過ぎてしまうと、困ったことになる可能性も。焦らずに一つずつ進めることが大切ですが、「いつまでに何をしなければいけないか」という期限は、頭に入れておきましょう。
遺言の手続きは、一般の人には難しく感じることもたくさんあります。「これってどうすればいいんだろう?」と迷うことがあれば、遠慮せずに専門家に相談しましょう。費用はかかるかもしれませんが、後々のトラブルを防ぐためには大切なことです。
どんなに頑張っても、人間なのでミスをしてしまうこともあるかもしれません。もし手続きで失敗をしてしまった場合は、すぐに正直に相続人に伝え、どのように対応すべきかを相談することが大切です。隠したり、ごまかしたりすると、信頼を失ってしまう可能性があります。
遺言執行の期間は、長くかかることもあります。慣れない手続きや、相続人とのやり取りで、精神的にも肉体的にも疲れてしまうこともあるでしょう。無理をしすぎず、困ったときは周りの人に頼ったり、休息を取ることも忘れないでください。
遺言執行者は大変な役割ですが、故人の大切な想いを繋ぐ、とても意味のある仕事です。焦らず、周りの人と協力しながら、一つずつ進めていきましょう。
5.遺言執行者に関するQ&A
はい、遺言執行者に指定されたとしても、必ず就任しなければならないわけではありません。ご自身の状況などを考慮して、就任を辞退することができます。辞退する場合は、相続人にその旨を明確に伝えることが大切です。
遺言執行者の任期は、遺言の執行が完了するまでとされています。具体的には、遺言書の内容に従って、遺産の管理、名義変更、引き渡しなどの手続きが全て完了し、相続人への報告が終わるまでが任期となります。
遺言執行者がその任務を怠ったり、不正な行為をした場合など、正当な理由があれば、相続人は家庭裁判所に遺言執行者の解任を請求することができます(民法第1019条)。解任が認められるかどうかは、家庭裁判所の判断によります。
遺言書に書かれていない財産(遺漏財産)が見つかった場合、遺言執行者の職務範囲を超えるため、原則として遺言執行者はその財産を遺言に基づいて処分することはできません。
この遺漏財産については、相続人で遺産分割協議を行い、その分け方を決める必要があります。必要に応じて、改めて遺産分割協議書を作成することになります。
遺言書で複数の遺言執行者が指定されている場合、遺言書に職務の分担方法が定められているときは、その定めに従います。
定めがない場合は、各遺言執行者が単独で職務を行うことができます。ただし、遺言執行者間で協議して職務を分担することも可能です。重要な行為については、共同で行うことが望ましい場合もあります。
6.遺言執行者とは? まとめ

この記事では、故人の遺言内容を実現するために重要な役割を担う遺言執行者について、その法的な位置づけから、具体的な手続きの流れ、そして職務を遂行する上での注意点までを詳しく解説しました。
遺言執行者は、相続人の単なる代理人ではなく、遺言者の最終的な意思を実現するという独立した使命を負っています。その業務は、遺言書の確認から始まり、遺産の調査、管理、そして遺言内容の執行、相続人への報告と多岐にわたります。
特に、認知を含む遺言、遺贈がある場合、相続人が複数いる場合など、特定のケースにおいては遺言執行者の存在が手続きの円滑化と遺言者の意思の確実な実現に大きく貢献します。
遺言執行者に選ばれた際には、その責任の重さを理解し、遺言書の内容を正確に把握するとともに、相続人との良好なコミュニケーションを心がけることが大切です。また、遺産管理における注意義務や、法的手続きの遵守も重要なポイントとなります。
もし手続きに不安を感じたり、判断に迷うことがあれば、ためらわずに専門家に相談することも、円滑な遺言執行を進める上で有効な手段です。
遺言執行者の役割は決して楽ではありませんが、故人の大切な想いを未来へと繋ぐ、非常に意義深いものです。この記事が、遺言執行者として選ばれた皆様が、その役割を正しく理解し、円滑に職務を遂行するための一助となれば幸いです。
»» 次の記事:遺言書で寄付はどうやるの?具体的な方法を徹底解説 »»
«« 前の記事:遺言書(自筆)が発見された!どうすれ良いか?解説いたします。 ««
大塚法務行政書士事務所 大塚博幸

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)