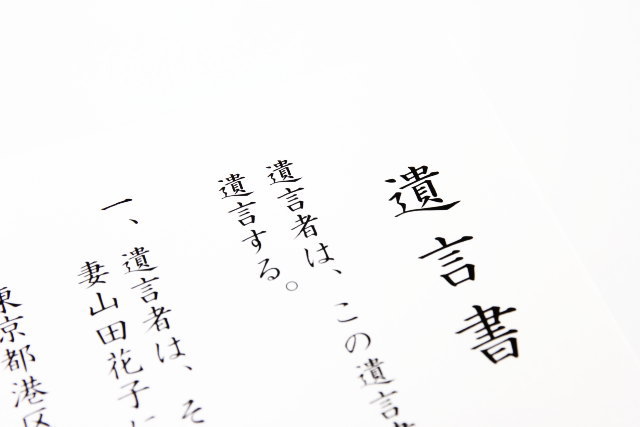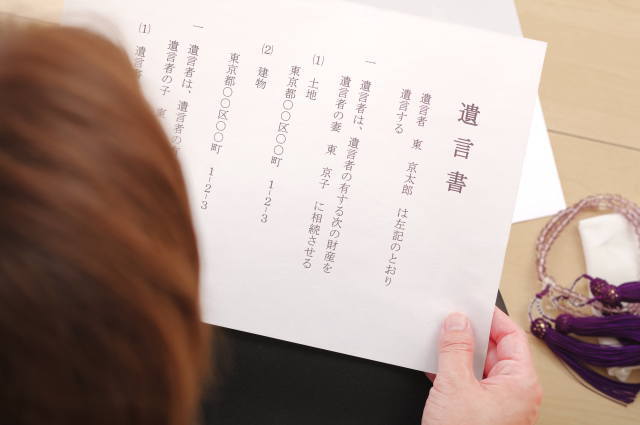・人生の終盤にさしかかると、自分の財産がどのように分けられるか、家族の未来がどうなるかを考えることが非常に重要です。
・人生の終盤にさしかかると、自分の財産がどのように分けられるか、家族の未来がどうなるかを考えることが非常に重要です。
遺言書を作成することで、残された家族や親しい人々の負担を減らし、円満な相続を実現することができます。特に、相続に関して不安を抱えている方々にとっては、遺言書が非常に有効な手段となります。
この記事では、遺言書を残すべき方々について、具体的なケースを挙げて解説します。
1.そもそも遺言書とは?

遺言書とは、故人がその死後にどのように財産を分けたいかを記した法的効力を持つ文書です。遺言書があることで、相続人同士の争いを防ぐことができ、また意志通りに財産を分配することができます。
遺言書を作成するメリット
遺言書があることで、遺産分割協議が不要になり、相続人間のトラブルを回避することができます。特に遺産を巡る争いが起こりやすい場合に有効です。
遺言書を作成する際には遺留分に注意が必要です。遺留分とは、相続人が最低限受け取る権利がある財産の割合であり、遺言書でこれを侵害しないようにする必要があります。
2.遺言書がある場合と無い場合の違い
遺言書があると、相続時のトラブルを避け、故人の意志通りに財産を分けることができます。逆に遺言書がない場合、法定相続分に従って遺産が分けられ、相続人同士の意見対立が起きることがあります。ここでは、遺言書がある場合とない場合の違いを具体例で説明します。
例:遺産が3000万円の場合
例として妻と子供が2人の場合、法定相続分に従い以下のように分けられます。
- 妻:1/2(1,500万円)
- 子どもA:1/4(750万円)
- 子どもB:1/4(750万円)
しかし、遺産分割協議が必要になり、意見の対立が生じる可能性もあります。
遺言書に「妻に全ての財産を相続させる」と記載した遺言書を作成することも可能です。但し、子供には遺留分があるため、遺留分を考慮した上で作成する必要があります。(遺留分を考慮しないと争いに発展する可能性があります。)
- 妻が受取る額:2,250万円
- 子供A:375万円(遺留分=法定相続分の1/2)
- 子供B:375万円(遺留分=法定相続分の1/2)
上記のように、遺言書を作成することにより、法定相続分と違った分け方が可能になります。お子さんの1人に多く渡したい場合も、同様に遺言書を作成しておけば、遺産分割協議での争いを防ぐことも可能になります。
ここでは、特に遺言書を残した方が良い方について、具体例を上げて下記に解説いたします。
3.子供達の仲が悪い方
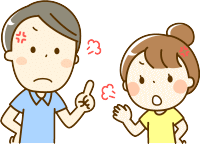
遺産相続が家族間での争いの原因になることがあります。特に、子ども達が仲が悪い場合、相続に関して意見が対立しやすくなります。
遺言書がないと、法定相続分に従って遺産が分配され、結果的に分割方法に争いが生じることが考えられます。ここでは、子ども達が仲が悪い場合に遺言書を作成するメリットを具体的な例で説明します。
① 遺言書がない場合
相続人が長男、次男、長女の3人の場合、法定相続分に従って遺産は分けられますが、もし遺産が不動産や動産など分割が難しい財産であれば、協議が難航します。たとえば、遺産が不動産であった場合、売却せざるを得なくなる可能性があり、兄弟間で争いが生じる原因となります。
(例:遺産が3,000万円の場合)
- 長男:1/3(1,000万円)
- 次男:1/3(1,000万円)
- 長女:1/3(1,000万円)
② 遺言書がある場合
遺言書に「長男に自宅を相続させる」「次男と長女には500万円ずつ渡す」と明記しておけば、相続人間の意見対立を防ぐことができます。
(例:遺産が3,000万円の場合)
- 長男:自宅(評価額2,000万円)
- 次男:500万円
- 長女:500万円
次男、長女の遺留分は、各500万円になります。この様な内容で作成しておけば、不要な争いを避けることが出来ます。
 兄弟仲が悪いと相続が発生した場合もスムーズな遺産分割協議ができません。遺言を残しておくことにより、遺産分割協議も必要なくなり、スムーズな相続手続ができます。
兄弟仲が悪いと相続が発生した場合もスムーズな遺産分割協議ができません。遺言を残しておくことにより、遺産分割協議も必要なくなり、スムーズな相続手続ができます。
遺言書の中に「なぜ、そのような内容にしたのか。」、「以後、兄弟仲よく暮らすように。」など、付言事項も記載しておきましょう。
4.子供がいない ご夫婦の方
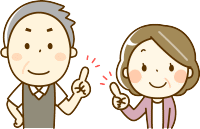
子どもがいない夫婦の場合、遺産相続は配偶者や故人の親、兄弟姉妹が対象となります。この場合、遺言書がないと相続人間での分配に問題が起きやすく、特に配偶者以外の親や兄弟姉妹に遺産が分けられることがあるため、遺言書を作成しておくことが非常に重要です。
ここでは、子どもがいない夫婦の例を通して、遺言書の必要性を説明します。
① 遺言書がない場合
子どもがいない場合、法定相続分に従い、遺産は配偶者と故人の親や兄弟姉妹に分けられます。たとえば、親が健在であれば、配偶者2/3、親1/3で遺産を分けることになります。相続人間で意見が分かれることがあるため、後の争いを防ぐためにも遺言書が役立ちます。
(例:遺産が3,000万円の場合)
- 配偶者:2/3(2,000万円)
- 故人の親:1/3(1,000万円)
※故人の親が2人とも健在の場合は、1000万円/2=500万円ずつ相続。
- 配偶者:3/4(2,250万円)
- 故人の兄弟姉妹:1/4(750万円)
※兄弟姉妹が複数いる場合、この1/4を兄弟姉妹で分割します。例えば、兄弟姉妹が2人なら、各兄弟姉妹は375万円を相続することになります。
② 遺言書がある場合
故人の親には遺留分があるため、遺留分を考慮して遺言書を作成する必要があります。一方、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書に「配偶者に全財産を相続させる」と記載しておけば、配偶者が遺産の全てを相続することができます。
(例:遺産が3,000万円の場合)
- 配偶者:5/6(2,500万円)
- 故人の親:1/6(500万円)
※故人の親が2人とも健在の場合は、500万円/2=250万円ずつ相続。
- 配偶者:3,000万円
- 故人の兄弟姉妹:0円(兄弟姉妹に遺留分はありません。)
遺言書を作成することにより、配偶者に多くの財産を相続させることが可能になります。また、両親、兄弟に特定の財産等を相続させることも可能です。
 子供がいない夫婦の場合、どちらか一方が亡くなれば、もう一方が必ず全財産を相続するとは限りません。亡くなった配偶者に親や兄弟、甥姪などがいれば、その人にも財産を相続する権利があります。
子供がいない夫婦の場合、どちらか一方が亡くなれば、もう一方が必ず全財産を相続するとは限りません。亡くなった配偶者に親や兄弟、甥姪などがいれば、その人にも財産を相続する権利があります。
配偶者に全財産又は、なるべく多く相続させたい。と考えている場合は、その旨を遺言書にして下さい。兄弟姉妹には遺留分が無いので全財産を相続させるが可能です。※両親には遺留分があります。
5.独身で相続人の いない方

独身者で相続人がいない場合、相続を受けるべき人がいないため、遺言書が非常に重要になります。法定相続人がいない場合、遺産は最終的に国に帰属しますが、遺言書を残しておくことで、自分の希望に沿った相続人を指定することができます。特に、友人や親しい人に財産を残したい場合、遺言書の存在が大きな役割を果たします。
① 遺言書がない場合
相続人がいない場合、最終的には国の財産として国庫に帰属することになります。親しい友人や知人には何も渡らないことになります。
- 相続人なし:最終的に国庫に帰属
② 遺言書がある場合
遺言書に「全財産を親しい友人Bに遺贈する」と記載しておけば、遺産はBさんに引き継がれます。このように、遺言書で希望する相続先を指定しておくことで、法定相続人がいない場合でも、自分の意志を反映させることができます。
- 親しい友人B:全額
※受遺者には、相続税等の税金が発生します。
遺言書が無い場合、国庫に帰属することになりますが、例えば所有する不動産を慈善団体などに寄付したい場合など遺言書に遺贈することを記載しておけば、遺言書で指定した人が相続することも可能になります。
また、ペットを飼育されている場合には、遺言書に負担付遺贈を記載しておき、ご自身が亡くなった後、財産を贈与する代わりにペットの面倒をみてもらうなどの遺言書を作成することも可能です。
このように、独身で相続人がいない場合でも遺言書を作成しておくことで、自分の意志を明確に伝え、遺産の管理や分配をスムーズに行うことができます。
 全く身寄りがない人の財産は、最終的には国の財産として、国庫に帰属することになります。しかし、全く身寄りのない人であっても、実際には色々な人にお世話になって生活しております。その様なお世話になった人や特定の施設等に財産を寄付したいという方も多いかと思います。
全く身寄りがない人の財産は、最終的には国の財産として、国庫に帰属することになります。しかし、全く身寄りのない人であっても、実際には色々な人にお世話になって生活しております。その様なお世話になった人や特定の施設等に財産を寄付したいという方も多いかと思います。
この様な場合、遺言書を作成することにより、ご自身の希望に沿って財産を有効に生かすことができます。
6.内縁の妻がいる方
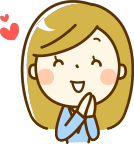
内縁の妻がいる場合、法的な結婚関係にないため、法定相続人には含まれません。内縁の妻に遺産を残したい場合は、遺言書を作成することが非常に重要です。
遺言書を作成せずに亡くなると、遺産は法定相続人(例えば、子供や親)に分配されるため、内縁の妻が遺産を受け取ることはありません。遺言書を作成することで、内縁の妻に遺産を引き継がせることができます。
① 遺言書がない場合
内縁の妻は法定相続人ではないため、財産を受け取ることができません。代わりに、法定相続人が財産を相続します。
- 相続人が親の場合: 親が全財産を相続
- 相続人が兄弟姉妹のみの場合 :兄弟姉妹が全財産を相続
※内縁の妻には何も相続されません。この場合、内縁の妻が住んでいた自宅も相続人に引き継がれ、退去を求められる可能性があります。
② 遺言書がある場合
遺言書があれば、内縁の妻に財産を遺贈することが可能です。例えば、以下のように指定することで、内縁の妻の生活を守ることができます。
- 内縁の妻に預貯金を遺贈
- 内縁の妻に自宅を遺贈し、残りの財産を親または兄弟姉妹に分与
(例:遺産が3,000万円の場合)
- 内縁の妻:2,500万円
- 故人の親:500万円(遺留分)
- 内縁の妻:3,000万円(遺贈)
- 兄弟姉妹:0円(兄弟姉妹には遺留分がないため、全額遺贈可能)
遺言書を作成することにより、上記の様な分配も可能になります。但し、遺言書を作成する際には、遺留分を考慮した上で作成しないと、新たなトラブルに発展する可能性がありますので、ご注意ください。
自筆証書より公正証書で遺言書を残した方が、紛失・改ざんなども防ぐことができ安心度が高くなります。
 一緒に暮らしている妻がいるが正式に入籍していない。自分が死んだ後の相続が心配という方。長年一緒に夫婦として生活していても、入籍していなければ相続権はありません。本人が亡くなると、親族が出てきて、今まで住んでいた家を追い出される場合が有ります。
一緒に暮らしている妻がいるが正式に入籍していない。自分が死んだ後の相続が心配という方。長年一緒に夫婦として生活していても、入籍していなければ相続権はありません。本人が亡くなると、親族が出てきて、今まで住んでいた家を追い出される場合が有ります。
この様な場合、財産を内縁の妻に遺贈すると言う遺言書を作成しておく必要があります。
7.主な財産が 自宅の土地と建物の方
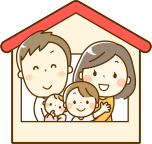
自宅の土地や建物は、現金とは異なり簡単に分割できないため、相続時にトラブルが発生しやすい財産の一つです。遺言書がない場合、相続人間で共有状態になり、売却や処分の際に意見がまとまらないケースもあります。
こうした問題を回避するためには、遺言書を作成し、具体的な相続方法を決めておくことが重要です。
① 遺言書がない場合
法定相続分に従って自宅を共同所有することになりますが、不動産は現金のように単純に分割できません。
- 配偶者:1/2
- 長男:1/4
- 次男:1/4
この場合、自宅を3人で共有することになり、売却や活用の際に全員の同意が必要となります。意見が合わず、トラブルに発展する可能性があります。
- 兄:1/2
- 弟:1/2
兄弟姉妹間で共有することになりますが、どちらかが住み続けたい場合、もう一方の持分を買い取る必要が生じます。資金がない場合、やむを得ず売却するケースもあります。
② 遺言書がある場合
遺言書を作成し、自宅の所有者を明確にすることで、スムーズな相続が可能になります。
- 配偶者:自宅
- 子ども2人:代償金として現金を受け取る(配偶者が現金を用意できる場合)
このように指定しておくことで、自宅が分割されず、配偶者が引き続き住み続けることができます。
- 長男:自宅
- 次男:代償金として現金を受け取る(長男が支払える場合)
長男が自宅に住み続けたい場合、次男への代償分を用意する必要があります。
③ 遺言書の作成ポイント
共有状態を避けるため、単独の相続人を指定する。
他の相続人へ現金を支払う必要がある場合、その準備をどうするか検討。
売却して得た現金を分配する方法も記載可能。
配偶者に「配偶者居住権」を設定し、住み続けられるようにする。
 自宅の土地・建物は相続トラブルの原因になりやすいため、遺言書で明確に指定することが重要です。特に、誰が相続するのか、代償金の支払い方法、売却の可否などを事前に決めておくことで、相続人間の争いを防ぐことができます。
自宅の土地・建物は相続トラブルの原因になりやすいため、遺言書で明確に指定することが重要です。特に、誰が相続するのか、代償金の支払い方法、売却の可否などを事前に決めておくことで、相続人間の争いを防ぐことができます。
8.事業を営んでいる方
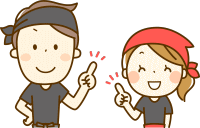
事業を営んでいる方が遺言書を作成することは、事業の継続や相続トラブルを防ぐために非常に重要です。個人事業主と法人(株式会社)では事業用資産や相続財産の取り扱いが異なりますが、いずれの場合でも遺言書を適切に作成することで、スムーズな事業承継が実現できます。
① 遺言書がない場合
遺言書がない場合、事業用資産や株式の分割が法定相続分に基づいて行われます。この場合、事業用資産(店舗、設備、営業権など)が複数の相続人で分割されるため、事業の運営に支障をきたしたり、相続税を支払うために事業用資産を売却しなければならない場合があります。
例えば、相続人が配偶者と子ども2人(長男・次男)の場合、法定相続分に従い、事業用資産と個人資産が以下のように分割されることになります。
- 配偶者:1/2
- 長男:1/4
- 次男:1/4
このように事業用資産が分散されると、経営が困難になり、相続税の支払いのために事業用資産の売却を余儀なくされる可能性もあります。
② 遺言書がある場合
遺言書を作成し、後継者を明確に指定することで、事業の継続がスムーズになります。事業用資産と個人資産を分けて相続することで、相続人間でのトラブルを防げます。
例えば、以下のように遺言書を作成することができます
- 後継者(例:長男)に、事業用資産(店舗、設備、営業権など)を相続させ、事業を継続
- 次男や配偶者には、個人資産(自宅、預貯金など)を相続させ、事業には関与しない
- 長男が事業用資産を相続し、次男には代償金を支払う方法で、事業を継続しつつ、相続人に公平な配分を行うことも可能
③法人の場合の注意点
法人(株式会社)の場合、事業用資産は法人名義であるため相続財産には含まれませんが、株式は相続財産として扱われ、相続した株式により経営権が変わります。
例えば、相続人が配偶者と子ども2人(長男・次男)の場合、株式は以下のように分割されます:
- 配偶者:株式の1/2
- 長男:株式の1/4
- 次男:株式の1/4
株式の過半数を持つ者が経営権を握るため、株式の分配方法が重要です。
遺言書で、経営権を引き継ぐ人物を指定することができます。例えば、長男に株式を全て相続させることで、事業の経営権を一元化し、事業の継続を確保できます。
④ 遺言書の作成ポイント
事業の継続を望む人物を後継者として指定し、相続人とのトラブルを防ぎます。
事業用資産は事業承継者に、個人資産は他の相続人に割り振ります。
法人の株式を誰が相続するかを明確にすることで、経営権の移行をスムーズにします。
事業承継者に事業用資産を譲り、他の相続人には現金や不動産で補償を行う方法を検討します。
事業の方向性や今後の経営方針を遺言書に記載することも有効です。(付言に記載)
 規模の大きな企業であれば顧問契約を締結している弁護士や税理士が助言してくれるでしょう。しかし、小規模な会社や個人事業主であれば、日常の事業が忙しく相続対策が後回しになりがちです。
規模の大きな企業であれば顧問契約を締結している弁護士や税理士が助言してくれるでしょう。しかし、小規模な会社や個人事業主であれば、日常の事業が忙しく相続対策が後回しになりがちです。
そこで、自分の死後の事業に支障が出ないよう事業の承継者を指定し、事業用の財産を相続させる遺言書作成をお勧め致します。
9.面倒を見てくれる子に財産を残したい方
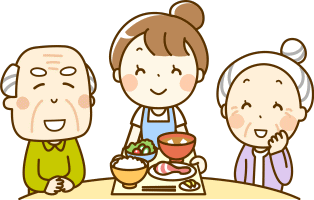
遺言書がない場合、財産は法定相続分に従って分割されます。この場合、子どもが複数人いる場合には、面倒を見てくれる子だけに全ての財産が残るわけではなく、法定相続分に基づいて平等に分配されます。
① 遺言書ない場合
例:子どもが2人の場合
- 子1(面倒を見てくれた子):1/2の財産
- 子2(他の子):1/2の財産
このように、面倒を見てくれた子に対して十分な配慮がされない可能性があり、また、相続人間で争いが起きることもあります。特に、面倒を見ていた子が生活費や医療費を負担していた場合、他の相続人との不公平感が生じることがあります。
② 遺言書がある場合
遺言書を作成することで、面倒を見てくれた子に対して特別に財産を残すことができます。遺言書であらかじめ指定しておけば、他の相続人との争いを避け、意図した通りに財産を渡すことができます。(遺留分は考慮する必要があります。)
- 子1(面倒を見てくれた子):3/4の財産
- 子2(他の子):1/4の財産
遺言書を作成することにより、このような分配も可能になります。例えば自宅と預貯金1/2を面倒見てくれた子に相続させ、預貯金の1/2を他の子に相続させることも可能です。
なお、遺留分は法定相続の1/2になりますので、子が2人の場合=1/2✕1/2=1/4が1人の子の遺留分になります。3人の場合は1/3✕1/2=1/6となります。
 例えば3人の子供がいて、長女が老後の面倒を見てくれるのであれば、長女に全財産を取得させる遺言が可能です。しかし、遺言をする場合には遺留分との関係に気をつける必要があり、この場合、他の2人から遺留分取戻しの請求がされる可能性があります。
例えば3人の子供がいて、長女が老後の面倒を見てくれるのであれば、長女に全財産を取得させる遺言が可能です。しかし、遺言をする場合には遺留分との関係に気をつける必要があり、この場合、他の2人から遺留分取戻しの請求がされる可能性があります。
状況により、最初から遺留分を考慮し、各相続人に遺留分相当の遺産を取得させ、その上で面倒を見てくれる子に多くの遺産を取得させる内容の遺言をする方が、死後の争いを避ける為にお勧めです。
10.遺言書残した方が良い方 まとめ

通常、遺言書がない場合、法定相続分で分配されるケースが多くなります。しかし、それぞれの事情により、法定相続分では納得出来ないため争いに発展する場合があります。しかし、相続財産は、本来、故人の財産であり、その分配方法も故人が決めることが出来ます。
その方法として有効なものが遺言書になるわけです。従って、ご自身のお気持ちで、誰にどの財産をを幾ら残したいのか、遺言書に記載しておくことで、不要な争いを避けることが可能になります。
遺言書を作成する場合、遺言の内容に従って、手続きを進める遺言執行者も記載することが一般的です。遺言により分配方法も決まり、遺言執行者も記載されていれば、後は、淡々と手続きを進めることになり、遺産分割協議も不要です。
また、特にお子さんんがいない場合や相続人がいない場合など、遺言書を残しておく方が、不要な争いなどを防ぐことになります。
当事務所でも、遺言書の作成サポートを行っておりますので、不明点がありましたらお気軽にご相談下さい。
»» 次の記事:遺言書の種類を解説!それぞれの特徴と選び方 »»
«« 前の記事:遺言書に書いて有効なものは? ««
大塚法務行政書士事務所 大塚博幸

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)