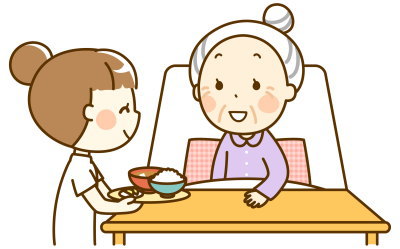・相続に関する制度には、「相続放棄」「相続排除」「相続欠格」など、重要な概念があります。これらは、それぞれ異なる目的や状況に応じて使われる制度です。
本記事では、これらの違いや手続き方法、必要書類、適用される条件などについて詳しく解説します。また、実際にどのようなケースでこれらの制度に該当するのかも紹介します。
相続が発生した場合の基礎知識として、参考にご覧下さい。
1.相続放棄とは?
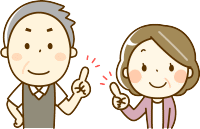
相続放棄とは、被相続人が所有していた全ての財産(プラス・マイナス財産の全部)を放棄することをいいます。相続放棄を選択することで、相続人は財産を一切受け継がないことになります。この制度は、財産の中に負債が多い場合や、相続人間でトラブルが予想される場合に特に有効です。
・相続放棄を選択する主なケース
相続財産に多くの借金や負債が含まれている場合、これらを引き継ぐことで経済的に大きな不利益を被る可能性があります。財産調査を慎重に行い、プラスの財産よりマナイスの財産が多いことが確定した場合は、相続放棄をすることで、負債を引き継がずに済むため、自己の財産を守ることができます。
相続人同士の意見が合わず、遺産分割を巡って争いが起こりそうな場合、相続放棄をする方もおります。遺産分割が難航し、家族間での関係が悪化するリスクを避けるために、相続放棄を選択することは珍しくありません。この場合、相続放棄をすることで争いに巻き込まれず、精神的な負担を減らすことができます。
被相続人がどのような借金を抱えているのか、またはどこに負債があるのかが不明な場合、相続放棄を選ぶことで思わぬ負債を引き継がずに済みます。被相続人の財産状況を十分に把握できない場合に、後から予期しない負債が発覚するリスクを避けるために相続放棄をすることも一つの方法です。
資産的価値があまりない不動産を相続した場合、維持費や税金が発生し経済的に負担になる。また、遠方にある不動産や売却が難しい不動産など、維持管理の手間が大きいなど、主たる相続財産が不動産のみで資産的価値よりも維持管理が負担になる場合は、相続放棄も検討してみましょう。
・相続放棄の効果と注意点
相続放棄を選ぶと、その後は、プラス、マイナスの財産を受け取ることがなくなります。つまり、相続放棄をした者は、最初から相続人ではなかったことと見なされ、他の相続人にその権利が移ります。
相続放棄は、家庭裁判所に対して正式に申述する必要があり、その手続きには注意が必要です。なお、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければならないため、放棄の意思が固まった段階で速やかに手続きを行うことが求められます。
2.相続放棄の手続き
相続放棄は、「相続開始を知った日」から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することで行います。この期間を過ぎると、相続放棄はできなくなるため注意が必要です。
民法(参考)
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
相続放棄は、強制・脅迫によるものでなければ、原則、認められます。但し、相続人が相続財産を隠す・使用した場合などは、3ヶ月以内であっても相続放棄することが出来なくなります。又、一旦放棄すると3ヶ月以内であっても撤回・取消しは出来ませんので注意が必要です。
・申述に必要な書類

相続放棄の申述には、戸籍(除籍・改正原戸籍)等、被相続人(故人)と申述人(相続放棄する方)の続柄により添付する書類が異なります。下記を参考にご覧ください。
① 相続放棄の申述書(家庭裁判所 所定の様式)
② 被相続人の住民票除票(戸籍附票)
③ 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
④ その他、申述人の関係に応じた書類
- 被相続人の死亡記載のある戸籍
- 被相続人の死亡記載のある戸籍
- 代襲相続人の場合、被代襲者の死亡記載のある戸籍
- 被相続人の出生~死亡までの戸籍
- 被相続人の子が亡くなっている場合、その子の出生~死亡までの戸籍
- 直系尊属が亡くなっている場合、その直系尊属の死亡記載のある戸籍
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 被相続人の子が亡くなっている場合、その子の出生~死亡までの戸籍
- 被相続人の直系尊属の死亡記載のある戸籍
※おい・めい(代襲相続人)の場合は、本来の相続人(被代襲者)の死亡記載のある戸籍
上記の書類を準備して家庭裁判所に申述を行います。問題なく受理された場合には、家庭裁判所より「相続放棄申述受理通知書」が発行されます。又、相続放棄を証明する書類として「相続放棄申述受理証明書」があります。こちらは、相続放棄が受理された後に、家庭裁判所に交付申請し取得します。
3.相続放棄後の次の相続人
被相続人の配偶者・子(第1順位)の全員が相続放棄した場合、最初から相続人でなかったことになり、次の順位の父母(祖父母)が相続人の地位を取得することになります。
民法(参考)
第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
(1)子供全員が相続放棄した場合
・妻に全て相続させようと子供全員が相続放棄しても、その権利は被相続人の父母に移ることになります。
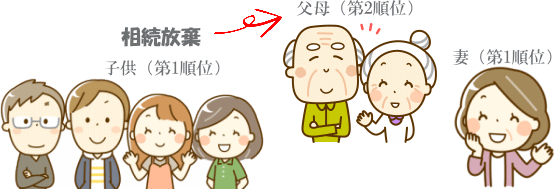
相続財産が1千万円とした場合・・
- 本来の法定相続分による分配 = 妻 500万円(1/2)+ 子供全員 500万円(1/2)= 1,000万円
- 子供全員が放棄した場合 =妻 666万円(2/3)+ 父母 333万円(1/3)=1,000万円
となります。子供全員が相続放棄したことにより、相続権が妻(第1順位)と父母(第2順位)に移ったため、妻の相続分も変動することになります。
(2)子供のみ相続人の場合
・子供のみ相続人の場合、長男1人が相続放棄しても、長男の子は代襲相続出来ません。

相続財産が1千万円とした場合・・
- 本来の法定相続分による分配 = 1,000万円 ✕ 1/4(子供の人数)= 250万円(子供1人あたり)
- 子供1人が相続放棄した場合 = 1,000万円 ✕ 1/3(子供の人数)= 333万円(子供1人あたり)
相続人が子供のみ場合、そのうちの1人が相続放棄すると、他の子供が相続分が増加することになります。
(3)相続放棄と次の相続人 まとめ
相続の順位は、下記の様になります。相続放棄した場合、下記の順位で相続分が変動する場合があります。
【相続順位表】
| 故人(被相続人) | 第1順位の相続人 | 第2順位の相続人 | 第3順位の相続人 |
|---|---|---|---|
| 父・母 | 配偶者・子 | 配偶者・祖父母 | 配偶者・兄弟 |
| 夫・妻 | 配偶者・子 | 配偶者・父母 | 配偶者・兄弟 |
| 子(未婚の場合) | ― | 子の父・母(祖父母) | 子の兄弟 |
配偶者が先に亡くなっている場合は、配偶者の除いて、そのままの順位になります。例えば、故人が夫(妻)の場合、相続順位は、①子、②父母、③兄弟になります。なお、子供、兄弟が複数人いる場合、両親が2人いる場合に、そのうち1人が放棄しても、他の相続人の相続分が増えることになり、順位は変動しません。
- 配偶者+子(2人)で配偶者が相続放棄した場合=子が全ての相続財産を取得します。
- 配偶者+子(2人)のうち、子の1人が相続放棄した場合、配偶者ともう一人の子で相続財産を取得します。
- 配偶者と子(2人)のうち、子2人が相続放棄した場合、配偶者と父母で相続財産を取得します。父母が既に亡くなっている場合は、配偶者と兄弟で相続財産を取得します。
遺産分割協議の際に、相続放棄をされている方がいる場合、どのような順位で、誰が相続人になるのか、法定相続分はどうなるのか、良く確認した上で、遺産分割協議を行う必要があります。相続人が欠けていた場合、遺産分割協議が無効になりますので、ご注意ください。
4.相続放棄後の財産管理義務
法律により、相続放棄をした者であっても、放棄の時点で相続財産を占有している場合には、次の相続人や財産清算人に引き渡すまでの間、自己の財産と同じように注意して保存する義務があります。これは特に不動産や貴重品などを管理している場合に注意が必要です。
民法(参考)
第940条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
例えば・・相続放棄者が手元で保管しているものや被相続人と同居しいてる家など、その占有物に対し
- ① 他の相続人、又は ② 放棄したことにより、次の相続人になった者
- ③ 財産清算人(相続放棄者以外に相続人がいない場合、家庭裁判所に申立てを行い清算人が選任されます。)
に引き渡すまでの間、自己の財産と同じように注意して保存する義務があるということになります。
財産の保存義務とは
相続人には、現に占有している相続財産を適切に管理・保存する義務が課せられています。この義務は、相続放棄をした場合でも適用されるため、注意が必要です。
相続財産を故意に失ったり、損傷させたりする行為をしてはいけない義務があります。たとえば、不動産を管理する際に意図的に価値を下げるような行為や、財産を破壊するような行動。
相続財産を適切に保存・管理するため、建物の修繕、貴重品の保管など、財産の維持に必要な手続きや管理を行うこと。
現段階では、相続人が負うべき財産の保存義務がどこまで厳密に適用されるのかについて、法的な見解が完全には確立されていない部分もあります。具体的には、財産を滅失させる行為をしてはならないこと(①)のみが義務とされる場合と、さらに財産を維持するために必要な行為(②)も義務として含まれる場合があるかどうかが不明確な状況です。
5.相続廃除とは?
相続廃除とは、特定の相続人に財産を相続させたくない場合に、家庭裁判所に請求することでその相続権を失わせる制度です。法律により、以下のような行為があった場合に適用されます。
民法(参考)
第892条 遺留分※)を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
上記により、被相続人に対して① 被相続人に対する虐待、②被相続人への重大な侮辱、③著しい非行があった場合、このいずれかがあった場合、被相続人は、推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することできることになります。
上記法律では「遺留分を有する推定相続人」が行った行為に対して定められています。遺留分とは、相続人が相続財産を最低限度もらえる権利と言えます。配偶者・子供・両親(直系尊属)が遺留分の権利を有し、兄弟姉妹にはありません。
つまり、遺言書で全ての財産を他者に相続させる、または遺贈した場合も遺留分があるため、排除したい相続人も財産を受取ることが可能になってしまうため、このような法律が定めれた考えられます。これとは逆に、遺留分を有しない兄弟姉妹に財産を渡したくない場合は、遺言書を作成し、他者に相続させることで、兄弟姉妹は相続財産を受取ることが出来なくなります。
6.相続廃除の手続
相続排除の手続きは、生前に被相続人が申立てる方法と遺言書に基づき遺言執行者が申立てる方法があります。
(1)生前に相続排除を申立てる手続
被相続人が生存中に、家庭裁判所へ申し立てを行い、特定の推定相続人の相続権を排除する方法です。裁判所の審査を経て、正式に排除が認められると、その相続人は財産を相続できなくなります。
被相続人の住所地を管轄する裁判所に相続人廃除の申立てを行います。なお申立てには下記の書類が必要になります。
- 相続廃除の申立書
- 申立人の戸籍謄本
- 廃除を求める推定相続人の戸籍謄本
要件を満たしていると判断された場合には、廃除の審判が下されます。廃除の確定後、審判書の謄本と確定証明書が交付されます。
審判確定の日から10日以内に廃除される推定相続人の本籍地、または届出人(申立人)の所在地の市区町村役場に届出を行います。
(2)遺言による相続人廃除の手続き
被相続人が生前に家庭裁判所に申立てを行わなかった場合でも、遺言によって相続人の廃除を求めることができます。
被相続人が公正証書遺言などで、特定の相続人の廃除を希望する旨を記載します。
《 相続人廃除の文例 》
第〇条 遺言者の長男〇〇 〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)は、平成〇年頃より継続して遺言者に対し暴言・脅迫を行い、生活を脅かす言動を続け、令和〇年〇月〇日には、遺言者に対して身体的暴力を加え、怪我を負わせた。これらの遺言者に対する重大な侮辱および虐待を行った、長男〇〇 〇〇を遺言者の推定相続人から廃除する。
第〇条 本遺言の執行者として、〇〇 〇〇(住所:〇〇 〇〇、職業:〇〇〇)を指定する。
単なる不仲では認められないため、具体的な非行の内容を明記 することが重要です。証拠がある場合(警察の報告書、診断書など)、それについても記載しておきましょう。また、遺言執行者を指定する際には、廃除の手続きを進めるため、信頼できる人物(弁護士など)を指定しておきましょう。なお、自筆証書遺言よりも 公正証書遺言での作成をお勧めします。
被相続人が亡くなった後、遺言執行者(遺言書で指定された人)が家庭裁判所へ廃除の申立てを行います。申立ての流れは、生前申立ての場合とほぼ同様です。
裁判所が審理し適切と判断された場合、廃除の審判が下されます。廃除の確定後、審判書の謄本と確定証明書が交付されます。
生前申立てと同様に、審判確定後10日以内に市区町村役場へ廃除の届出を行います。
(3)相続人廃除の効果と注意点
相続人の廃除が確定すると、その相続人は遺産を相続する権利を失います。これは、単なる遺産の取り分を減らす「遺留分の削減」ではなく、法律上の相続権そのものを剥奪するものです。
しかし、廃除された相続人の子(代襲相続人)は、民法の規定に従って代襲相続をすることが可能です。つまり、廃除された相続人の子どもがいれば、その子どもが本来の相続人の地位を引き継ぎ、相続権を有することになります。
- 廃除の対象:父A が長男Bを廃除した場合、BはAの遺産を相続できなくなる。
- 代襲相続の発生:Bに子Cがいる場合、Cは代襲相続人としてAの遺産を相続する権利を持つ。
- 子どもがいない場合:Bに子Cがいない場合、Bの相続権は消滅し、他の相続人に遺産が分配される。
このように、相続人本人は廃除されても、その子どもには影響が及ばないため、廃除を検討する際は、代襲相続の可能性も考慮する必要があります。
一度廃除が確定した相続人であっても、被相続人の許しを得ることで「復権」することが可能です。復権とは、廃除された相続人の相続権を回復する手続きであり、次のような流れで行われます。
- 被相続人の許し:被相続人が、かつて廃除した相続人を許し、相続権を回復させたいという意思を持つことが前提です。
- 家庭裁判所への申立て:被相続人は、家庭裁判所に復権申立てを行います。
- 復権の確定:裁判所の許可が下りると、廃除の効力が取り消され、相続人としての権利が復活します。
復権は被相続人の意思によるものであり、相続人が「復権したい」と単独で申し立てても認められません。なお、被相続人が生前に復権を申し立てるほか、遺言書に記載する方法もあります。
7.相続欠格とは?
相続欠格とは、一定の重大な違法行為を行ったことにより、自動的に相続権を失う制度です。民法第891条により、以下の行為をした者は、相続欠格者となります。
民法(参考)
第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために刑に処せられた者。
2 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
3 詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取消し、又は変更することを妨げた者。
4 又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取消させ、又は変更させた者。
5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。
と定められています。③~⑤では遺言書に関することになりますが、基本的には、被相続人の意思に反して、遺言書を書かせたり、取消しさせたり、相続発生後、発見された遺言書が自分に不利な内容の為、破棄した場合等は相続人になれず、財産も受取れないことになります。
相続欠格に該当した場合、その相続人は法律上当然に相続権を失います。なお、相続欠格になった人の子ども(代襲相続人)は、通常どおり相続権を持ちます。また、相続欠格は、相続廃除とは異なり、家庭裁判所の判断を待つ必要はなく、欠格事由があった時点で相続権が消滅することになります。
8.相続放棄・相続排除・相続欠格 まとめ

相続放棄・相続排除・相続欠格は、それぞれ異なる目的や手続きが必要な制度です。特に相続放棄は、負債を引き継がないための手段として選ばれることが多いですが、相続排除や相続欠格は特定の事情がある場合になります。
相続手続は、複雑で面があります。もし、どの様に進めれば良いかわからない場合などは、早めに専門家に相談されることをお勧めします。
当事務所は、葛飾区で平成21年開業の行政書士事務所になります。遺言書作成、相続手続きのご相談、手続代行のなどのサポートを行わせて頂いております。これまでに、公正証書遺言作成のサポートから相続手続一式代行など、多くのご依頼を頂いており経験豊富な事務所でもあります。遺言書作成や相続手続でご不明点などありましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。
»» 次の記事:離婚・再婚した場合の相続人は?内縁の妻の相続は? »»
«« 前の記事:相続財産とは?含まれるのもの・含まれないもの ««
大塚法務行政書士事務所 大塚博幸

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)