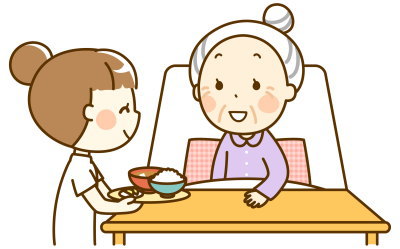・相続人に認知症の方や未成年者の方が含まれている場合、通常の相続手続きとは異なる対応が必要となります。
特に、相続人に意思表示能力が欠けている場合や、法定代理人が必要な未成年者がいる場合、手続きは複雑になります。
本記事では、認知症の方や未成年者が相続人の場合に、どのような対応が求められるのかについて詳しく解説します。
1.相続人に認知症の方がいる場合の対応
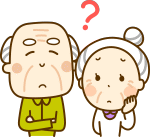
相続人に認知症の方が含まれている場合、通常の相続手続きとは異なる対応が必要になります。認知症の進行度合いやその方の意思能力の有無によって、手続きは複雑になります。特に、認知症の方が意思表示能力を欠いている場合、法的な手続きを行うためには特別な配慮が求められます。
(1)認知症の方が相続人に含まれている場合の問題点
民法第3条2項では、「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったとき、その法的行為は無効とする。」と定めています。これにより、認知症の相続人が遺産分割協議に参加しても、意思能力が欠けていると判断された場合、その協議内容が無効になる可能性があります。認知症の進行に伴い、意思能力がなくなることが多いため、協議には慎重な判断が必要です。
現時点では、認知症の方が意思能力を欠いているかどうかに関する明確な基準は設けられていませんが、例えば、認知症による要介護認定を受けている場合などは、意思能力を有しないと判断される可能性が高いと思われますが、最終的には、医師等の専門家に相談する必要があります。
(2)成年後見人の必要性

遺産分割協議は法律行為に該当します。相続人の1人が認知症により意思能力を有しなかったときは、その方の代理人として成年後見人が必要になります。成年後見人は、家庭裁判所の審判によって選任され、法的手続きの代理を行います。
この手続きを司法書士に依頼した場合、一定の費用(10万円~20万円程度)がかかるため、相続人はこの点も考慮しなければなりません。
成年後見人は、認知症の方の財産を守る立場に立ち、その方の利益を最優先に考えた対応を行います。選任されると、成年後見人はその認知症の方が亡くなるまで後見を続けることになります。報酬として、月額2万円程度、財産額により3万円~6万円の報酬が必要になる場合があります。
認知証の方の親族を成年後見人に推薦することも可能ですが、最終的には、家庭裁判所の判断になりますので、必ずしも選任されるわけではありません。もし、親族の方が後見人に選任された場合、報酬が節約できますが、状況に応じて後見監督人が選任されます。(月額1万円~3万円程度の報酬が必要。管理財産額による。)
成年後見制度は、認知症などにより判断能力が不十分な方の権利を守り、適切に財産管理や契約締結を行うための法的な制度です。成年後見人を選任するためには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。この申し立ては、配偶者や親族などが行うことになります。
・成年後見の流れ
・家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てを行います。この際、申し立てに必要な書類(本人の診断書や家族関係書類など)を提出します。
・家庭裁判所は、認知症の程度や本人の状態を確認し、成年後見人が必要かどうかを審査します。
・後見人が必要と判断された場合、裁判所が成年後見人を選任します。後見人には、通常、弁護士や社会福祉士などの専門家が選ばれます。
・成年後見人が選任されると、後見人が認知症の方の財産などの管理を開始します。遺産分割協議にも後見人として参加することになります。
(3)遺産分割協議を行う際の注意点
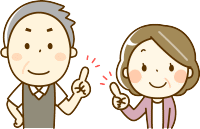
遺産分割協議において、重度の認知症の方が相続人に含まれている場合、成年後見人が代理人となるため、通常の相続人同士の協議が行われるわけではありません。成年後見人は、認知症の方の利益を確保するため、法定相続分を守ることが求められます。したがって、他の相続人の希望通りに遺産分割が行われることにはなりません。
また、親族が成年後見人に選任されることもありますが、その場合、親族が相続人であると認証の方と利益相反になります。このため、特別代理人が必要になります。特別代理人は、認知症の相続人に代わってその権利を行使する役割を担います。
法定後見人が選任された後、遺産分割協議を行う際には、後見人は被後見人の財産を守る立場にあります。このため、通常は法定相続分に基づいた遺産分割が行われることになります。そのため、他の相続人が意図する遺産分割とは異なる場合があり、調整が難しくなることがあります。
特に、重度の認知症の方が相続人に含まれている場合、その方が遺産分割協議に参加できないため、後見人を立てて遺産分割を行う必要があります。この場合、後見人なしで遺産分割を行うと、その協議内容が無効になる可能性があるため、十分に注意が必要です。
また、後見は被後見人が亡くなるまで続くため、後見人が専門家(弁護士や司法書士など)に選任された場合、後見人に対する報酬の支払いも続くことになります。この点を考慮し、相続人同士でよく話し合い、どのように相続手続きを進めるべきかを検討することが重要です。
(4)遺産分割協議を行わない方法も

相続人に認知症の方がいる場合に遺産分割協議を行うには、成年後見人が必要になりますが、それには時間と費用が必要になります。そこで遺産分割協議を行わなくても相続手続きが可能な方法を解説いたします。
・将来的なことは予測不可能ですが、被相続人(故人)が遺言書を残しておけば、遺産分割協議は不要となります。遺言書には、相続させる人や分配方法など明記され、その内容が最優先されるため、相続人全員が協議をする必要がなくなります。推定相続人の方が、ご高齢になり不安がある方は、ご自身が健康なうちに遺言書を作成しておくことも有効な対策になります。
・遺言書がない場合でも、法定相続分に基づいて相続を行う方法もあります。法定相続分とは、民法に定められた相続の基本的な割合です。この方法では、相続人全員が法定相続分に従って財産を分けることになります。そのため、遺産分割協議書を作成する必要がなく、協議を行うことなく相続手続きを進めることも可能です。
ただし、不動産が相続財産に含まれる場合、共同所有となるため後々の管理や売却が難しくなることがあります。そのため、共同所有する前に、後の取り決めや運用について十分に話し合うことが重要です。
2.認知症に備える生前対策

認知症になる前に行うべき生前対策の一つに、遺言書の作成や任意後見契約、家族信託の活用があります。これらの制度は、認知症の進行に備え、財産の管理や相続においてトラブルを未然に防ぐために非常に有効です。それぞれの制度の特性を理解し、どのように活用できるかを知ることが大切です。
(1)遺言書の重要性と種類
遺言書は、相続が発生したときに自分の意志を明確に伝えるために有効です。認知症が進行する前に遺言書を作成しておくことで、後の相続問題をスムーズに進めることができます。認知症が進行して意識が不確かになった場合、遺言書があることで、家族や相続人間での争いを避けることが可能です。
・遺言書には大きく分けて三種類あります。
自筆証書遺言は、最も手軽に作成できる遺言書の形式です。自分で手書きで書き、封印して保管します。公証人の関与が不要ですが、法的効力を確保するためには要件を満たす必要があります。また自宅保管の場合は、相続発生後に裁判所による検認が必用になります。
公正証書遺言は、公証人に作成してもらう遺言書です。この遺言書は、公証人が作成するため無効になるリスクが低く安心度が最も高い遺言書と言えます。ただし、公証人の費用等が発生します。
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に証明してもらう形式です。内容を秘密にしておくことができる反面、自筆証書遺言よりも複雑で費用もかかるため、秘密証書遺言を選択される方は少ないといえます。
遺言書の作成は、早期に行うことが重要です。将来誰でも認証になるリスクがあります。元気なうちに自分の意志を形にしておくことで、家族に対する配慮もできます。
(2)任意後見制度の活用
任意後見は、認知症になった際に自分の財産管理や生活支援を信頼できる人物に任せるための制度です。任意後見制度は、法定後見制度とは異なり、認知症の前に自分が後見人を選べるという特徴があります。この制度は、認知症が進行した際に、後見人が法律的な代理権を持って財産を管理し、必要な支援を行うことができるようにするものです。
任意後見契約を結ぶことで、自分の意思が尊重され、家族の負担が軽減されます。後見人としては、家族以外にも専門家(弁護士や司法書士)を選ぶことができます。
(3)家族信託を利用した財産管理
家族信託は、比較的新しい制度で財産を家族に託して管理を任せる制度です。この制度は、認知症対策としても注目されています。信託契約を結ぶことで、信託財産の管理が任意の受託者に任され、受益者が利益を受けることができます。
信託の内容は、契約時に決めた条件に基づいて運用されます。認知症が進行し、本人が財産を管理できなくなった場合でも、受託者が適切に財産を管理し運用することができます。これにより、財産管理が適切に行われ、本人の意志を尊重した管理が可能となります。
家族信託の特徴は柔軟性が高い点です。信託契約の内容は個別に設定できるため、細かな希望に対応できるのが魅力です。たとえば、特定の資産を特定の家族に渡したい、または特定の使い道を指定したい場合にも対応可能です。
認知症対策として、遺言書、任意後見、家族信託はそれぞれ重要な役割を果たします。これらの制度を適切に理解し、活用することで、認知症による不安を軽減し、財産管理や相続がスムーズに進むことができます。早期に対策を講じて、家族や相続人に負担をかけず、安心した生活を送るための準備をしましょう。
3.相続人に未成年者の方がいる場合の対応

相続手続きにおいて未成年者が関わる場合、特別な対応が求められます。未成年者は法律行為を単独で行うことができないため、親権者や特別代理人がその代理を務めることになります。このような状況下では、相続における遺産分割協議を進める際に、どのように対応すれば良いかをしっかりと理解しておくことが重要です。
(1)民法における未成年者の法律行為の規定
民法第5条では、以下のように規定されています
①未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
②前項の規定に反する法律行為は、取消すことができる。
上記のことから、未成年者の相続に関する法律行為には、法定代理人の同意が必要であることがわかります。
(2)親権者と未成年者の利益相反について
通常の場合、親権者(親)が代理することになりますが、相続人が親権者(親)と子(未成年者)の場合、親権者は未成年者の代理人となることが出来ません。これは、親権者が自分に有利な形で遺産分割が進んでしまう可能性があるからです。
つまり、親権者と未成年者の利益が相反する行為(利益相反行為)については、親は代理人になれず、特別代理人が必要になります。
利益相反とは?
一人の人が「どちらの利益を優先するか」で迷ってしまう状況のことです。例えば、親が子どもの代理として遺産の分け方を決めるとき、親自身の取り分を多くしたい気持ちと、子どもの利益を守るべき立場がぶつかってしまいます。このように自分の利益と代理人として利益が反することを利益相反といいます。
(3)特別代理人が必要な理由
遺産分割協議も法律行為に該当しますので、相続人が親(夫又は妻)と子(未成年者)の場合、「親」と「子の特別代理人」との遺産分割協議になります。なお、民法改正により、18歳以上であれば、遺産分割協議に参加できることになりました。(18歳未満の方がいる場合は、これまで同様に特別代理人が必要になります。)
・特別代理人は、子の住所地を管轄する家庭裁判所に、親権者又は利害関係人(親族等)による申立てによって行います。
- 申立書(家庭裁所定の様式)
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 特別代理人候補者の住民票又は戸籍の附票
- 利益相反に関する資料(遺産分割協議書案・契約書案等)
- 利害関係人による申立ての場合は、利害関係を証する資料(戸籍謄本等)
上記書類を一式揃え家庭裁判所に申立てを行います。特別代理人に選任された方は、審判で定められた行為について未成年者を代理することになり、その行為が終了した時に、特別代理人としての任務も終了します。
※成年後見人の場合、遺産分割協議が完了しても、認知症の方等が亡くなるまで後見人が付きますが、未成年者の特別代理人の場合は、遺産分割協議等の完了等により任務が終了となります。
(4)特別代理人を立てずに相続手続きを行うには?

・遺産分割協議を行う場合、未成年者は協議に参加出来ませんので親権者が代理人になります。親権者と未成年者が利益相反になる場合は、特別代理人が必要になりますが、法定相続分による分配では、遺産分割協議書が不要になりますので、協議を行わなくても相続手続きが可能です。
被相続人が不動産を所有していた場合は、法定相続分による共同所有となります。
子供が成人してから遺産分割を行う方法もありますが、成人してから遺産分割を行えば良いと分配も行わずに放置していると、もし、遺産分割協議を行う前に、相続人の1人が先に亡くなってしまった場合、相続手続きが複雑になる可能性があります。
又、不動産の相続登記についても、令和6年4月より3年以内の登記が義務化されます。(※正当な理由がなく3年以内に相続登記を行わない場合は、10万円以下の過料が科される場合があります。)その他、分配の有無に関わらず相続税申告は、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。
(5)どの様に相続手続きを進めるのが良いか?
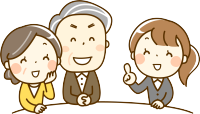
・ここでは、相続手続きに未成年者がいる場合、①特別代理人の選任、②法定相続分による分配、③未成年者の成人後に遺産分割協議等について整理していきたいと思います。
・特別代理人を立て、遺産分割協議を行えば、相続財産に関する権利も早めに確定し安心度が高いと言えます。但し、家庭裁判所に対する申立てが必要になり、時間と労力が必要になります。又、申立てを司法書士等に依頼した場合は、その費用も必要になります。
その他、特別代理人は未成年者の財産を守る必要がありますので、特定の相続人のだけが有利になる遺産分割協議は出来ません。
・遺産分割協議を行わずに法定相続分による分配では、被相続人が所有していた不動産も共同所有になりますが、不動産は原則、単独所有が望ましいとされています。
例えば、長男(50%)・次男(50%)の2人が共同所有の場合に、長男が亡くなると、長男の妻(25%)・子(25%)が相続人になります。法定相続分で所有していくと時間の経過とともに共同所有者が増えていき、結局、意見がまとまらずに不動産が売却できない可能があるからです。
その他、固定資産税についても共有して支払う義務があり、その支払いも複雑になる可能性があります。
不動産を早めに売却する予定のある方や預貯金等を含め早めに分割して整理しておきたい方等は、こちらの方法も良いかと思います。但し、法律で定められている割合に限られます。
・相続登記については、令和6年4月より3年以内の登記が義務化されますが、同時に「相続人申告登記」制度も設けられ、この申出を行うことにより義務を果たしたことになります。(法定相続分の割合の確定不要。)この制度を利用することにより、不動産の相続登記を一旦保留しておくことも可能です。
ただし、上記で述べました様に、遺産分割前に相続人の1人が亡くなってしまった場合、相続手続きが複雑になる可能性や長時間放置したことにより、当時の財産状況の把握が困難になる可能性もあります。主な財産が不動産のみであり売却する予定もない方は、こちらも1つの方法かと思います。
※相続税申告及び生命保険等の手続きがある場合は、先に行う必要がありますので注意してください。
4.認知症の方・未成年者の相続手続きまとめ

・後見人・特別代理人の申立てを行うことは、労力や費用が掛かることになるので、出来れば自分たち相続手続きを行いたいと思われる方が多いのではないでしょうか?
基本的には、法定相続分による分割が原則で遺産分割協議は、法定相続分を変えて相続する方法になりますので、法定相続分で良い方は、遺産分割協議を行わないことも可能です。(法定相続分で分配を行い、その後。遺産分割協議することも可能。)
もし、法定相続分を変えて相続する必要がある方は、法律で定める方法によって遺産分割協議を行う必要があります。※権限のない方は代理人になれませんので、協議自体が無効になります。
どの様な方法が良いかは?相続人の方の状況により異なりますので、もし、不明な事があれば早目に専門家に相談し、そのアドバイスを元に、もう一度考えられた方が良いかと思います。
当事務所は、葛飾区で平成21年度開業の行政書士事務所にです。これまでに遺言書作成や相続に関するご相談・ご依頼を頂いております。もし遺言書や相続問題で不明点がありましたら、当事務所までご相談下さい。経験豊富な事務所ですので安心してお問合せ下さい。ご相談だけでも大丈夫です。
»» 次の記事:寄与分・特別の寄与とは何か? »»
«« 前の記事:離婚・再婚した場合の相続人は?内縁の妻の相続は? ««
大塚法務行政書士事務所 大塚博幸

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)