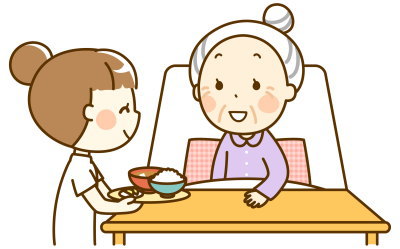ご家族が亡くなった場合に必要な手続きは、非常に多岐にわたります。役所への届出、生命保険・葬祭費等の受取手続、廃止・継続手続き、相続・税務の手続きから銀行の口座解約・準確定申告等の手続き等、様々な手続が必要になります。
申請しないと給付・還付されないものもありますので、最初に確認して頂ければと思います。
1.役所への届出・申請等

身近な家族が亡くなった際には、役所への各種届出や申請が必要となります。死亡届をはじめ、世帯主の変更、健康保険や年金に関する手続きなど、期限が定められているものも多いため、早めに対応することが大切です。
手続きを円滑に進めるために、必要な書類を確認し、該当する窓口で申請を行いましょう。
① 死亡届
・死亡届は、故人が亡くなった事実を市区町村に報告する手続きです。この届け出をすることで、故人の住民票が抹消され、除票(死亡したことを証明する住民票)が発行されます。また、故人の戸籍にも死亡の記録が追加されます。死亡届は、死亡後7日以内に提出しなければなりません。
➡〔 提出先 〕故人の死亡地、本籍地、または届出人の住所地の市区町村役場
② 世帯主変更届
・故人が世帯主だった場合、その世帯に15歳以上の方が2人以上残っている場合は、次の世帯主を設定するために「世帯主変更届」を提出する必要があります(故人が亡くなった日から14日以内)。
故人が1人世帯だった場合や、2人世帯で残った方が1人しかいない場合は、自動的に新しい世帯主が決まるため、手続きを行う必要はありません。
➡〔 提出先 〕住所地の市区町村役場
③ 児童扶養手当認定申請
・児童扶養手当は、ひとり親家庭を支援するために支給される手当です。例えば、父親が死亡した場合、母親が児童を養育するための支援を目的としています。なお、支給額は、申請者の前年(または前々年)の所得に基づいて決定され、所得制限を超えると手当が支給されなくなります。
➡〔 提出先 〕住所地の市区町村役場
④ 復氏届
・復氏届は、結婚によって姓を変更した後、配偶者が亡くなった場合に元の姓に戻す手続きです。配偶者が死亡した場合、そのまま姓を変更せずに生活を続けることもできますが、元の姓に戻す場合は、管轄の役所で手続きを行う必要があります。
➡〔 提出先 〕住所地、または本籍地の市町村役場
⑤ 姻族関係終了届
・姻族関係終了届は、配偶者が死亡した場合に、配偶者の親族(血族)との姻族関係を終了させるための手続きです。この届出をすることで、亡き配偶者の親(義父母)との法律上の関係が終了します。
➡〔 提出先 〕住所地、または本籍地の市町村役場
⑥ 子の氏変更許可申請
・配偶者が死亡し、生存している配偶者が氏を変更する際、その氏を子どもにも名乗らせたい場合は、「子の氏変更許可申請」を家庭裁判所に申し立てる必要があります。家庭裁判所は子どもの利益を考慮して審査を行い、許可が下りると、子どもの氏が変更され、戸籍に反映されます。
➡〔 提出先 〕子の住所地の家庭裁判所
2.受取りの手続き
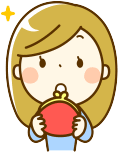
配偶者や親族が亡くなった場合、遺族が受け取るべき各種給付金や保険金、年金などの手続きが必要です。これらの手続きは、適切な機関への申請を通じて行います。
死亡した方が加入していた保険や年金の種類により、手続き先は異なりますが、必要な書類を揃え、各機関で申請を進めることで、遺族が受け取るべき給付をスムーズに受け取ることができます。
以下に代表的な受取りの手続きについてまとめましたので、ご確認ください。
① 生命保険金:〔生命保険会社、損害保険会社〕
・被保険者が死亡した場合に受け取れる保険金の請求手続きです。契約内容に基づき、遺族が指定された保険金を受け取ることができます。
② 入院、手術給付金:〔生命保険会社、損保保険会社〕
・死亡に至る前に入院や手術を受けた場合、その費用をカバーする給付金の受け取り手続き。
③ 葬祭費(国民健康保険):〔市区町村役場〕
・国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合に支給される葬祭費の手続きです。市区町村役場で申請を行います。
④ 埋葬料(健康保険):〔健康保険協会支部、全国保険協会〕
・健康保険に加入していた方の葬儀に対して支給される埋葬料の手続。
⑤ 葬祭料(労災保険): 〔労働基準監督署〕
・労働者が労働災害で死亡した場合、葬祭費として支給される手続。
⑥ 死亡退職金:〔雇用先企業〕
・会社に勤務していた方が亡くなった場合に支給される死亡退職金の手続き。
⑦ 雇用保険未支給失業給付:〔ハローワーク〕
・亡くなった方が失業給付を受け取っていなかった場合、その未支給分を遺族が受け取る手続き。
⑧ 生命保険付き住宅ローン:〔住宅ローン会社、銀行〕
・生命保険が付帯されている住宅ローンの場合、死亡により保険金でローン残高が支払われる手続き。
⑨ クレジットカード:〔クレジットカード会社〕
・亡くなった方のクレジットカードを利用していた場合、残債の支払いやカードの停止手続きを行います。
⑩ 年金関係:〔年金事務所〕
・死亡した年金受給者に関する手続き、未支給年金の請求や遺族年金の手続きを年金事務所で行います。
⑪ 年金受給者死亡届け:〔年金事務所〕
・年金を受給していた方が亡くなった場合、その旨を年金事務所に届け出る手続き。
⑫ 未支給年金:〔年金事務所〕
・亡くなった方の未支給年金を遺族が受け取るための手続き。
⑬ 遺族年金:〔年金事務所〕
・配偶者や子供などが受け取ることのできる遺族年金の請求手続き。
⑭ 個人年金:〔保険会社〕
・個人年金に加入していた場合、その契約内容に基づき死亡保険金や年金の請求手続きを行います。
⑮ 遺族補償年金 (労災保険):〔労働基準監督官〕
・労災事故で死亡した労働者の遺族に支給される補償金の手続き。
受け取り手続きは、必要な手続きを漏れなく行うことで、遺族や家族が負担を軽減し、スムーズに次のステップへ進むことができます。故人の名義変更や受け取り手続きは、期限内に確実に行うことが大切です。各手続きに必要な書類や注意点をしっかり確認し、手続きを進めていきましょう。
3.廃止の手続き
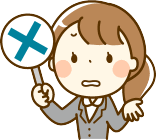
故人が契約・登録していた各種サービスや会員証については、速やかに解約・廃止手続きを行う必要があります。手続きを行わないと、不要な請求が続いたり、第三者による不正利用のリスクが生じる可能性があります。以下、主な手続き先と必要な対応についてご案内します。
① 運転免許証:〔国家公安委員会、最寄りの警察署〕
・運転免許証の名義変更や返納手続きは、最寄りの警察署や運転免許センターで行います。
② JAF会員証:〔JAF〕
・故人がJAF会員であった場合、JAFに連絡し、会員の解約手続きを行います。これにより、会員費の請求を停止できます。
③ 身分証明書:〔学校・会社〕
・学校や会社で使用していた身分証明書については、学校や勤務先で返納手続きを行います。身分証明書の返納により、故人の名前での不正利用を防ぎます。
④ 新 聞:〔学校・会社〕
・故人が定期購読していた新聞の購読を解約するためには、契約している新聞社に連絡を入れます。これで未払いの購読料を防ぐことができます。
⑤ ケーブルテレビ:〔運営会社〕
・ケーブルテレビの解約手続きは、サービスを提供しているケーブルテレビ運営会社に行います。不要な視聴契約を停止するための手続きです。
⑥ スポーツクラブ:〔運営会社〕
・故人がスポーツクラブの会員だった場合、その運営会社に解約の連絡を行います。会員費の継続支払いを避けるために重要です。
⑦ 携帯電話:〔電話会社〕
・故人が契約していた携帯電話の解約手続きは、契約している電話会社に連絡します。月額料金の請求を停止し、名義変更も行えます。
⑧ 貸金庫:〔契約銀行〕
・故人が契約していた貸金庫の解約は、契約銀行で行います。遺族が必要な手続きをし、契約を解除することができます。
廃止の手続きは、故人に関連する契約やサービスを適切に終了させるために重要なステップです。各手続きは期限内に行い、不要な支出や手続きを防ぐことができます。必要書類や手続きの流れを事前に確認し、漏れなく手続きを進めましょう。
4.継続の手続

故人が契約・所有していた財産や契約の中には、そのまま継続が必要なものがあります。これらの手続きを怠ると、サービスの停止や権利の喪失につながるため、適切に対応しましょう。
① 自動車:〔陸運局〕名義変更や廃車手続きを行います。
② 自動車保険:〔損害保険会社〕契約内容の確認・変更を行います。
③ 火災保険・家財保険:〔損害保険会社〕継続または解約の判断を行います。
④ 預貯金口座:〔銀行、郵便局〕相続手続きを進めます。
⑤ 株式・有価証券:〔証券会社〕名義変更手続きを行います。
⑥ 公共料金:〔電力会社・ガス会社・水道局〕契約者変更や支払い方法の確認が必要です。
⑦ NHK:〔NHK〕契約者変更や解約の手続きを行います。
⑧ 借地・借家:〔地主・家主〕契約の引継ぎを確認します。
⑨ 敷金・補償金:〔家主・不動産会社〕清算・継続の手続きを行います。
⑩ 住宅・土地:〔法務局〕所有権移転登記を行います。
⑪ 信金・組合出資金:〔信用金庫〕出資金の相続手続きを行います。
⑫ 貸付金:〔金融機関〕返済・相続手続きを進めます。
⑬ 自動車納税者:〔東京運輸支局又は自動車検査登録事務所〕名義変更や納税手続きを行います。
⑭ ゴルフ会員権:〔ゴルフ場〕会員権の相続・継続手続きを行います。
⑮ 特許権:〔特許庁〕権利継承手続きを行います。
⑯ 音楽著作権:〔一般社団法人日本音楽著作権協会〕権利の継続手続きを進めます。
⑰ 事業免許・届出:〔法務局〕事業継続のための手続きを確認します。
継続手続きは、故人の財産や契約を守るために重要なものです。早めに関係各所へ問い合わせを行い、必要な手続きを進めることが大切です。
5.相続関連の手続
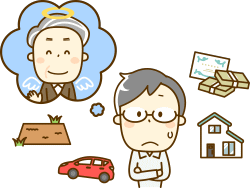
相続が発生すると、さまざまな法的手続きを進める必要があります。相続手続きは、財産の確認から相続人の特定、遺産の分割に至るまで、多岐にわたります。これらの手続きを適切に進めることで、スムーズな相続が実現します。以下に、相続に関連する主要な手続きについて簡潔に解説します。
① 遺言書の確認:〔家庭裁判所〕
・まず、故人に遺言書があった場合、その内容を確認します。自筆証書遺言のは、家庭裁判所で遺言書検認を行います(法務局保管除く)。遺言書がない場合、法定相続に基づいて手続きを進めます。
② 相続人調査:〔市区町村役場〕
・相続人を確認するためには、故人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本を取得する必要があります。戸籍謄本は市区町村の戸籍課等で取得します。戸籍から相続人の調査を行い、誰が相続人であるかを確定します。相続人が複数名いる場合、遺産分割協議が必要となります。
③ 相続財産調査:〔各銀行・法務局〕
・相続財産の内容を把握するため、銀行の通帳や残高証明書等を取得するなど金融資産の調査を行います。不動産は、法務局で登記簿謄本を取得し確認します。
④ 遺産分割協議〔状況により家庭裁判所〕
・相続人全員で遺産をどのように分けるかを決める「遺産分割協議」を行います。協議が成立した場合は、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・押印をもらいます。もし協議がまとまらない場合、家庭裁判所で調停を申し立てを行うなどの解決策が必要になります。
⑤ 不動産の相続登記:〔法務局〕
・不動産が相続財産に含まれている場合、法務局で相続登記を行い、不動産の名義を変更します。相続登記は3年以内に行うことが義務化され、この期限を過ぎると、罰則が課せられることもあるため、早めに行うことが重要です。
⑥ 法人役員変更: 〔法務局〕
故人が法人の役員であった場合、その法人の役員変更手続きを行います。
相続手続きは複雑で時間がかかることもありますが、適切に進めることで円滑に終了します。相続に関する疑問や不安がある場合は、ぜひご相談ください。
6.税務関連の手続
相続発生後、故人の状況、相続財産額に応じて準確定申告や相続税申告が必要になります。それぞれ申告期間が定められていますので、忘れない様に注意しましょう。
① 準確定申告:〔故人の住所地の税務署〕

通常の確定申告は、1月から12月までの1年間に得た所得について、次の年の2月16日から3月15日の期間内に所得を得た本人が申告をします。 しかし、申告すべき被相続人が年の途中で亡くなった時は、相続人が被相続人に代わって準確定申告を所轄の税務署に行います。
この準確定申告は、亡くなった日までの申告を行うことになります。そして、相続開始を知った日の翌日から 4 か月以内に相続人が申告と納税をしなければいけません。
~ 確定申告をしていた可能性がある人 ~
- 個人事業(自営業)を行っていた人
- 給与所得で2,000万円を越えた収入があった人
- 1つの会社から所得を得ていて、この所得以外に20万円以上の所得があった人
- 不動産収入(アパートや土地などの賃貸借等)があった人
- 不動産等の資産を売却した人
- 生命保険や損害保険の一時金や満期金を受け取った人
- 高額な医療費を支払っていて確定申告をすることで所得税の還付を受けられる人
~準確定申告の手続~
- 申告者:相続人または包括受遺者。相続人が複数人いる場合は連署で行う。
- 申告先:被相続人の死亡当時の住所地を管轄する税務署 《※相続人の住所地を管轄する税務署ではないので注意!》
- 必要書類:確定申告書、確定申告書の付表、給与や年金の源泉徴収票、医療費控除のための領収書、生命保険や損害保険の控除証明書《※他にも書類も必要になる場合があります。》
② 相続税申告:〔故人の住宅地の税務署〕
相続税の申告は、相続発生から10ヶ月以内に行う必要があります。相続税申告書は、故人の住所地を管轄する税務署に提出します。
7.預貯金の口座名義変更・解約の手続

・相続が開始されますと被相続人の財産は、相続人の共有財産になりますので、遺産分割協議が確定するまで、銀行は預金の引出しを凍結します。預金を解約したり、名義変更したり、引き出すためには、次の書類を銀行に提出しなければなりません。
(各金融機関により異なる場合がありますので事前にお問い合わせされることをお勧めいたします。)
- 銀行預金を誰が取得したかを示す遺産分割協議書
- 遺産分割協議替を作成していない場合は、引き出すことに相続人全員が承諾したことを示す承諾書
- 亡くなった人の戸(除)籍謄本および相続人の戸籍謄本
- 銀行所定の死亡届出書
- 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
※民法改正により遺産分割前に相続貯金の払い戻しが出来る様になりました。
単独で払い戻し出来る金額(口座ごと)=相続開始時の預金額✕1/3✕払戻しを行う相続人の法定相続分
※同一の金融機関からの払い戻しは150万円が上限になります。

例)として、相続開始時の預金(1口座)600万円、相続人2人の場合。
お1人で払戻し出来る金額は=600万円✕1/3✕1/2=100万円となります。
8.生命保険金 受取りの手続
・生命保険金は、故人が死亡した時点で所有していた財産でなく、死後に保険会社から受取人に支払われるものです。従って、受取人に指定された人が生命保険を請求しなければ支給されません。
(1)保険会社に提出する書類
受取人が指定されているときは、遺産分割協議を経由せずに、生命保険金の支払いが行われますので、遺産分割協議書は不要です。
- 保険会社所定の保険金請求書
- 保険証券
- 医師が発行する死亡診断書、死体検案書
- 被保険省の死亡の事実記載のある住民票の除票または戸籍謄(抄)本
- 保険金受取人の印鑑登録証明書(発行から6 か月以内のもの)
- 保険金受取人の戸籍謄本
- 死亡の原因が不慮の事故による場合は、事故を証明する書類(事故状況報告書等)、災害事故証明書兼交通事故状況届出書、交通事故証明書
※契約内容・保険会社により必要な書類が異なる場合があります。
(2)生命保険金の受取人が1人に特定できないとき
生命保険金の「受取人が相続人」とされている場合や「受取人が既に死亡し新たな受取人の指定がない」場合など、受取人を1人に特定できない時は、受取人全員の協議により、代表者を決めて保険金の支払いを請求することができます。この場合は、保険会社に代表者選任届を提出しなければなりません。
(3)遺言による受取人の変更
遺言による受取人の変更の場合、遺言の効力が生じた後、保険契約者の「相続人がその旨を保険者に通知しなければならない。」とされています。従って、遺言で受取人の変更になった場合は、生命保険会社への通知と共に、上記、提出書類+「公正証書遺言書」又は、「自筆証書遺言書」(原本提出を要求される場合あり)が追加されることになります。
9.相続で必要な届出や手続 まとめ

相続で必要な届出や手続についてまとめさせて頂きました。一人の方がお亡くなりなると、これほどの手続などが発生することになります。祖族人の方が1人で行うのは、非常に大変であり時間も掛かります。もし、ご自身で相続手続きを行うことが難しい場合は、当事務所にお気軽にご相談下さい。
相続一式のサポートからご自身では行うことが難しい部分的なサポートなど、ご希望の範囲でサポートさせて頂きます。なお、当事務所にご依頼頂いた場合は、当事務所が窓口となり、司法書士、税理士と連携して相続手続きを行わせて頂きますので、お客様がご自身で探すことも不要になります。
また、当事務所は平成21年度開業の行政書士事務所であり、これまで多くの相続手続を行っておりますので、安心してご相談下さい。ご相談だけでも大丈夫です。
»» 次の記事:遺産分割協議を行う前に知っておきたいことは? »»
«« 前の記事:相続問題!これだけは知っておきたい基礎知識 ««
大塚法務行政書士事務所 大塚博幸

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)