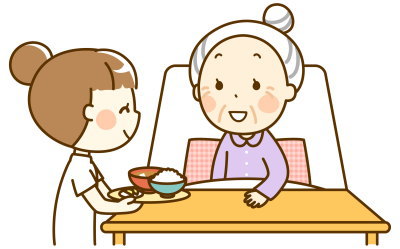・相続は、大切な人が亡くなった後、私たちが必ず向き合う問題の一つです。しかし、相続には複雑な手続きや法律が絡んでおり、どこから手をつけてよいか分からないという方も多いのではないでしょうか?
本記事では、相続の基本的な概念から、相続財産の種類、実際の手続きの流れ、相続に関わる税金の知識まで、相続に関する大切な情報を分かりやすく解説します。
どの様な場合に相続放棄や限定承認を選ぶべきか、また、相続税の基礎控除額や申告の方法など、実務的なポイントも解説いたします。相続に直面したとき、適切に対応できるようにするための第一歩として、この記事を役立ててください。
1. 相続とは?

相続とは、両親や親族が亡くなった際に、その人の財産的な権利や義務を一定の身分関係にある相続人が受け継ぐことを指します。相続は 被相続人(亡くなった人)が死亡した瞬間から開始 し、相続人は相続財産を取得する権利とともに、負債を引き継ぐ可能性もあります。
相続開始の時期
相続の開始時期は 被相続人が死亡した瞬間 です。死亡届の提出日ではなく、死亡した日が基準となります。
例えば、Aさんが 3月1日に亡くなった場合、相続は3月1日に開始されます。仮にAさんの家族が3月5日に死亡届を役所に提出しても、相続の開始日は3月1日になります。このため、相続に関する手続は、死亡日を基準に進める必要があります。
2. 相続財産とは?
(1)相続財産の定義

民法では、「相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。但し、被相続人の一身に属したものはこの限りではない。」 と定められています。つまり、 被相続人が生前に所有していた財産や負債 は基本的にすべて相続の対象となります。ただし、 個人的な権利(例:扶養請求権、年金受給権など)は相続できません。
例として、ご主人が亡くなった時から、相続権のある方(配偶者・子等)が権利義務を承継するということになります。
(2)相続財産の分類
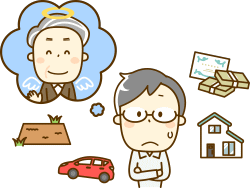
相続財産は、大きく プラスの財産 と マイナスの財産 に分類されます。相続人が引き継ぐのは、これらの財産の両方です。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続しなければならないため、相続人は財産の確認と評価を慎重に行うことが重要です。
プラスの財産は、相続人が遺産として受け継ぐことのできる価値のある財産です。これには、以下のものが含まれます。
・土地や建物がこれに該当します。これらは、物理的な価値を持つため、相続財産の中でも大きな割合を占めることがあります。相続後、名義変更を行う必要があります。
・現金、預金、株式、投資信託などの金融資産は、最も一般的な相続財産です。これらの資産は現金化が容易であり、相続財産の中でも重要な部分を占めます。相続後、銀行や証券会社で名義変更の手続きが必要です。
・自動車、貴金属、家具、宝石、骨董品などの動産も相続財産として評価されます。これらは物理的なものに価値があるため、適切に評価し、分配の際に考慮する必要があります。
・著作権、特許権、ゴルフ会員権、貸付金、売掛金など、財産的価値を持つ権利や契約も相続財産に含まれます。これらは相続後に譲渡するか、承継する方法を決める必要があります。
マイナスの財産は、借金や未払いの義務など、相続人が引き継ぐ必要がある負債です。相続人はプラスの財産だけでなく、以下のようなマイナスの財産も承継します。
被相続人が生前に負っていた借金(例:住宅ローン、消費者金融の債務、クレジットカードの未払い金など)は、相続人が引き継ぐことになります。多額の借金がある場合、相続放棄を選択することも検討する必要があります。
税金、医療費、家賃、公共料金など、被相続人が生前に支払っていなかった未払いの金銭も相続財産に含まれます。これらの未払金についても、相続人が支払い義務を負うため、しっかりと確認しなければなりません。
被相続人が他人の借金の保証人であった場合、その保証債務も相続人に引き継がれます。保証債務の内容によっては、相続人が高額な負担を背負うことがあるため、注意が必要です。
相続財産には、上記のプラスとマイナスの財産以外にも特定の財産が含まれることがあります。
生命保険金は、受取人指定がされている場合、原則、相続財産に含まず遺産分割の対象にもなりません(みなし相続財産として、相続税申告の対象には含まれます)。しかし、被相続人が受取人として指定されていた場合、保険金は相続財産となり分割の対象になります。
借地権や借家権などの使用権も相続対象です。借地権は原則として相続できますが、第三者に譲渡する場合には地主の承諾が必要です。
相続財産は、ただ単に物理的な財産だけでなく、権利や義務も含まれるため、相続手続きを行う際は注意深く評価し、適切に分割を行うことが重要です。また、マイナスの財産をどのように扱うかも重要な判断となります。
3.相続の流れ

相続手続きは、被相続人(亡くなった方)の財産や権利義務を相続人が承継するために必要な手続きのことを指します。相続が開始すると、一定の期限内にさまざまな手続きを行う必要があり、適切な準備と対応が求められます。以下に、一般的な相続手続きの流れを説明します。
(1)被相続人の死亡(相続開始)
相続は、被相続人の死亡と同時に開始します。死亡届の提出とは関係なく、相続開始日は死亡日が基準となります。相続人は、被相続人の財産や負債を引き継ぐ立場になりますが、以降の手続きを進めるにあたって慎重に判断する必要があります。
(2)死亡届の提出と葬儀の実施
被相続人の死亡後、死亡届を市区町村役場に提出する必要があります(届出期限:死亡日を含めて7日以内)。この手続きにより、戸籍が抹消され、埋火葬許可証が発行されます。(埋火葬許可証は、火葬、埋葬の際に必要になる書類ですので、大切に保管して下さい。)同時に、僧侶や親族などの調整を行い葬儀の準備、手配も進めて行きます。
死亡届は、以下のいずれかの市区町村役場に提出することができます。
- 被相続人(亡くなった方)の本籍地の役所
- 被相続人が亡くなった場所の役所(死亡地)
- 届出人(親族など)の住所地の役所
提出は24時間365日可能で、夜間や休日でも役所の「時間外窓口(宿直室など)」で受け付けてもらえます。
- 死亡届(死亡診断書付き) ※医師が記入したもの
- 届出人の本人確認書類(運転免許証など)
- 認印
(3)遺言書の有無の確認
次に、遺言書の有無を確認します。もし遺言書がある場合、原則、遺言書に従って遺産分割を進めることになります。遺言書が公正証書遺言であれば、家庭裁判所での検認手続きは必要ありませんが、自筆遺言や秘密証書遺言の場合、家庭裁判所での検認が必要となります。(法務局の自筆証書遺言制度を利用している場合は、検認不要。)
(4)相続財産の調査・評価、相続人の確定調査
次に、相続財産の調査を行います。相続財産は、不動産、金融資産、動産、権利関係などが含まれます。これらを整理し、評価額を決定する必要があります。また、相続人を確定するために、戸籍謄本を取り寄せるなどの手続きを行い、誰が法定相続人なのかを確認します。なお、財産調査を行った後に財産目録を作成し、関連する資料をファイリングしておくと整理が行い易くなります。
- 被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本(被相続人の死亡日以降に取得したもの)
- 相続人の住民票(被相続人の死亡日以降に取得したもの)
- 印鑑証明書(銀行等の有効期間に注意)
- 法定相続情報一覧図(状況に応じて)
戸籍・住民票は、銀行手続、不動産所有権移転登記、相続税申告などの相続手続で必要になります。最初にまとめて取得しておいた方が、何度も役所に足を運ばずに済みます。但し、銀行等により印鑑証明書の有効期間(3か月、6か月など)が定められている場合が、ありますので、ご注意下さい。
もし、手続先が多い場合は、「法定相続情報一覧図」取得しておくと、手続の際に、戸籍等の提出が不要になりますので、こちらを取得しておくことも一つの方法です。
(5)相続放棄・限定承認の手続き(3か月以内)
相続財産が負債を超える場合など、相続に不安がある場合は、相続放棄や限定承認を検討します。相続放棄は、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申し立てて行うことができます。相続放棄をすると、相続人は初めから相続人ではなかったことになります。限定承認は、相続財産が負債を上回る場合に、負債を超えない範囲でのみ相続する方法です。
※相続の承認又は放棄は、相続の開始があったことを知った時から、3か月以内(原則)となっております。この期間内に何もしないと、単純承認したものとみなされますので注意が必要です。
(6)遺産分割協議の実施
相続財産が確定し、相続人が確定したら、遺産分割協議を行います。これは、相続人が集まり、誰がどの財産を受け取るかを決める重要な手続きです。遺言がない場合、法定相続分に従って分割することが基本ですが、相続人全員が合意することで、柔軟な分割方法を選ぶことも可能です。協議が整わない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
(7)準確定申告の提出(4か月以内)
相続が開始した後、準確定申告を行う必要があります。準確定申告は、被相続人の死亡後4か月以内に行います。これにより、亡くなった方の税金や未払いの確定申告が行われます。相続財産に所得がある場合や、課税対象の収入がある場合は、必ず準確定申告を提出する必要があります。
- 給与収入が2,000万円を超える
- 複数の企業から給与収入がある
- 事業所得や不動産所得がある
- 公的年金の収入が400万円を超える
- 副業収入が20万円を超える
- 配当所得や株式売却による利益がある
準確定申告は、被相続人が事業を行っていた場合、給与以外の収入があった場合、または年末調整を受けていない場合などに必要となります。
・準確定申告に関する詳細は、国税庁HPをご覧ください。
⇒ 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
(8)相続税の申告・納税(10か月以内)
相続が発生した場合、相続財産が一定額を超えると相続税が発生し、申告が必要となります。相続税の申告は、相続開始から10か月以内に行う必要があります。
相続税が課税されるかどうかは、相続財産の総額が基礎控除額を超えるかに依存します。基礎控除額は以下の式で計算されます。
- 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
この基礎控除額を超えた場合、相続税の申告が必要になります。
相続財産が基礎控除を超える場合、相続税申告が必要です。申告対象には、現金、預金、不動産、株式、保険金などすべての相続財産が含まれます。また、負債(借金)も相続財産に含まれ、相続財産から差し引くことができます。
・相続税に関する詳細は、国税庁HPをご覧ください。
⇒ 相続税の申告手続
(9)相続財産の分配と名義変更
遺言書または遺産分割協議書にもとづいて、相続人間で財産の分配を行います。不動産の相続登記、預貯金・証券などの解約・名義変更など申請に必要な書類を準備し、各機関に手続きを行います。
- 遺言書または遺産分割協議書
- 被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍(改正原戸籍・除籍)謄本
- 被相続人(故人)の住民票の除票
- 相続人の戸籍・住民票
- 相続人の印鑑証明書
- 固定資産評価証明書(申請時の年度)
- 不動産の登記簿謄本
- 被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍(改正原戸籍・除籍)謄本
- 被相続人(故人)の住民票の除票
- 相続人の戸籍・住民票
- 相続人の印鑑証明書
- 銀行の通帳など
※銀行により必要な書類が異なる場合があります。
※被相続人・相続人の戸籍・住民票に代えて法定相続情報一覧図を提出することも可能。
4.相続承認の種類
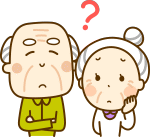
相続の承認には3つの種類があります。これらの方法は相続人がどのように相続財産を引き継ぐかを決定するため、選択によってその後の手続きや責任が大きく異なります。以下で、各種類について具体的に解説します。
(1)単純承認
単純承認とは、相続人が積極的に相続を受け入れる意思表示をせず、相続開始から特に手続きを取らない場合に、法律上、自動的に相続が承認されることです。これにより、相続人は財産(プラスの財産)も負債(マイナスの財産)も引き継ぐことになります。
相続人は、財産と負債の両方を引き継ぐことになります。負債を引き継ぐことに注意が必要です。何も手続きをしなければ、単純承認となります。
(2)限定承認
限定承認とは、相続人が相続を受ける際、相続財産の範囲内でのみ負債を引き継ぐ方法です。これにより、相続人は財産がプラスであれば受け取りますが、負債が大きい場合はその範囲内で負債を清算します。
- 相続開始(死亡):相続開始後、相続人は相続権を持ちます。
- 限定承認の意思決定:相続人は、相続財産を整理し、負債がある場合に限定承認を選択するか決定
- 家庭裁判所への申請:限定承認は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
- 家庭裁判所の認可:家庭裁判所が限定承認を認めると、相続財産の範囲内で負債を引き継ぎます。
- 相続財産の清算:相続人は、財産と負債を整理し、財産がプラスであれば受け取ります。負債があれば、財産で清算されます。
- 申述書(裁判所の所定様式)
- 被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍(改正原戸籍・除籍)謄本
- 被相続人(故人)の住民票の除票(戸籍の附票)
- 相続人の戸籍謄本など
限定承認は、相続人全員の合意が必要です。相続財産と負債を整理するため、手続きには時間がかかることがあります。
・限定承認の申述に関する詳細は、裁判所HPをご覧ください。
⇒ 相続の限定承認の申述
(3)相続放棄
相続放棄とは、相続人が相続権を放棄し、相続財産を一切受け取らないことを決定する手続きです。放棄した相続人は、最初から相続人でなかったことになります。
- 相続開始(死亡):相続開始後、相続人は相続を受ける権利が発生します。
- 相続放棄の意思決定:相続人が相続放棄を決定し、家庭裁判所に申し立てます。
- 家庭裁判所への申請:相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。申立ては、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
- 放棄認定:家庭裁判所が相続放棄を認めると、相続人は正式に放棄され、他の相続人が相続権を持つことになります。
- 相続放棄の申述書(裁判所の所定様式)
- 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本
- 被相続人(故人)の住民票除票(戸籍附票)
- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本など
- その他、放棄する相続人により取得する戸籍が異なります。
申し立ては相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。相続放棄をすることで、最初から相続人ではなかったことになり、他の相続人が相続を受けることになります。(相続放棄した場合、代襲相続は行われません。)
・相続放棄の申述に関する詳細は、裁判所HPをご覧ください。
⇒ 相続の放棄の申述
相続登記の義務化(令和6年4月1日~制度開始)
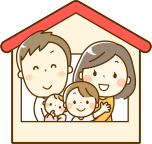
令和6年4月1日から、相続登記の義務化が施行されました。相続が発生した場合、相続開始から3年以内に相続登記を行わなければならないことが定められています。
この義務化により、相続人は遺産分割協議を行い、不動産の名義変更を迅速に行う必要があります。なお、正当な理由なく登記をしない場合、過料(10万円以下)が課される可能性もありますので、期限内に相続登記を完了させることが重要です。
相続人申告登記
相続登記が義務化され、相続人は登記を行う必要がありますが、遺産分割協議がまだ完了していない、または相続人の特定に時間がかかる場合など、相続登記をすぐに行うのが難しいこともあります。そういった場合に利用できるのが、相続人申告登記です。
相続人申告登記は、相続人が簡易に相続登記を行うための制度です。この方法では、相続人が登記申請をすることで、相続登記義務を履行することができます。しかし、いくつかの留意点があります。
相続人申告登記では、不動産の権利関係は公示されません。そのため、相続した不動産を売却したり、抵当権を設定したりする場合には、別途通常の相続登記を行う必要があります。
また、相続人申告登記を行っても、遺産分割に基づく相続登記を行うことはできません。遺産分割協議が終わらない限り、正式な相続登記は申請できないため、相続登記を申請する場合は、遺産分割協議が整ってから改めて登記を行う必要があります。
相続登記の義務化、相続人申告登記の詳細は、下記をご覧ください。
⇒ 相続登記が義務化されました。(東京法務局)
⇒ 相続人申告登記について(法務省)
5.相続の基礎知識 まとめ

相続は、故人の財産や義務を相続人が引き継ぐ重要な手続きです。相続が始まると、プラスの財産とマイナスの財産を含む遺産の確認や、相続税の申告が必要となります。遺言書がある場合はその内容に従い、ない場合は法定相続分に基づいて財産が分割されます。
相続手続きは複雑で、書類の準備や期限の管理が重要です。もし、ご自身で進めるのが難しい場合には、専門家のサポートを受けることでスムーズに手続きを進めることができます。
当事務所では、相続手続きに関するご相談、手続一式のサポートなど行わせて頂いております。また、戸籍の取得から法定相続情報一覧図の取得、銀行手続など、部分的なサポートも行わせて頂いております。
もし、相続手続でお困りの場合は、当事務所までお気軽にとお問合せ下さい。
»» 次の記事:相続で必要な各種届出や手続きについてのポイントと流れ »»
«« 前の記事:小規模な相続の相談とお手伝い ««
大塚法務行政書士事務所 大塚博幸

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)