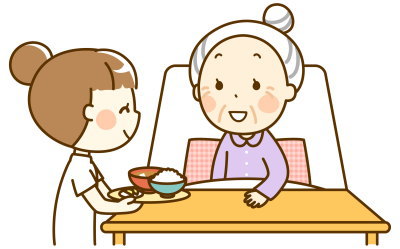・相続が発生した場合、残された配偶者が住み慣れた家に住み続けることができるかどうかは、非常に重要な問題となります。
そこで登場するのが、「配偶者居住権」という制度です。配偶者居住権は、民法改正により新たに設けられた制度で、相続発生後、残された配偶者が一定の条件で住まいを確保できる権利として法律で定められました。
この記事では、配偶者居住権とは何か、どのようにして成立するのか、そのメリットとともに詳細に説明します。
1.配偶者居住権とは?

夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者が故人名義の住宅に住み続けられる権利を「配偶者居住権」といいます。これは、住む家を失わないために設けられた法律上の権利で、短期のものと長期のものがあります。配偶者居住権を正しく理解し、相続にどのように活用できるかを解説します。
配偶者居住権が導入された背景
従来の民法では、配偶者が故人名義の自宅を相続する場合、他の相続人(子や親)との遺産分割により、家を売却せざるを得ないケースがありました。特に、配偶者が高齢で収入が少ない場合、住む家を失うリスクがありました。そこで、民法改正により、配偶者居住権が新設され、配偶者は自宅に住み続ける権利を確保できるようになりました。
参考 民法1028条(一部省略)
被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に※相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物の全部について※無償で使用及び収益をする権利を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 ※遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が※遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
解説
※注1)相続の開始時に住んでいることが条件になっています。住んでいない場合は、配偶者居住権の権利を得られないことになります。
※注2)無償で使用できますので、家賃等の支払いも必要ありません。
※注3)配偶者居住権は、遺産分割協議か遺言書等による遺贈により権利を取得出来ることになります。
参考リンク
法務省:残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます。
法務局:配偶者居住権と何ですか?
2.配偶者《短期》居住権とは?
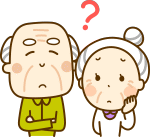
配偶者短期居住権は、相続が発生した際に、残された配偶者が一定期間は無償で自宅に住み続けられる権利です。なお、故人(被相続人)が所有していた建物に配偶者が居住していたことが短期居住権の成立要件になります。
(1)短期居住権の存続期間
短期居住権の存続期間は、以下のいずれか遅い日までです。
- 遺産分割協議により相続人のうち誰が建物を相続するか?決まったとき
- 相続開始(亡くなった日)の時から6ヶ月を経過する日
上記①②のいずれかの遅い日までの間住み続けることが可能になります。もし、遺産分割協議が早く成立した場合も、相続開始日から6ヶ月は住み続けることができ、6ヶ月を経過しても協議が成立するまでは住み続けることが出来ます。
(2)短期居住権の注意点
配偶者短期居住権は、配偶者を一時的に保護する権利になります。この権利を譲渡したり、建物取得者の許可なく第三者に使用させること等は出来ません。また、住んでいる建物は、善良な管理者の注意をもって使用し固定資産税等の費用、通常の修繕費用なども負担することになります。
譲渡・貸与不可:配偶者短期居住権は、他人に貸したり売却することは出来ません。
管理責任:配偶者は、善良な管理者として建物の修繕費や固定資産税の負担をすることになります。
登記不可:配偶者短期居住権は、登記はできません。もし、建物が第三者に譲渡された場合は,その第三者に配偶者短期居住権を主張できません。
3.配偶者《長期》居住権とは?
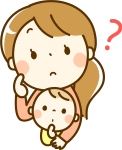
通常、配偶者居住権とは、こちらのことをいいます。配偶者居住権(長期)は、配偶者が亡くなるまで、または一定期間にわたり、自宅に住み続けることができる権利となります。民法改正によって導入され、相続が発生した場合も高齢の配偶者が住居を失わないように配慮された法律になります。
配偶者居住権の成立要件
ここでは、配偶者居住権の成立要件として、夫(故人)、妻(配偶者)のケースで解説いたします。
- 夫(被相続人)と妻(配偶者)が婚姻関係にあったこと(法律上の配偶者)。
- 夫が所有していた建物に、亡くなる時点で妻が居住していたこと。
- 遺産分割、遺言書の指定により配偶者居住権を取得したこと、または家庭裁判所の審判によって取得したこと。
短期配偶者居住権と違い、こちらは、通常、妻が亡くなるまでの期間になります。遺産分割等において居住する期間を定める事も可能です。
配偶者居住権者の義務
配偶者居住権者は、建物全部について無償で使用・収益することが出来ます。但し善良な管理者の注意をもって使用・収益する義務があります。
- 建物の増改築については、所有者の承諾が必要になります。
- 第三者に使用・収益させる場合は、所有者の承諾が必要になります。
- 固定資産税等の費用、通常の修繕費用なども負担することになります。
上記の義務に違反した場合は、所有者の意思表示により配偶者居住権が消滅される場合がありますので注意する必要があります。
また、配偶者居住権は第三者に対抗する為に登記を行う必要があります。この登記は、所有者(例:子)と配偶者(例:妻)が共同で申請を行います。(※建物の登記になります。土地は登記できません。)
4.配偶者居住権と遺産分割
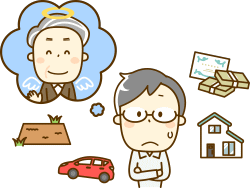
配偶者居住権の趣旨としては、相続発生時に残された配偶者が居住する家に困らない様に保護する制度になります。通常、配偶者居住権が設定されるまで、遺言書がない時は、法定相続分による分配になりますので下記の分配になります。
- 例)被相続人(夫)、相続人が妻と子1人の場合、妻と子で1/2ずつの分配になります。
相続財産が持家と現金の場合
例)持家の評価額が3,000万円、現金2,000万円、相続財産総額=5,000万円の場合
- 妻:5,000万円✕1/2=2,500万円
- 子:5,000万円✕1/2=2,500万円
妻が持家を相続すると...
- 妻=3,000万円(法定相続分+500万円)
- 子=2,000万円(法定相続分-500万円)
妻が500万円多く相続することになりますので、子に500万円を支払うことになります。しかし、500万円を現金で払う事が出来ない、持家を売却したら住む家も失ってしまう。この様な場合に配偶者を保護する制度として定められた法律が配偶者居住権になります。
配偶者居住権を利用した場合
上記の同様条件で配偶者居住権を利用した場合を解説します。
例)配偶者居住権の制度を利用し、その価格が1,500万円の場合
(法定相続分は2,500万円ずつ)
- 妻=2,500万円-1,500万円(配偶者居住権)=1,000万円
配偶者居住権を利用した場合、自宅に住みづけることができ、なおかつ1,000万円の財産を取得することも可能になります。主に相続財産が持家の場合、遺産分割で住む家を失わない様に、または、住む家とお金をバランスよく相続できるように積極的に活用するのも一つの方法です。
5.配偶者居住権の価格の計算法
国税庁のHPに配偶者居住権の価格の評価方法について記載されています。計算式は下記になります。
配偶者居住権の価格=
①居住用建物の相続税評価額-{ ①居住用建物の相続税評価額✕(②耐用年数-③経過年数‐④存続年数/②耐用年数-③経過年数)✕⑤存続年数に応じた法定利率による複利現価率 }
①居住用建物の相続税評価額:固定資産税評価額✕1.0
②耐用年数:国税庁HPの主な減価償却資産の耐用年数表から一部抜粋(住宅用のもの)
- 木造・合成樹脂造のもの 22年✕1.5=33年
- 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの 47年✕1.5=71年
③経過年数:建物の建築から現在までの経過年数
④存続年数:配偶者が居住権が設定された年数
- 一定の期間を定めた場合は、その期間。終身の場合は、厚生労働省公表の生命表の平均余命=存続年数
⑤存続年数に応じた法定利率による複利現価率:下記、国税庁の複利表は参考にして下さい。
計算例(配偶者居住権価格)
下記の例で配偶者居住権価格を計算例として算出します。参考にご覧下さい。
- 配偶者(女性)80歳 配偶者居住権 終身
- 相続税評価額=1,000万円(建物)・2,000万円(土地)
- 耐用年数=木造住宅 33年
- 経過年数=10年
- 存続年数=13年(平均余命12.25年)
- 複利現価率=0.681(法定利率3%)
配偶者居住権価格=1000万円-{1000万円✕(33年-10年-13年/33年-10年)✕0.681=704万円
=1,000万円(建物 相続税評価額)-704万円(配偶者居住権価格)=296万円(居住用建物の価格)
=2000万円(土地 相続税評価額)ー{ 2000万円(土地 相続税評価額)✕0.681(複利現価率)}=638万円(敷地利用権の価額)
=2000万円(土地 相続税評価額)-638万円(敷地利用権の価額)=1,362万円(居住建物の敷地価額)
参考リンク
詳細につきましては、下記のリンクをご覧ください。
・配偶者居住権等の評価
・主な減価償却資産の耐用年数表
・複利表
・第23回生命表(完全生命表)の概況
・第23回生命表(男)
・第23回生命表(女)
6.配偶者居住権の登記の流れ

配偶者居住権の登記は、配偶者が取得した居住権を公に記録し、第三者に対してその権利を主張できるようにする手続きです。権利関係のトラブルを防ぐため、早めに登記を行いましょう。なお、登記は建物所在地の法務局で申請します。
(1) 配偶者居住権の成立
配偶者居住権を登記するには、まず配偶者居住権が正式に認められる必要があります。これを実現するために、以下のいずれかの方法で権利を成立させることが求められます。
- 遺産分割協議:相続人同士が話し合い、合意によって配偶者居住権を設定します。
- 遺言:被相続人が遺言によって配偶者居住権を指定した場合、遺言内容に従い権利が成立します。
- 家庭裁判所の審判:相続人間で合意が得られない場合、家庭裁判所が配偶者居住権の設定を判断します。
これらの方法のいずれかで配偶者居住権が成立した後、次のステップとして登記手続きを進めることになります。
(2)必要書類の準備
配偶者居住権の登記を行うためには、以下の書類を準備する必要があります。
- 登記申請書(法務局所定の様式)
- 登記原因証明情報(遺産分割協議書、遺言書、家庭裁判所の審判書など)
- 登記識別情報(建物)
- 固定資産評価証明書(建物)※申請時の最新年度のもの
- 配偶者居住権者の戸籍謄本・住民票
- 建物を新たに所有する方の印鑑証明書(3か月以内のもの)など
その他、配偶者居住権の取得が遺産分割協議、または遺言書など状況に応じて、必要な書類が異なります。
・相続登記に必要な書類の詳細は、下記をご覧ください。
法務局:相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等
法務局:相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)
(3)法務局への登記申請
必要書類を準備したら、不動産の所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。法務局で申請書類が審査され、問題がなければ登記が完了します。登記が完了すると、不動産登記簿に「配偶者居住権」が記載されます。
登記の際の注意点
配偶者居住権は、登記をしていないと第三者(不動産を取得した人)に対して主張できません。権利を主張するためには第三者より先に登記を行う必要があります。配偶者居住権の取得後、なるべく早めに登記をしておきましょう。
登記には登録免許税がかかります。配偶者居住権の設定登記に掛かる登録免許税は、不動産価格の1000分の2になります。
通常の場合、配偶者居住権の登記をしても土地、建物の所有者は別の相続人になります。後のトラブルにならないように建物の管理や修繕等について事前に話合いをしておきましょう。
7.配偶者居住権と遺言書の関係
配偶者居住権は、遺言によって設定することが可能です。※民法1028条の規定により、遺言では「遺贈」として記載します。
遺言書文例
〇条 遺言者は遺言者の所有する次の建物の配偶者居住権を妻〇〇 〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇生)に遺贈する。同配偶者居住権の期間は妻〇〇 〇〇の死亡時までとする。
〇条 遺言者は遺言者の所有する次の建物の負担付所有権を長男〇〇 〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇生)に遺贈する。
〇条 遺言者は遺言者の所有する次の土地を長男〇〇 〇〇に相続させる。
建物(登記簿謄本を取得し詳細に記載)
土地(登記簿謄本を取得し詳細に記載)
こののように、配偶者居住権を遺贈するという形で明記します。
(1)遺言書がない場合のリスク
配偶者居住権の設定には、遺言書、遺産分割、家庭裁判所の審判など法定要件を満たす必要があります。もし、遺言書がない場合、相続人全員の話合いが必要となり、配偶者が希望通り自宅に住み続けられない可能性も考えられます。
また、配偶者短期居住権(被相続人の死後、最低6か月間は無償で住み続けることができる権利)は法的に保証されていますが、それを超えて住み続けるには、相続人間の合意が必要になります。配偶者の生活を安定させるためにも、遺言書で明確に配偶者居住権を設定することが望ましいと言えます。
(2)相続・配偶者居住権のどちらを選択するべきか
遺言書を作成される際に、配偶者居住権の設定か所有権の相続か悩む方もいるのではないでしょうか。どちらを選ぶ方が良いか難しい問題ですが、不動産の価格と他の金融資産とのバランスを考慮する必要があります。また事前の話合いで相続人が納得されるのであれば、全ての財産をを妻が相続することも可能です。(但し遺留分の問題が残ります。)
主たる財産が持家の場合に、遺産分割で揉める可能性がある時は、配偶者居住権の設定を考慮し、不動産価格と金融資産が同等の場合などは、妻に不動産を相続させ、金融資産を子供に相続させる方法なども考えられます。
まずは、ご自身の財産の種類と金額を確認し、遺産分割で揉める可能性も考慮した上で、どちらを選ぶか検討されて見てはいかがでしょうか。その他、家族信託で持家を信託する方法などもありますので、もし判断が難しい場合は、一度専門家にご相談することをお勧めします。
(3)遺言書作成をお考えの方へ
遺言書作成をお考えの場合は、こちらもご覧ください。
・《遺言書作成》相談・サポート
葛飾区在住の方で遺言書作成をお考えの方は、こちら
・葛飾区で遺言書作成をお考えの方へ
8.婚姻期間20年以上の夫婦の優遇措置
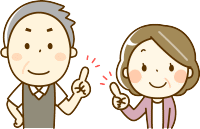
法改正により婚姻期間20年以上の夫婦間で行われた居住用不動産の生前贈与・遺贈は、原則、相続財産の先渡しとして計上せずに良いとになりました。つまり、居住用不動産評価額分は、相続財産に含めずに遺産分割を行う事が出来ます。
また、配偶者居住権においても、婚姻期間20年以上の夫婦で、夫が妻に配偶者居住権を遺贈した場合等、その居住権評価額も原則、相続財産から除外されます。
※遺贈は遺言書作成して行う事が一般的です。重要な書類になりますので公正証書遺言をお勧めします。
8.配偶者居住権Q&A
配偶者居住権を取得すると、相続開始時に居住していた建物に対して、無償で居住し、使用および収益する権利が得られます。この権利は、遺産分割や遺贈を通じて取得することができます。
配偶者居住権に期限を定めていない場合は、配偶者が生存している限り、終身にわたって存続します。ただし、期限を定めた場合は、設定された期間内に限られます。
配偶者短期居住権は、相続開始時に居住していた建物に対して、一定期間無償で居住する権利です。この期間は、遺産分割が確定するまでまたは相続開始から6ヶ月を経過する日までのいずれか遅い日までになります。
配偶者短期居住権を取得すると、居住建物の使用について善良な管理者として取り扱う義務があります。また、原則、第三者にその建物を使用させることはできません。
登記の有無はご自身の判断にもよりますが、第三者に配偶者居住権を主張する為には、登記をする必要があります。
配偶者居住権を持っている場合、居住建物に必要な修繕を行うことができます。修繕が必要な場合は、所有者に通知することも必要です。
配偶者居住権が消滅した後、居住建物を返還する義務があります。ただし、配偶者がその建物について共有持分を有している場合、返還を求められないことがあります。
配偶者居住権は譲渡できません。この権利は配偶者本人にのみ帰属し、他の者に移転することは認められていません。
配偶者居住権の存続期間や条件は、遺産分割協議や遺言によって異なる定めがされることがあります。配偶者が同意すれば、条件を変更したり、期間を短縮することも可能です。
配偶者短期居住権が終了した後は、特別な手続きは不要ですが、居住建物を返還する義務があります。返還時には、建物を元の状態で返却することが求められます。
5.まとめ

民法改正により配偶者の住居を守る法律が充実したと言えます。
現在まで相続財産が主に不動産の場合、遺産分割は故人の持家を売却しないと出来ない為、仕方なく家を売却する方もおりました。しかし、この権利の行使することにより、配偶者の方が住み慣れた家を失う可能性が低くなったとも言えます。但し、配偶者の生活を困らない様にしておきたいとお考えなら、事前に遺言書を作成しておく方がより安心と言えます。
特にお子様がいない夫婦の場合、相続人は配偶者と故人の親又は兄弟になりますので、遺言書を作成しておきましょう。
最後までお読み頂きまして有難うございました。当事務所は平成21年度開業の行政書士事務所になります。遺言書や相続人に関するご相談がありましたら、ご遠慮なく当事務所にご相談下さい。これまで公正証書遺言書の作成サポートや相続手続一式代行のご依頼を数多く頂き、経験豊富な事務所ですので安心してお問合せ下さい。ご相談だけでも大丈夫です。
»» 次の記事:知っておきたい!相続預金の払戻し制度 »»
«« 前の記事:寄与分・特別の寄与とは何か? ««
大塚法務行政書士事務所 大塚博幸

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)