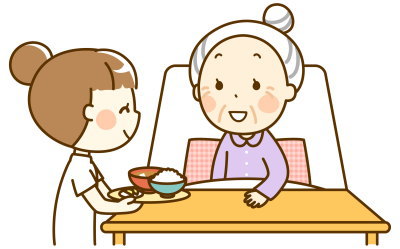・相続財産は、被相続人が所有していた財産を指し、基本的に金銭的価値が評価できるものが対象となります。
一般的に相続財産には不動産、預貯金、株式など、目に見える形で金銭評価ができる資産が含まれます。遺産分割においても、相続税の課税対象となるのは、このような金銭評価可能な財産が基本です。
なお、生命保険や死亡退職金等の一部の財産は、受取人指定がある場合、その受取人固有の財産と見なされるため、通常、相続財産には含まれません。
ここでは、相続財産に含まれるものと含まれないものについて、具体例を交えて解説していきます。
1.相続財産に含まれるもの

これには、不動産、現金、金融資産、契約上の権利など、さまざまな種類の財産が含まれます。具体的には、次のようなものが相続財産に該当します。
① 不動産:土地・建物の所有権は、相続財産に含まれます。
・不動産の所有権は登記簿で確認できます。法務局で取得し名義が被相続人のものであるかを確認しましょう。
② 動 産:現金・預貯金・自動車・家財道具・貴金属等の所有権。
・通帳や自動車登録証明書、貴金属の所有証明書などで確認できます。銀行や金融機関から残高証明書を取得することも有効です。
③ 債 権:株式・売掛金・賃金・賃借債権・土地建物の賃借権など。
・株式などの金融資産は証券会社や銀行に問い合わせることで確認。売掛金は未払いの請求書や契約書などから確認できます。
④ 無形財産権:特許権・商標権・意匠権・著作権等。
・特許庁や商標登録機関で登録内容を確認することができます。著作権は文化庁での登録情報をもとに調べることが可能です。
⑤ 契約上の地位:契約上の権利や義務。
・契約書を確認し、相続人が契約上の地位を引き継ぐことができるかどうかを調べます。
⑥ 債 務:借金・未払金・買掛金・損害賠償の支払い等・・・
・借入契約書や未払金の請求書を確認し、負債額を把握します。
一般的には、不動産・預貯金・有価証券・自動車等の相続が多いかと思いますが、注意したいのは借金等も相続財産に含まれますので、相続財産総額で負債が多い場合は、相続放棄を検討しましょう。なお、相続放棄は、相続があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。
2.相続財産に含まれないもの
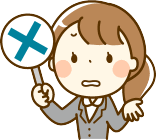
相続財産に含まれないものとして、以下のものがあります。これらは通常、相続財産として扱われないものになります。
① 身元保証等の保証期間に制限のない保証債務
・期間が無制限で責任が不確定な保証は、相続財産には該当しません。
② 年金受給権・死亡退職金・香典等・・
・これらは受取人の固有の財産として相続財産には含まれません。但し、相続財産に含まれないものでも経済効果が認められる死亡退職金等は、みなし相続財産として相続税が課せらることになります。
みなし相続財産(例)
みなし相続財産とは、相続財産に含まれないが相続税申告の際には、その財産額も含まれるものを言います。以下に、みなし相続財産に該当する例を挙げます。
・故人が保険料を負担していた生命保険(死亡保険金)
・死亡退職金
・相続開始前7年(3年)以内の贈与
・故人から生前、相続時精算課税の適用を受けて取得した財産等
生命保険や年金など判断が難しいものがありますので、専門家又は、関係機関に一度ご相談された方が良いかと思います。
3.生命保険金(死亡保険金)と相続財産の関係
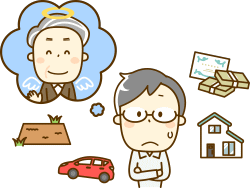
生命保険金は、受取人の指定(本人以外)があれば、その受取人の「固有の財産」となりますので、相続財産には含まれません。(※受取人の指定がない場合は相続財産に含まれます。)又、相続を放棄した場合でも「固有の財産」に該当する場合は、受取可能です。
(1)受取人の違いによるケース
・受取人の指定により固有の財産になるケースと相続財産になるケースがあります。ここでは、各ケースを参考に解説させて頂きます。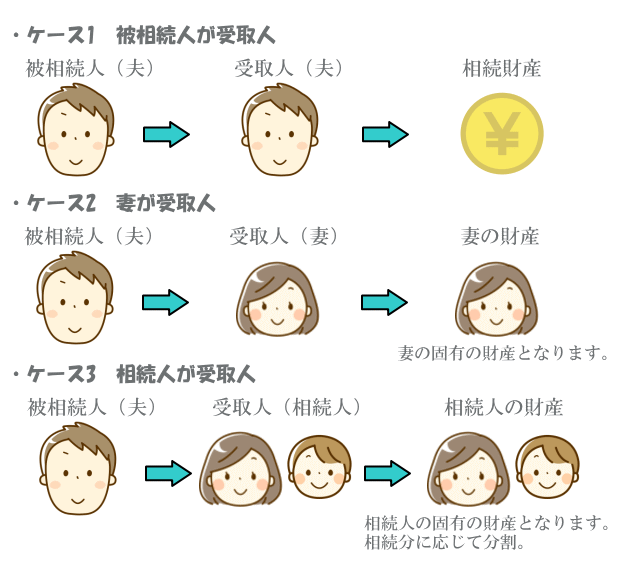
| 被相続人 | 受取人 | 財産の種類 | |
|---|---|---|---|
| ケース1 | 夫 | 夫 | 相続財産 |
| ケース2 | 夫 | 妻 | 妻の固有財産 |
| ケース3 | 夫 | 相続人 | 相続人の固有財産 |
- 受取人の指定がある場合: 生命保険金は、受取人が指定されている場合、その受取人の固有の財産となります。したがって、相続財産には含まれません。
- 受取人の指定がない場合: 受取人が指定されていない場合、生命保険金は相続財産として扱われます。
(2)保険料負担と受取人の違いによる課税対象
・被相続人が保険料を負担していた場合、受取人の固有の財産となり相続税の課税対象になります。しかし保険料の負担者と受取人が異なる場合、課税の対象が異なります。参考例して下記のケースをご覧ください。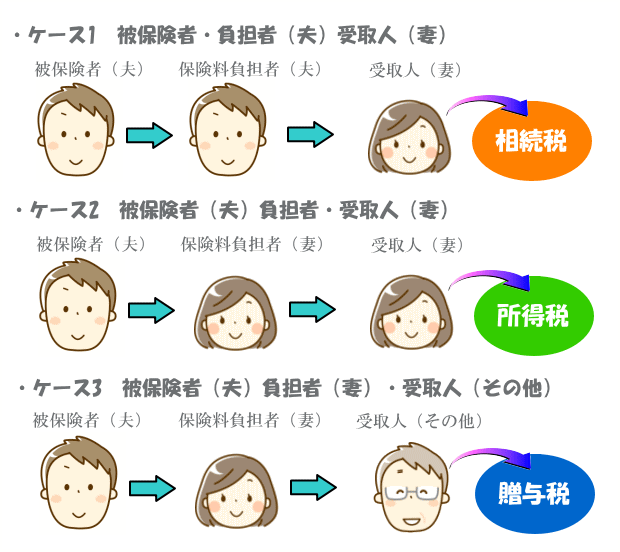
| 被保険者 | 保険料負担者 | 受取人 | 税の種類 | |
|---|---|---|---|---|
| ケース1 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
| ケース2 | 夫 | 妻 | 妻 | 所得税 |
| ケース3 | 夫 | 妻 | その他 | 贈与税 |
生命保険は、保険料負担者・受取人等により相続財産(遺産分割対象)になるか?受取人の固有の財産(遺産分割対象外)になるか?又、どの税目になるのか等、複雑な面があります。遺産分割協議や納税を行う際には、よく確認してから行われた方が良いかと思います。
その他、生命保険の受取人が相続人の1人に指定されていた場合、その受取額が「特別受益」として持ち戻しの計算対象になるのか?問題になる場合がありますが、相続人間によほどの不公平が生じる極端なケースを除き特別受益にあたらないとされています。
つまり受取人に指定されていた相続人は、生命保険の受取と遺産分割による相続財産の受取が可能となります。
(3)生命保険の非課税枠
生命保険金が相続税の課税対象になる場合、「法定相続人数✕500万円」までは非課税とされています。但し、相続人以外の方が受取った場合は、非課税枠の適用がありません。
4.死亡退職金と相続財産の関係
死亡退職金は、在職中に亡くなった社員等の方に会社から支給されるもので、受取人は、通常会社の「支給規定」に定められているため、受取人の固有財産となります。又、死亡退職金にも生命保険同様に「法定相続人数✕500万円」までの非課税枠があります。
※生命保険金と同様に、受取人の指定の有無によって相続財産(遺産分割対象)又は、固有財産(遺産分割対象外)になります。
5.香典・弔慰金と相続財産の関係
香典・弔慰金(会社から遺族に送られる見舞金等)は、相続財産に含まれるのか、ここでは、香典・弔慰金のそれぞれについて解説いたします。
(1)香典
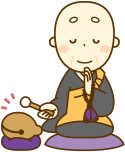 一般的に香典の受取人は喪主であり、香典は葬式費用充てられるものと考えられます。香典から葬式費用を引き、残金がある場合は、祭祀主催者が祭祀費要として受取ることが香典の性質に合うものと考えられます。
一般的に香典の受取人は喪主であり、香典は葬式費用充てられるものと考えられます。香典から葬式費用を引き、残金がある場合は、祭祀主催者が祭祀費要として受取ることが香典の性質に合うものと考えられます。
香典を相続人で分配することも考えられますが、相続財産ではないため、喪主の裁量によるものとなります。(相続人による香典の分割請求権ないと考えられます。)
(2)弔慰金
・弔慰金は、故人と生活を共にしていた人を、援助・慰めの為に送られるものであり、勤務先会社の規定や法律により受取人の範囲が定められています。そのため、相続財産に含まれず、受取人固有の財産となりますので相続人が分割請求する権利もないと考えられます。(但し、受取人=相続人の場合は、特別受益に該当する場合があります。)
6.祭祀財産と相続財産の関係
(1)祭祀財産とは?
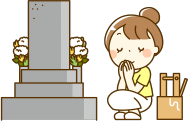
祭祀財産とは、先祖代々の系譜や祭具、②墳墓(お墓)の所有権等になります。祭祀財産は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継(祭祀承継者)し、相続の対象にならないとされています。たとえ高価な墓地・仏壇・仏具を被相続人が所有していても相続人が相続する対象とはされません。
(2)祭祀承継者の指定
祭祀承継者には、被相続人から①「生前に指定された人・遺言で指定された人」がなります。②遺言の指定がない時は、「慣習」に従って決まりますが、この「慣習」が明らかでなく争いがある時は、③家庭裁判所で祭祀承継者を決めることになります。
※祭祀承継者は、相続人以外でもなることが可能です。(特別な付き合いがあった人等)
(3)祭祀財産と相続財産の関係
祭祀財産の承継は 相続とは無関係であり、相続人が祭祀を承継したことによって、相続分が減らされたり、或は、祭祀を営む為の費用を相続財産から控除して取得したり、また相続分が増えたりすることはありません。
7.マイナス財産(借金等)と相続財産の関係
相続財産は、マイナスの財産も含まれます。借金や買掛金、未払税金、医療費、住宅ローンなどの債務が含まれている場合には、プラスの財産だけではなく、これらの財産も引き継ぐことになります。これを「単純承認」といいます。
単純承認では、「プラス」と「マイナス」でマイナスの方が大きい場合は、被相続人に代わって借金だけ支払っていくことにもなりかねません。この様な状況を防ぐ為には、相続があったことを知った時から3ヶ月以内に「相続の放棄」又「は限定承認」を行う必要があります。
基本的には、相続開始から何も行わなければ単純承認となり、「相続の放棄・限定承認」は家庭裁判所に申述する必要があります。
特に、被相続人が事業を営んでいた場合等、負債を抱えている場合もありますので、早めに相続財産調査を行い、負債が明らかに大きい場合は「相続放棄」・どちらかよくわからない場合は「限定承認」を3ヶ月以内に行っておいた方が安心です。
8.保証人と相続財産の関係
民法(896条)では、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」と規定されています。
一身専属的な権利・義務とは「扶養の権利義務」や「子を監護教育する権利」等を指し、これ以外のものは、原則、相続人が相続する事になります。つまり、保証債務も原則、相続財産とされ相続人が相続した場合には、その保証債務を支払う義務があります。
但し、保証契約の中でも、「具体的な債務額の確定していない基本的な身元保証」、「債務の責任限度額及び保証期間を定めないでした保証」については、相続人が予測できない責任を生ずる可能性があることから相続性を有しないとされております。
以上により、相続開始時に「金額が確定されている保証債務」等は、相続されることになり相続人に支払い義務が生じる事になります。
※相続開始時には、どの様な財産があるのか?慎重に調査することが重要です。
9.死亡事故による損害賠償請求権との関係
被相続人が交通事故死して得た損害賠償請求権は、相続財産として扱われます。
交通事故において加害者等に対し、死亡した被害者自身が生きていたら請求するであろう損害の賠償については、基本的に、不法行為に基づく損害賠償請求権という権利となり、相続人が相続することになります。また、被害者の遺族が受けた精神的損害の賠償金を受給できる権利とされる慰謝料請求権も同様に、相続財産として扱われます。
※損害賠償請求権は、相続人が損害や加害者を知ったときから3年間行使しないと時効によって消滅します。不法行為のときから20年を経過したときも消滅します。
※死亡事故のような「不法行為に基づく損害賠償請求権」では、胎児も生まれたものとみなされますので、お腹の子も亡くなった被相続人の損害賠償請求権を相続することはもちろん、固有の慰謝料請求権があります。但し、胎児である今の時点では請求できませんので、生まれた後、法定代理人が代わりに請求することになります。
10.相続放棄で受け取れない財産・受け取れる財産

相続放棄を選択した場合、基本的にその相続人は遺産を受け取る権利を失います。しかし、相続放棄をしても、特定の財産については受け取ることができる場合があります。
この記事では、相続放棄後に受け取れない財産と、逆に受け取れる財産について、生命保険や死亡退職金などを中心に詳しく解説します。
(1)相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に対して相続を放棄する手続きを行うことです。これにより、相続人は遺産だけでなく負債も含め、被相続人の遺産を一切相続しないことになります。相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければならないため、期限を守ることが重要です。
(2)相続放棄で受け取れない財産
相続放棄をした場合、基本的には被相続人の遺産を一切受け取らないことになります。これに該当するのは以下のような財産です。
相続放棄をした場合、遺産分割における現金や不動産、預貯金、株式などの金融資産は一切受け取ることができません。これらの財産は相続人が取得する権利があります。相続放棄は、その権利を放棄したことになります。
相続放棄を行うことで、被相続人が残した負債(住宅ローン、クレジットカードの未払いなど)も相続しないことが確定します。つまり、相続放棄によって負債を免れることが出来ます。相続人の方は相続財産の調査を行い、負債の多い場合は相続放棄をされた方が良いかと思います。
(3)相続放棄でも受け取れる財産
相続放棄をしても、以下のような財産は受け取ることができる場合があります。特に生命保険金や死亡退職金など、特定の契約に基づく財産には、契約内容などを確認する必要があります。
生命保険金は、被相続人が生前に契約した保険に基づく支払いであり、受取人が指定されています。相続放棄を行った場合でも、受取人として指定されている場合には、その生命保険金を受け取ることができます。
死亡退職金は、被相続人が勤めていた会社が死亡後に支払うことが多い一時金です。この死亡退職金は、通常、受取人が指定されており相続財産には含まれません。そのため、相続放棄をした相続人でも、死亡退職金を受け取ることが可能です。死亡退職金の受取人指定は、会社や団体の規定に基づいて決まります。
生前に被相続人から贈与された財産(現金、不動産など)は、相続放棄による影響を受けません。相続財産とは別に扱われるため、相続放棄をしても贈与された財産を受け取ることができます。
但し、以下のような注意点があります。
- 債権者を害する目的で行われた生前贈与は、民法の規定により取消しの対象となる可能性があります。(詐害行為取消し権)
- 生前贈与であっても、相続開始前7年(3年)以内の贈与は相続税の課税対象になります。
その他、遺留分を侵害している場合、生前贈与された財産が遺留分侵害額請求の対象 となることがあります。特別受益に該当する場合や、相続開始前 1年以内の贈与 は、他の相続人から請求を受ける可能性があります。
相続放棄を行った場合でも、未支給年金や遺族年金、労災保険の遺族補償給付など、一部の給付金や年金については受け取ることができます。
 ・相続放棄をすると、基本的には遺産を受け取ることはできませんが、生命保険金や死亡退職金など、特定の契約に基づく財産については受け取ることができるものがあります。相続放棄をする際は、どの財産が受け取れるのか、受け取れないのかをしっかりと理解し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。
・相続放棄をすると、基本的には遺産を受け取ることはできませんが、生命保険金や死亡退職金など、特定の契約に基づく財産については受け取ることができるものがあります。相続放棄をする際は、どの財産が受け取れるのか、受け取れないのかをしっかりと理解し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。
11.相続財産とは?含まれるもの・含まれないもの まとめ

ここまでご覧頂きまして、有難うございました。このページでは、相続財産になるもの、ならないものなどについて、まとめさせて頂きました。この様なことを把握することは、相続財産の分配を行う際の遺産分割協議にも参考になるかと思います。また、相続を放棄した場合も受取れる財産もありますので、こちらも参考にして頂ければ幸いです。
当事務所は、葛飾区の行政書士事務所になります。平成21年度開業で、これまで遺言書、相続に関するご相談から手続代行などのご依頼を頂いております。もし、遺言書の作成や相続手続などでご不明点がありましたら、お気軽に当事務所にご相談下さい。
お客様のお話をお聞きした上でアドバイスををさせて頂きます。相談だけでも大丈夫です。
»» 次の記事:相続放棄・相続排除・相続欠格とは? »»
«« 前の記事:遺留分とは?遺留分侵害額請求権とは? ««
(
大塚法務行政書士事務所 大塚博幸

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)