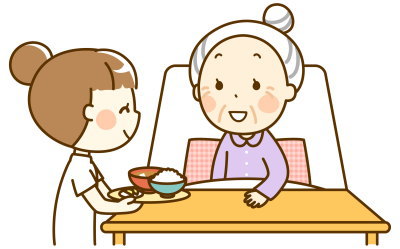遺産相続が発生すると、相続人の間で遺産をどのように分割するかを決める必要があります。これを「遺産分割」と呼びます。相続の手続きには様々な法的ルールがあり、正しく理解しなければトラブルに発展する可能性があります。
本記事では、「遺産分割とは何か?」という基本的な解説から、具体的な遺産分割の方法、協議を行う前に知っておくべきことまで詳しく解説します。
相続が発生し、遺産分割をスムーズに進めるための参考にしてください。
1.遺産分割とは?
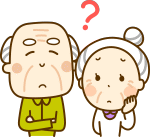
遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた財産を、相続人が分けるための手続きです。被相続人の財産は、相続が開始した時点で法定相続人の共有財産となります。しかし、このままでは不動産の登記や預貯金の解約・引き出しなどの手続きが困難になります。そのため、相続人全員が合意し、正式な遺産分割を行う必要があります。
遺産分割には以下の方法があります。
被相続人が生前に作成した遺言書に分割方法の指定があれば、その内容に従います。
遺言書がない場合、相続人全員が話し合って分割方法を決めます。
相続人間で協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停や審判により分割方法が決められます。
(1)遺言による分割指定
・被相続人が遺言で遺産の分割方法を指定していたときは、遺言指定がもっとも優先されます。遺言の遺産分割の方法によって分割した際に、法定相続分以下の分配になる相続人が出てくる可能性があります。
この場合、法定相続分との不足分を他の相続人に請求することはできません。ただし、遺留分を侵害しているときは、遺留分の権利がある相続人から取り戻しの請求(遺留分侵害額請求)を行うことができます。
(2)遺産分割協議での分割指定
・遺言書が無い場合、遺言書に分割方法の指定が無い時は、共同相続人の協議で分割方法を決めます。この協議には、「共同相続人全員の参加」と「全員の同意」(必ずしも全員が一同に会する必要はなく、遠隔地の相続人や海外在住の相続人の場合には手紙でも可)が必要となります。
話し合いで共同相続人全員が合意すれば、どの様な分割でも問題ありません。遺言書の内容と違う分割でも、相続人全員が納得すれば法定相続分と違う分割もできます。
(3)家庭裁判所による分割(調停・審判)
・共同相続人の間で協議がまとまらなかったり、共同相続人の協議に参加できない事情があって協議ができないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停申立を行うことができます。さらに家庭裁判所での共同相続人の調停がまとまらないときは、家庭裁判所の審判によって分割方法を決めることになります。
家庭裁判所の調停では、調停委員が中立的な立場で話し合いをサポートします。相続人同士での直接の話し合いが難しい場合でも、第三者を交えて冷静に話し合うことが可能になります。しかし、調停で合意に至らない場合、最終的には裁判官の判断による審判が下されます。
審判に進むと、相続人の希望に関わらず、裁判所が適切と判断した方法で遺産を分割することになるため、できるだけ協議や調停で合意に達することが望ましいでしょう。
(4)遺産分割の重要性
遺産分割が適切に行われないと、相続財産が共有状態のままとなり将来的なトラブルにつながる可能性があります。特に不動産など分割しにくい財産を共有状態のままにしておくと、売却や活用の際に相続人全員の同意が必要となり、手続きが煩雑になります。そのため、早めに適切な手続きを進めることが重要です。
2.遺産分割協議とは?

相続が開始され、相続財産の分割方法が《相続人全員の合意》として決まれば、その内容を記載した書面を作成します。この書面が「遺産分割協議書」です。遺産分割協議書は、後日紛争を防ぐために非常に重要です。相続人全員の合意を証する書面として、不動産や預貯金などの遺産の名義変更に必要な書類となります。
遺産分割協議の成立要件
共同相続人は、いつでも協議を通じて遺産を分割することができます。しかし、遺産分割協議の成立には、相続人全員の参加と合意が必要です。一部の相続人が不参加であったり、その意思を無視して行った場合、その協議は無効となります。
自由な分割方法
遺産分割協議においては、相続人全員の合意により、配分方法や割合を自由に決めることができます。そのため、法定相続分に従う必要はありません。相続人の間で異なる割合で分けることも可能です。
3.遺産分割の方法は?
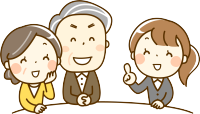
遺産分割を行う際に、土地や建物などのように均等に分けられない財産もあります。この場合、相続人全員が納得できるようにどのように割り振るかが遺産分割の重要なポイントとなります。遺産をどのように分けるかには、主に以下の方法があります。
(1)現物分割
現物分割は、遺産をそのままの形で分割する方法です。例えば、居住している家と土地は長男に、現金や預金は母に、株券や貴金属・宝石は長女に分けるという具合です。この方法は、遺産ごとに取得者が決まるため、比較的簡単に分割できる場合が多いです。
現物分割は、遺産の個々について取得者を決めるため、基本的な方法と言えるでしょう。しかし、土地や建物などの物理的に分けることができない財産がある場合、または相続人間での合意が得られない場合は、他の方法を併用することが必要です。
(2)換価分割
換価分割は、遺産を現金にして、その代金を相続人に分ける方法です。例えば、居住している家と土地を相続する際、その土地や家を売却して代金を相続人で分ける方法が換価分割です。
換価分割は、現物分割で分けにくい場合や、分割後に不公平が生じる場合に有効です。また、現物分割と併用して、相続分の過不足を調整することも可能です。換価することで、現物分割の際に均等に分けられない財産を現金に変換し、公平に分けることができます。特に、不動産や金銭的に換金しづらい財産の処理に役立つ方法です。
(3)代償分割
代償分割は、特定の相続人が相続財産を取得する代わりに、他の相続人に手持ちの現金で不足分を支払う方法です。例えば、長男が家や土地を取得する代わりに、その価値に相当する金額を他の相続人に支払う形で調整します。
代償分割は、特定の相続人が多くの遺産を取得する場合に有効な方法です。しかし、この方法は、支払う側に十分な資力がない場合には適していません。資金不足を補うために、生命保険金や他の資産を活用することも一つの方法です。こうすることで、相続人全員が公平に分けられるよう調整します。
(4)その他の分割方法
その他の分割方法としては、以下のものがあります。
遺産のすべてについて分割を行う方法です。この方法では、遺産を一度に完全に分割するため、スムーズに相続手続きが進みます。
遺産の一部を分割し、残りは未分割のままにする方法です。しかし、一部分割は将来のトラブルを引き起こす可能性が高いため、慎重に決定する必要があります。
遺産を相続人全員の共有財産として分ける方法です。この方法では、将来的に権利関係が複雑になり、管理が煩雑になる可能性があるため、慎重に選択すべきです。
遺産分割には様々な方法がありますが、それぞれの方法には特徴や利点、欠点があります。遺産分割を進めるにあたり、相続人全員が納得できる方法を選ぶことが大切です。現物分割や換価分割では、財産ごとに適した方法を選び、相続人間で十分に話し合いを行うことが必要です。
4.遺産分割協議前に注意すること
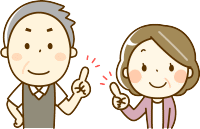
遺産分割協議を行うには、相続人全員の参加が必須です。まずは相続人を確定し、その後、遺産分割対象となる財産を把握することが重要です。
相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍や住民票の除票を取得し、調査を行うことが必要です。これらを基に、遺産分割協議を行う準備を整えておくことが求められます。
(1)相続人の調査
相続人を確定するためには、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得することが基本です。戸籍を順番に取得することで、婚姻歴や子供の有無、養子縁組等、相続人の範囲を再確認することができます。これにより、誰が相続人となるかを明確にし、適切な分割協議を行うことができます。
また、被相続人の死亡年月日・最後の住所地等は、被相続人を特定する事項として、遺産分割協議書に記載しますし、各相続手続きにも必要になりますので、死亡記載の戸籍と併せて住民票の除票も取得しておきましょう。
(2)相続財産の調査
遺産分割の際に、最も重要となるのが相続財産の調査です。具体的にどのような財産があるのかを把握しないと、分割方法やその割合について話し合うことができません。そのため、事前に財産目録(リスト)を作成しておくことが重要です。
財産目録(リスト)の作成方法として、プラス財産・マイナス財産(借金等)を別に記載し、プラスの財産として、土地.建物、預貯金、有価証券等を分けて記載し、マイナスの財産も負債、未払金等分けて記載します。プラス・マイナスの合計をそれぞれ記載し、差引をする事で全体の総額も把握し易くなります。
これにより、相続人全員が公平に分割できるよう、具体的な話し合いを進めやすくなります。
(3)生前に贈与された財産等
遺産分割において、相続人以外の人に贈与された財産や、特定の相続人に生前贈与された財産についても注意が必要です。これらは特別受益として、遺産分割の際に考慮する必要があります。生前贈与された財産については、契約書や銀行の記録などで、贈与が行われたことを確認し、遺産分割協議に反映させる必要があります。
その他、寄与分(故人の財産の維持や増加に貢献)や特別寄与料(故人の親族だが相続人でないものが無償で療養看護等を行った人=相続人に対し請求)、配偶者居住権等、近年の法改正により新たに定められたものもありますので、こちらも、状況に応じて話し合う必要があります。
5.協議の途中で問題が生じた場合の対処方法
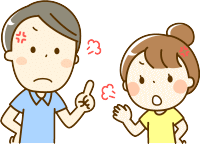
遺産分割協議がスムーズにこともあります。相続人間での意見の不一致や、分割方法に対する理解の違いなどが原因です。こうした場合、どのように問題を解決していくべきかを段階的に解説します。
(1)意見の不一致を解消する方法
相続人間の意見が食い違うことは珍しくありません。協議が進まないとき、以下の方法も検討してみましょう。
感情的にならず、冷静に意見を交換することが重要です。まずは、相続人全員が話し合いの場に出席し、それぞれの意見を述べる機会を設けます。意見交換を通じて、相手の立場や気持ちを理解し合うことが、協議を進める鍵となります。
もし、対話で解決できない場合、弁護士などの専門家に相談することも有効です。専門家は第三者的な立場で意見を述べることが可能ですので、専門家のアドバイスを受けながら協議を進めるのも一つの方法です。
完全な一致を目指すのではなく、双方がある程度納得できる妥協案を見つけることが重要です。例えば、一部の財産を譲歩し合う形で、最終的に合意に達することもあります。
(2)調停前に考えられる方法
調停に進む前に、調整を試みる方法として以下のような方法も考えられます。
親族や友人、または弁護士を立てて、第三者を交えた交渉を行います。この第三者が中立的な立場で双方の意見を調整することで、問題が解決する場合もあります。
意見が対立している場合、直接的な話し合いを避け、各自の希望を文書にまとめて相手に提出します。。お互いの希望が見えることで、意見を冷静に見直すこともできます。時には、相手が譲れない点を明示することで、解決の糸口が見えてくる場合もあります。
(3)相手が協議に参加しない場合
相続人が協議に参加しない場合、まずはその理由を確認します。もし、相続人が意図的に協議に参加しない場合や連絡が取れない場合、家庭裁判所に対して「遺産分割調停」を申し立てることができます。
家庭裁判所に申し立てを行うと裁判所が調停委員を選任し相続人間の調整を行います。相続人間で合意が得られなければ、調停は不成立に終わることもあります。その場合、審判に移行し家庭裁判所が最終的な遺産の分割方法を決定します。この審判による決定は法的効力を持ち、相続人はその分割方法に従わなければならなくなります。
6.行方不明の相続人がいる場合の対処方法

相続手続きにおいて、相続人が行方不明であると、手続きが滞ってしまう可能性があります。しかし、法的手続きにより、行方不明の相続人に適切に対応することができます。この記事では、相続人が行方不明の場合の対処方法を解説します。
(1)相続人の捜索
まず、行方不明の相続人を捜索するために、以下の方法を試みます。
親族や友人、知人に連絡を取って、相続人の行方に関する情報を集めます。
現在では、SNSなどを利用している方も多くおります。ここから相続人に連絡を取る方法も考えられます。
行方不明者の戸籍の附票を取得して、現在の住所地を確認します。住所が特定できましたら連絡をするように手紙等で伝えます。
(2)不在者財産管理人の選任
上記の方法でも行方がわからない場合は、家庭裁判所に申し立てて不在者財産管理人を選任してもらいます。不在者財産管理人は、行方不明の相続人に代わって遺産分割の準備や管理を行うことができます。その他、行方不明が7年以上続いている場合、その相続人に対して失踪宣告の申立てを行うことも考えられます。
相続人が行方不明である場合、まずは相続人の捜索を行い、それでも見つからない場合は、家庭裁判所に申し立てて不在者財産管理人を選任するなどの検討が必要になります。これらの手続きは法律的に複雑な場合もありますので、専門家(弁護士等)に相談しながら進めることをお勧めします。
7.遺産分割協議を行う前に知っておきたいこと まとめ

この記事は、遺産分割を行う前に知っておきたい基礎的な情報をまとめさせて頂きました。遺産分割は、相続人間で円滑に財産を分け合うための重要な手続きです。適切な方法で遺産分割協議を進め、合意を得ることで、後々のトラブルを防ぎ、相続手続きをスムーズに進めることができます。
相続手続には、遺産分割協議書が必要になりますので、協議がまとまりましたら必ず書面で作成してください。口約束では揉める可能性があります。なお、遺産分割協議書の作成に不安がある場合は、お気軽に当事務所にご相談下さい。当事務所では、協議書の作成から相続のご相談、相続手続代行まで相続に関するサポートを行わせて頂いております。
相談無料ですので、安心してお問合せ下さい。
»» 次の記事:遺産分割協議書作成のポイントと遺産分割Q&A! »»
«« 前の記事:相続で必要な各種届出や手続きについてのポイントと流れ ««
大塚法務行政書士事務所 大塚博幸

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)