

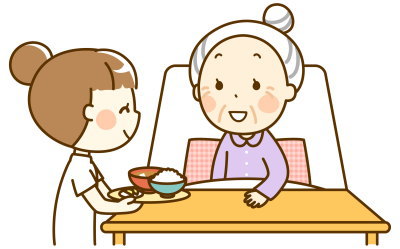
・相続において「寄与分」や「特別の寄与」は、相続財産の公平な分配を考えるうえで重要な概念です。相続は単なる財産の分配ではなく、被相続人(故人)の生前の関係性や貢献度を反映させるべきものでもあります。
そのため、特定の相続人や親族が被相続人の財産の維持・増加に特別に寄与した場合、それを考慮した分配が認められます。しかし、これらの制度について詳しく知らないと、不公平な結果になったり、後々のトラブルにつながる可能性もあります。
本記事では、寄与分と特別の寄与の違いを詳しく解説し、具体的な事例や請求手続きについても紹介します。相続に関する知識を深め、適切な対応を取るための参考にしてください。
1.寄与分とは?(対象:相続人)

「寄与分」とは、被相続人(故人)の財産の維持や増加に特別に貢献した相続人が、法定相続分とは別に加算して受け取ることができる財産のことを指します。これは、民法第904条の2に基づいており、相続人間の公平を保つための制度です。
民法904条の2によると...
共同相続人中に、①被相続人の事業に関する労務の提供、②財産上の給付、③被相続人の療養看護、④その他方法
により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価格から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。と定められております。
結果として、故人の財産が減少せず、又は増加した場合、「特別の寄与」した者は、相続分+寄与分の財産を受取ることが出来るという事になります。
2.寄与分が認められるケース
寄与分が認められるには、以下の要件などを満たす必要があります。
(1)共同相続人であること
寄与分は、共同相続人に限られます。友人・知人等が被相続人の財産の増加・維持に貢献したとしても、寄与分は認められないことになります。例えば、亡くなった親の会社を長年支えてきた息子(相続人)には寄与分が認めらる可能性がありますが、同じように手伝っていた親の友人には寄与分は認められないことになります。
※民法改正により相続人以外の親族は、被相続に人に対する特別の寄与に対し「特別寄与者」として「特別寄与料」が認められる可能性があります。※詳しくは下記「特別の寄与とは?」をご覧ください。
(2)被相続人の財産の増加・維持があること
寄与分が認められるには、①「特別の寄与(特別の貢献)」+②「故人の財産が増加・維持」が必要になります。たとえ特定の時期に多大な貢献をし財産が増加したとしても、相続開始時に財産が残っていなければ寄与分は認めれません。
例えば、ある相続人が被相続人の家業を支え、売上が増加した場合、その貢献が認められ、寄与分として財産を追加で受け取ることができる可能性があります。逆に、相続人が会社の手伝いをしていたものの、その活動が財産に直接結びついていない場合、寄与分が認められる可能性は低いと思われます。
(3)特別の寄与であること・・
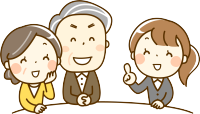
「特別の寄与」が必要になります。ただ単に子が親の面倒を看ていた等、扶養義務の範囲では「特別の寄与」が認められません。親の介護や家業の支援など、通常の範囲を超える特別な貢献があった場合に寄与分が認められる可能性があります。
例えば、子どもが親の介護を長年行い、経済的にも支えた場合、その介護が特別な寄与として認められる可能性があります。ただし、通常の扶養義務の範囲内で行った介護(例えば、月に数回訪問する程度)では、寄与分は認められません。
3.寄与分の計算方法
寄与分の計算は、相続財産に対してどの程度の貢献をしたかを基に行います。寄与分が認められる場合、その金額は相続財産から差し引いて計算され、他の相続人と公平に分けられます。具体的な計算方法を以下に示します。
事例

- 相続財産:1,000万円
- 相続人が①妻(A)・②長男(B)・③次男(C)
- 次男Cの寄与分:200万円
相続財産から次男(C)の寄与分200万円を差し引きます。
・1,000万円-200万円(寄与分)=800万円(みなし相続財産)
みなし相続財産800万円を基に、相続人に対して分配額を計算します。
- 妻(A)の法定相続分=800万円✕1/2=400万円
- 長男(B)の法定相続分=800万円✕1/2✕1/2=200万円
- 次男(C)の法定相続分=800万円✕1/2✕1/2=200万円+200万円(寄与分)=400万円
このように、寄与分が計算に加味されることで、実際に受け取る相続財産の額が増え、相続人の貢献度に応じた分配が行われます。
4.寄与分の請求手続き
相続において、共同相続人が被相続人の財産に特別な貢献をした場合、その貢献を反映させた「寄与分」を請求することができます。しかし、この寄与分に関して相続人同士の協議が進まない場合、家庭裁判所に申立てを行うことになります。ここでは、寄与分の請求手続きの流れや必要な準備について詳しく説明します。
(1)調停手続きの流れ
寄与分を請求するための第一ステップは、家庭裁判所での調停です。この手続きでは、遺産分割と寄与分の問題が同時に扱われることが一般的です。調停は裁判所の中立的な調停委員が進行を担当し、当事者の意見を聴取したり、解決策を提案したりして合意を目指します。
調停手続きは平日に行われ、1回の調停期日は2時間ほどになります。双方は別々に待機し、交互または同時に調停室に入って話し合いが進められます。調停が成立すれば、合意内容に基づいて遺産分割や寄与分が決まりますが、調停が不成立となった場合には次のステップである審判手続きに進むことになります。
(2)審判手続き
調停が不成立になると、審判手続きが開始されます。審判は、裁判官が相続人双方の主張や提出された証拠資料をもとに、法的に判断を下すプロセスです。審判では、裁判官が相続人の主張をもとに、寄与分の有無やその割合を最終的に決定します。
なお、寄与分は①寄与の時期、②寄与の方法、③寄与の程度、④相続財産額等の事情を考慮して定められます。審判の決定は、法的効力を持つため、その結果に従うことが求められます。
(3)寄与分を請求するためにかかる費用
寄与分を請求するには、一定の費用が発生します。具体的には、以下の費用が必要です。
- 収入印紙代:1,200円(申立人1人につき)
- 連絡用郵便切手代:1,020円(82円×10枚、50円×2枚、10円×10枚)※もし遺産分割調停がすでに進行している場合、追加の切手代を納付する必要はありません。
- 弁護士費用(弁護士に依頼する場合)
(4)申立てに必要な書類
寄与分の申立てには、家庭裁判所に提出する書類が必要です。以下が主な提出書類となります。
- 申立書:裁判所提出用1通+相手方全員の人数分(写し)
- 連絡先等の届出書
- 進行に関する照会回答書
- 被相続人との関係を証する戸籍謄本(除籍謄本,改製原戸籍謄本)
- 被相続人の戸籍附票(住民票除票)
- 相続人全員の戸籍謄本,戸籍附票(住民票)
- 寄与分を証明する資料など。
(5)申立先
寄与分の申立は、すでに遺産分割調停が家庭裁判所で進行している場合、その裁判所に申し立てを行うことになります。もし遺産分割調停がまだ始まっていない場合、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てることができます。また、調停・審判に関しては相手方との合意で管轄を決めることも可能です。
(6)寄与分の申立ての注意点
申立てする際には、単に貢献を示すだけではなく、その貢献が実際に被相続人の財産の増加や維持にどれだけ影響を与えたのかを証明することが重要です。証拠となる書類や記録をしっかりと準備し、裁判所に提出することが求められます。
また、調停や審判の手続きは時間がかかることがあります。感情的な対立を避け、冷静に手続きを進めることが大切です。
5.特別の寄与とは?(対象:相続人以外の親族)
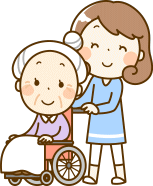
民法改正により、「特別寄与料」を請求できる制度が新設されました。「特別の寄与」とは、被相続人の相続人以外の親族(①配偶者、②6親等内の血族、③3親等内の姻族)が、無償で療養看護(労務提供)を行い、被相続人の財産の維持・増加に貢献した場合に、その貢献に応じた額を相続人に請求できる制度です。
民法1050条の1によると...
「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(特別寄与者)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金額(特別寄与料)の支払いを請求することができる。」と定められております。
特別寄与が認められる一例として、相続人以外の親族が被相続人に対して無償で介護や療養看護を行った場合があります。
例えば、長男の妻が義父を自宅で数年にわたり介護した場合や、兄弟姉妹の一人が親の重病に際して、日常的な世話や看護を無償で行った場合、その貢献が特別寄与として認められることがあります。このような場合、親族が提供した支援や介護が被相続人の生活維持に貢献したと評価され、特別寄与料を相続人に対して請求することも可能です。
6.特別寄与料の請求
特別寄与料の請求については、相続開始後に相続人に対して請求します。特別寄与料の金額等については、特別寄与者と相続人との協議により行います。もし協議が整わない・協議が行えない場合は、家庭裁判所に請求し審判により定められます。
請求先:相続人に対して請求
請求手順:
- 相続人と協議
- 合意できない場合は家庭裁判所に調停・審判の申し立て
- 審判で特別寄与料が決定
家庭裁判所に請求出来る期限は、特別寄与者が①相続の開始、②相続人を知った時から6か月以内、相続開始の時から1年以内になりますので注意が必要です。
(1)相続人との話し合いの進め方
特別寄与料を請求するためには、相続人との協議を行うことが基本です。話し合いの進め方としては、以下のステップを踏むとスムーズに進めやすくなります。
被相続人の財産の維持・増加にどのように貢献したかを相続人に説明します。介護や労務提供の期間や具体的な内容を整理しておくと説得力が増します。具体的には、介護日誌や家業手伝いの記録、関連する領収書などを用意し、どの程度の貢献があったかを示します。
市場価値(例:介護サービスの相場)を参考に、請求額を決定します。請求額の根拠を明確にすることで、相続人との合意を得られやすくなります。
相続人と合意に至った場合は、その内容について合意書等を作成しておきましょう。後々トラブルにならないように、支払い方法や支払期日なども具体的に記載しておきましょう。
(2)調停になった場合の手続き
特別寄与料の請求について、相続人と協議が整わない場合、家庭裁判所で調停を申し立てることができます。調停とは、裁判所が間に入って当事者同士の合意形成を図る手続きです。
特別寄与料を請求するのは、相続人ではない親族であり、被相続人の財産の維持または増加に貢献した者です。例えば、長期間にわたって無償で介護を行った義理の親族などが該当します。相続人や相続放棄をした者、相続欠格事由に該当する者、廃除によって相続権を失った者は申立てを行うことができません。
申立ては、特別寄与者が相続の開始を知った日から6か月以内、または相続開始の日から1年以内に行わなければなりません。期間を過ぎると、申立てができなくなるので、早めに手続きを行うことが重要です。
申立先は、特別寄与料を請求する相手方(相続人)の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所になります。申立人が支払う費用には、収入印紙1,200円(相手方又は被相続人が2人以上の場合は「1200円×人数分)が必要です。また、申立てを行う際には連絡用の郵便切手も必要になります。
- 申立書:裁判所提出用1通+相手方全員の人数分(写し)
- 戸籍謄本:申立人及び相手方
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 特別寄与を証明する書類など
話し合いがまとまらず、調停が不成立となった場合、調停は終了し、次に審判手続きが始まります。審判手続きでは、裁判所が特別寄与料の額を決定します。
7.特別寄与料の計算
特別寄与料は、相続人以外の親族が、被相続人の療養や介護などを無償で提供したことによる貢献に対する報酬です。民法第1050条第4項により、特別寄与料の額は被相続人の相続財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができません。つまり、相続財産がマイナス(借金等)が多い場合や相続財産がない場合には、特別寄与料を請求することはできません。
また、特別寄与料は、相続人に対して請求され、相続人がその負担を負うことになります。相続人が複数人いる場合、各相続人の法定相続分に基づいて負担額が決まります。
事例
 ・相続財産が1,000万円、相続人が①妻(A)・②長男(B)・③次男(C)
・相続財産が1,000万円、相続人が①妻(A)・②長男(B)・③次男(C)
・次男の妻(D)の特別寄与料が100万円とした場合。
まず、相続人の法定相続分を計算します。
- 妻(A):1,000万円 × 1/2 = 500万円
- 長男(B):1,000万円 × 1/2×1/2 = 250万円
- 次男(C):1,000万円 × 1/2×1/2 = 250万円
特別寄与料は相続人が負担しますが、負担割合は各相続人の法定相続分に基づいて決まります。
- 妻(A)の負担額:特別寄与料100万円 × 1/2 = 50万円
- 長男(B)の負担額:特別寄与料100万円 × 1/2 × 1/2 = 25万円
- 次男(C)の負担額:特別寄与料100万円 × 1/2 × 1/2 = 25万円
- 妻(A)=500万円-50万円(負担分)=450万円
- 長男(B)=250万円-25万円(負担分)=225万円
- 次男(C)=250万円-25万円(負担分)=225万円
次男の妻(D)は、特別寄与料100万円を受取。
特別寄与料の計算方法は、相続財産の総額から負担額を決定し、相続人ごとの法定相続分に基づいて、負担額が割り振られます。特別寄与料は、相続人以外の親族が被相続人に対して行った無償の貢献に対する報酬として請求が認められる制度です。
この計算例では、相続財産が1,000万円であり、次男の妻(D)が100万円の特別寄与料を受け取るケースを示しました。相続人は、それぞれ自分の相続分から特別寄与料を負担し、その分が差し引かれる形になります。
8.寄与分と特別寄与者(特別寄与料)の相違点

・寄与分と特別寄与者の共通点として、故人(被相続人)に貢献(特別の寄与)し、結果として故人の財産が維持又は増加されたことが前提になります。また、違いは、「寄与分」が相続人を対象とし、「特別寄与者」は、親族を対象にしております。
さらに、貢献(特別の寄与)の範囲としては
①被相続人の事業に関する労務の提供、②財産上の給付、③被相続人の療養看護、④その他方法となっており
無償で療養看護その他の労務の提供。
・特別寄与者が特別寄与料を請求にするには、
①無償であること。
②療養看護・労務の提供。と限定されいます。
| 寄与分 | 特別寄与者(特別寄与料) | |
|---|---|---|
| 対象者 | 相続人 | 相続人ではない親族(例:配偶者、兄弟姉妹、甥・姪) |
| 貢献の内容 | 事業労務の提供、財産の給付、療養看護、その他の支援 | 無償での療養看護、労務の提供 |
| 請求方法 | 相続分に反映 | 特別寄与料として別途請求 |
| 無償か有償か | 無償・有償問わず | 無償 |
| 主な要件 | 貢献の範囲が広く、相続人間で協議 | 療養看護や労務の提供、相続人ではない親族が対象 |
「寄与分」と「特別寄与者(特別寄与料)」は、相続における貢献が認められる仕組みですが、主な違いはその対象者と貢献の内容です。寄与分は相続人が行った貢献に対して認められるものであり、幅広い貢献が対象となります。一方、特別寄与者は相続権のない親族が行った無償の療養看護や労務提供に対して認められるものです。
特別寄与料を請求する場合は、無償であることが求められ、また貢献内容も療養看護や労務の提供とされています。そのため、特別寄与を申し立てる場合は、申立てを行う際に必要な証拠書類(介護日誌や医療記録など)を準備することが重要です。
9.寄与分と特別の寄与Q&A
寄与分は相続人がい対象になります。特別の寄与は、相続人以外の親族が対象になります。寄与分と特別の寄与は、取得出来る人にも違いがあります。
請求期間も、寄与分が相続開始から10年以内とされ特別の寄与は、相続開始を知った時から6ヶ月以内、相続開始から1年以内と特別の寄与の方が短くなっていますのでご注意ください。
相続人間の話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てを行う事になりますが、その前に親族等に間に入ってもらい話を進める、または、弁護士の相談するなどの方法もあります。
裁判所の申立てについても、司法書士に申立て手続きを依頼し、調停はご自身で進める方法もあります。この場合、司法書士の書類作成費用と申立て費用の実費のみになりますので、弁護士に依頼する場合より費用が安く済む場合があります。
家庭裁判所に相続放棄の申述を行い受理されると、相続人から外れることになります。寄与分は、相続人を対象にしているため、相続放棄後に寄与分のみの請求は認められないことになります。
一方、特別の寄与は、そもそも相続人以外の親族等を対象にしているため、相続放棄とは、直接結びつかないものになります。
①配偶者:例えば妻が義父の看護を行っていた場合などになります。妻は、義父の相続人ではありませんので、特別の寄与者に該当することになります。
②6親等内の血族:「血族」とは、血のつながりのある親族を指します。6親等内の血族とは、直系(親・祖父母・曾祖父母・子・孫・曾孫 など)、兄弟姉妹、叔父・叔母(おじ・おば)、甥・姪(おい・めい)、いとこ などになります。
③3親等内の姻族:配偶者の親(義父・義母)配偶者の兄弟姉妹(義兄・義弟・義姉・義妹)配偶者の祖父母 などになります。このような方が、特別の寄与を請求出来る人に該当します。なお、相続人は特別の寄与を請求出来ませんので、状況に応じて寄与分の請求をすることになります。
寄与分は、相続財産から特別の貢献した人にプラス、他の相続人はマイナスで計算されますので、相続財産全体には影響しませんが、個々の相続人は相続した額により納税額が変わることになります。
一方、特別の寄与は、遺贈として扱われるため、遺贈による相続税が課税されますので、基礎控除額を越える場合は、相続税申告が必要になります。
10.寄与分・特別の寄与 まとめ

・あまり聞きなれない言葉が並び、わかりずらい面もあるかと思いますが、整理しますと寄与分は、療養看護等をしていた相続人が他の相続人より、その労力をプラスして相続財産を貰える権利といえます。これば、労力提供していた相続人を保護し他の相続人との公平を図る制度と言えます。
一方、特別寄与者(特別寄与料)は、これまで、相続人以外の親族が故人の療養看護を行っても、直接保護する制度が無かった為、民法改正により新たに定められました。例えば、義父を看護していた妻がこの法律により、看護等の労力を特別寄与料として相続人に請求できる権利といえます。
当事務所は、平成21年度開業の葛飾区の行政書士事務所になります。遺言書・相続のご相談から遺言書の作成サポート、相続手続の一式代行など幅広い範囲で、お客様のサポートを行わせて頂いております。もし、遺言書、相続に関することで、何か聞いて見たいと思われることがありましたら、お気軽にお問合せ下さい。経験・豊富な事務所ですので安心してご相談下さい。ご相談だけでも大丈夫です。
»» 次の記事:配偶者居住権とは?短期・長期の違いや成立要件、メリットを解説 »»
«« 前の記事:認知症・未成年者がいる場合の相続手続き ««
大塚法務行政書士事務所 大塚博幸

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)

















