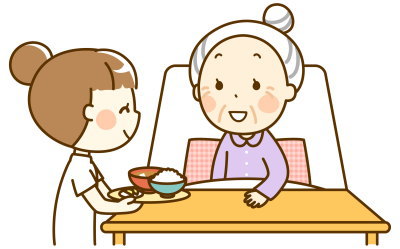・「相続財産を全て特定の相続人に譲る」といった遺言書があった場合でも、その他の相続人が全く財産を受け取れないわけではありません。
亡くなった方の配偶者、子供、両親には「遺留分」と呼ばれる法的権利があり、民法に定められた割合で相続財産を受け取る権利があります。(兄弟姉妹には遺留分がありません。)
この記事では、遺留分の権利を持つ相続人や遺留分の計算方法、また遺留分を侵害された場合に行使できる遺留分侵害額請求権について、わかりやすく解説していきます。
遺留分に関する正しい知識を持つことで、相続時のトラブルを回避することも可能です。
1.遺留分とは?

遺留分とは、被相続人が生前に贈与や遺贈により処分できない一定の割合の財産を指します。これは、相続人が生前に贈与や遺言によって不当な相続財産の分配をされないように守るために定められた制度です。
つまり、遺言書において遺産を特定の相続人に全て譲渡するように記載されていても、他の相続人は遺留分に基づき、一定の金額を受け取ることができる権利を持つことになります。
(1) 遺留分の権利を持つ人
遺留分の権利を有する相続人を「遺留分権利者」と言います。遺留分を持つのは、主に以下の相続人です。
- 配偶者
- 子供(代襲相続人も含む)
- 父母(直系尊属)
なお、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。もし兄弟姉妹が相続人であった場合でも、遺留分は発生しないため、遺言書通りの分配が適用されます。
(2) 遺留分の計算方法
遺留分を計算するためには、まず相続開始時点での被相続人の財産の額を算出し、その後、贈与額や負債などを加減する必要があります。民法1043条に基づき、遺留分算定額は以下のように計算します。
・遺留分算定額 = (相続財産 + 生前贈与額) - 負債額
具体的には、故人が亡くなった時点で所有していた財産(不動産や預金など)に、生前贈与された金額を加算し、負債を差し引いて遺留分を算出します。
重要なのは、相続人以外への贈与は相続開始前の1年間の贈与に限られ、相続人への贈与が特別受益にあたる場合(婚姻・養子縁組など)は相続開始前10年分を遺留分算定に加算します。
民法(参考)
1043条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める
2.遺留分の割合
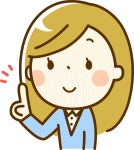
ここで相続人が取得可能な遺留分について解説させて頂きます。遺留分一覧表と各ケースごとの遺留分について下記を参考にして下さい。
(1)遺留分割合一覧表
遺留分の割合は、相続人に相続人によって異なります。まずは下記の一覧表をご覧ください。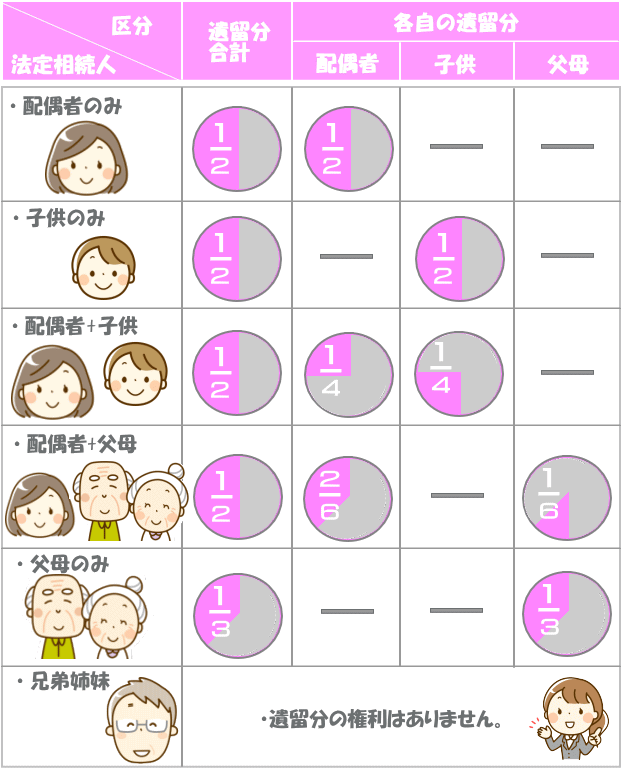
相続人の組み合わせにより遺留分の合計額、各自の遺留分が異なることになります。基本的には、法手相続分の1/2(父母のみ1/3)と考えると把握しやすくなります。
(2)各ケースごとの遺留分割合
遺留分算定額が1,000万円の場合:
・配偶者=1,000万円✕1/2=500万円
※配偶者が唯一の相続人である場合、遺留分はその全額の1/2にあたる500万円です。配偶者は常に遺留分を有します。
遺留分算定額が1,000万円の場合:
- 子供1人=1,000万円✕1/2=500万円
- 子供2人=1,000万円✕1/2✕1/2=250万円(子供1人あたり)
- 子供3人=1,000万円✕1/2✕1/3=166万円(子供1人あたり)
※子供が唯一の相続人の場合、遺留分は1/2です。この1/2の額を子供全員で均等に分け合うため、子供が複数いる場合はそれぞれの受け取る額が分割されます。例えば、子供が3人いる場合、遺留分算定額1,000万円の1/2にあたる500万円を3人で分けるため、1人あたり166万円となります。
遺留分算定額が1,000万円の場合:
- 配偶者=1,000万円✕1/4(1/2✕1/2)=250万円
- 子供1人=1,000万円✕1/4(1/2✕1/2)=250万円
- 子供2人=1,000万円✕1/8(1/2✕1/2✕1/2)=125万円(子供1人あたり)
※配偶者と子供が相続人となる場合、遺留分は1/2です。この額は配偶者と子供に分けられます。配偶者は1/4、残りの1/4を子供たちで均等に分けるため、子供が複数いる場合、各子供はその分を受け取ります。例えば、子供が2人いる場合、それぞれが125万円を受け取ることになります。
遺留分算定額が1,000万円の場合:
- 配偶者=1,000万円✕2/6(1/2✕2/3)=330万円
- 両親(1人)=1,000万円✕1/6(1/2✕1/3)=166万円
- 両親(2人)=1,000万円✕1/12(1/2✕1/3✕1/2)=83万円(両親1人あたり)
※配偶者と父母が相続人の場合、遺留分は1/2にあたりますが、遺留分の配分は少し複雑です。配偶者は2/6、父母(直系尊属)は残りの4/6を分け合います。この場合、父母がどちらか1人であれば1/6を受け取りますが、2人ならその額は半分ずつになります。たとえば、両親が2人の場合は、1人あたり83万円となります。
遺留分算定額が1,000万円の場合:
- 両親1人=1千万円✕1/3=330万円
- 両親2人=1千万円✕1/6(1/3✕1/2)=166万円
※父母のみが相続人である場合、遺留分は1/3にあたります。この額は父母で均等に分け合い、両親が1人であれば1/3を受け取ることになりますが、両親が2人であれば、その遺留分を1/6ずつ分けます(1人あたり166万円を受け取り)。
兄弟姉妹には遺留分権利がありません。このため、兄弟姉妹が唯一の相続人であった場合、遺言書に基づいて遺産が分配されます。もし遺言書が存在しない場合には、民法に基づいた法定相続分によって財産が分割されますが、遺留分を巡る問題は発生しません。
民法(参考)
1042条1項 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
3.遺留分侵害額請求とは?

遺留分権利者が自分の遺留分を侵害されている場合、権利を回復するために「遺留分侵害額請求」を行うことができます。この請求は、遺留分を侵害された金額の支払いを相手に求めるものです。
(1)遺留分侵害額請求権の行使
遺留分侵害額請求権は、生前贈与や遺贈が遺留分を侵害していると認められる場合に行使されます。この請求を行うには、まず受遺者や受贈者に対して通知をする必要があります。通知は通常、内容証明郵便を利用して行います。
令和〇年〇月〇日
東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号
〇〇太郎 殿
東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号
〇〇花子 ㊞
遺留分侵害額請求書
亡父〇〇 〇〇は、令和〇年〇月〇日付公正証書遺言により、長男の貴殿に財産の全てを相続させることを知りました。しかし、上記遺言は、私の遺留分を侵害するものでありますので貴殿に対し遺留分侵害額請求をいたします。
※参考例になります。その他、必要事項の追記等を行って下さい。
(2)遺留分侵害額請求権の期限
遺留分の侵害額請求権は、遺留分権利者が相続開始、或は自分の遺留分を侵害する(贈与・遺贈等)行為があったことを知った時から1年を経過すると時効により消滅します。又、自分の遺留分を侵害する行為があったことを知らなかった時でも、相続開始から10年を経過すると消滅します。
(3) 遺留分で揉めない為には?
故人の意思により遺言書は作成されますが、ご自身が亡くなった後に相続人同士の争いが起きそうな場合は、遺言書の作成をお勧めしております。遺言書の作成時に、遺留分を考慮した上で作成しておけば、後々の争いを未然に防ぐことになります。
遺留分を考慮した遺言書の作成には、ご自身の遺産がどれくらになるのか?大まかに把握しておく必要があります。土地・建物の不動産、銀行の預貯金・有価証券、その他負債等。これらの財産額に対し遺留分権利者の割合を考慮して遺言書を作成しておきましょう。中には評価が難しいものもありますが、その場合は専門家にご相談された方が良いかと思います。
その他、遺留分で揉めない方法としては、相続人に遺留分を放棄してもらう方法もあります。但し、相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が必要になります。家庭裁判所は、①遺留分放棄が自由意思によりされたのか?、②放棄の必要性・合理性の有無、③放棄の代償の有無等を考慮して判断することになります。
4.遺留分侵害額請求の流れと解説
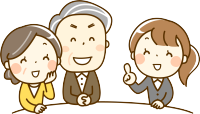
遺留分とは、法定相続人が最低限確保できる遺産の割合を指します。遺言によって特定の相続人や第三者に多くの財産が渡った場合でも、遺留分が侵害されていれば請求が可能です。ここでは、遺留分侵害額請求の具体的な手続きの流れを詳しく解説します。
(1)遺留分侵害の有無を確認する
遺留分侵害額請求を行うためには、まず自分の遺留分が侵害されているかどうかを確認する必要があります。
直系尊属(父母や祖父母)のみが相続人の場合、遺留分は 1/3 、配偶者や子どもなどが相続人の場合、遺留分は 1/2 です。この遺留分割合に基づいて、遺留分が侵害されているか確認することになります。
相続財産には、預貯金、不動産、株式など、あらゆる財産が含まれます。遺産総額をしっかり把握することが重要です。遺言書がある場合は、誰がどれだけ相続しているのかも確認します。
複雑な場合は、弁護士や税理士に相談して、法的なアドバイスを受けることが望ましいです。
(2)遺留分侵害額の確認
遺留分侵害額請求を行うには、侵害額を計算し、請求できる金額を明確にする必要があります。
- 遺留分 = (相続財産の総額 -相続債務)× 遺留分割合
例)相続財産が1,000万円、遺留分が1/2の場合、遺留分は500万円となります。もし遺留分500万円に対し実際に受け取った額が300万円なら、侵害額は200万円となります
(3)遺留分侵害額請求の通知を送る
遺留分侵害額が確定したら、相手方に対して請求の意思を伝えます。この請求は確実に届いたことを証明する為にも、内容証明郵便で送ることをお勧めします。なお、文書を送る際には冷静に、感情的にならずに記載することが大切です。
この段階で相手が支払いに同意すれば、合意書など作成し支払い方法も記載しておきましょう。もしご自身で行うことに不安がある場合は、早めに弁護士に相談し法的なアドバイスを受けましょう。
(4)交渉(任意の話し合い)
遺留分侵害額の請求をした後、相手と交渉を行い、金額や支払い方法について話し合います。交渉で合意で達した場合は、合意書などを作成して後のトラブルを防ぐことが重要です。もし、話し合いで合意が得られなければ、調停なども視野に入れておく必要があります。
(5)家庭裁判所で調停を申し立てる(交渉が不成立の場合)
交渉が不成立だった場合、家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停を申し立てを行います。調停は裁判所が間に入り、話し合いが進められます。調停で合意に達すると、正式な合意書が作成され終了となりますが合意できない場合は、訴訟に進むことになります。
(6)遺留分侵害額請求の注意点
遺留分侵害額請求権は、相遺留分侵害額請求権は、相続開始を知った日から 1年以内 に行使しないと時効で消滅します。交渉が難航したり法的な判断が必要な場合、早めに弁護士に相談することが重要です。
5.遺留分侵害の対策として考えられることは?

遺留分で揉めない様にするためには、どのような方法が考えられるか?遺言書のお願いする方法や生前贈与、遺留分の放棄について解説させて頂きます。参考にご覧下さい。
(1)遺言書(付言)
遺言書の作成する際に、付言事項として他の相続人に遺留分を請求しないよう記載しておきます。但し、法的効果はなく、あくまでもお願いする範囲に留まります。なぜ、その様にしたいのか理由も付言に書いておくことで、相続の理解を得られる場合もあります。
また、後で相続争いにならない様に、事前に家族間で良く話あっておくことも大切です。
(2)生前贈与
少しでも相続財産を減らす為、生前贈与という方法も考えられます。但し、生前贈与は、相続開始前の10年間(相続人)、または1年間(相続人以外)にしたものは、遺留分算定の財産額に加える必要があります(相続人の場合は、特別受益に限る)。そして、遺留分の侵害があることを知って行った贈与は、期限が限定されないことになります。
その他、贈与税等の問題も発生する場合がありますので、もし、生前贈与で行う場合は、早めに税理士等の専門家に相談する方が良いかと思います。
民法(参考)
第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
(3)遺留分の放棄
遺留分を有する相続人に、あらかじめ相続放棄をしてもらう方法になります。家庭裁判所に許可を得て行う必要がありますが、相続人の理解が得られている場合は、遺留分で揉めない一つの方法として考えられます。なお、遺留分放棄の許可申立てには、下記の書類等が必要になります。
- 申立書(裁判所所定の様式)
- 被相続人の戸籍謄本
- 申立人の戸籍謄本など
この申立は、財産を残す人(被相続人)が存命中に行うことができます。
6.遺留分・遺留分侵害額請求権 まとめ

遺留分は、特定の相続人が最低限確保できる権利として法律で定められています。配偶者・子供・直系尊属(父母など)が遺留分を持ち、兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分の計算方法や割合を理解することで、相続時のトラブルを防ぎ、円滑な遺産分割が可能になります。万が一、遺留分が侵害された場合には「遺留分侵害額請求」を行うことで、自分の権利を主張できます。ただし、この請求には期限があるため、早めの対応が必要です。
遺言書を作成する場合には、遺留分を考慮したうえで、財産の分配を決める様にしましょう。もし、不安がある場合は、当事務所にご相談頂ければアドバイスをさせて頂きます。
当事務所は、葛飾区の行政書士事務所にです。平成21年度開業で、これまで遺言書の作成、相続手続に関するご相談を、ご依頼を頂いております。経験豊富な事務所ですので安心してご相談下さい。ご相談だけでも大丈夫です。
»» 次の記事:相続財産とは?含まれるのもの・含まれないもの »»
«« 前の記事:遺産分割協議書作成のポイントと遺産分割Q&A ««
大塚法務行政書士事務所 大塚博幸

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)