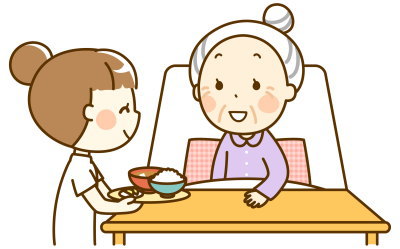・遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合い、遺産の分け方を決定した内容を正式な書面にまとめたものです。
この書面を作成することで、後々のトラブルを防ぎ、相続手続きを円滑に進めることができます。また、不動産の名義変更や銀行口座の相続手続きなどにも必要となります。
このページは、遺産分割協議書の作成方法と遺産分割に関するQ&Aをまとめております。作成方法では、綴じ方や署名押印の方法も解説しておりますので、是非ご覧ください。
- 1.遺産分割協議の基本
- 2. 遺産分割協議書作成のポイント
- 3.遺産分割協議書の作成例
- 4.遺産分割Q&A
- Q1.遺産分割のやり直しは出来る?
- Q2.遺産分割が金銭のみの場合は?
- Q3.分割後の銀行手続は?
- Q4.一方的な遺産分割に従いたくない場合は?
- Q5.協議の成立後に遺言書が出てきた場合
- Q6.協議の成立後に隠し子が現れたときは?
- Q7.遺産分割協議が まとまらない場合は?
- Q8. 遺産分割における「遺留分」とは?
- Q9.遺産分割での「寄与分」とは?
- Q10.相続人が一人の場合、遺産分割は?
- Q11.遺産分割で配偶者居住権を設定は?
- Q12.未成年の相続人がいる場合、遺産分割協議は?
- Q13. 相続を放棄した人がいる場合、遺産分割の影響は?
- Q14.使途不明金がある場合、遺産分割はどうする?
- Q15.代償分割・換価分割とは、どの様な方法ですか?
- 5.遺産分割協議書作成のポイントとQ&A まとめ
1.遺産分割協議の基本

遺産分割協議は、原則として相続人全員の合意が必要です。話し合いがまとまったら、書面に残すことで証拠となり、将来の争いを防ぐことができます。
- 相続人の確定 ⇒ 被相続人の戸籍を遡り、全ての相続人を確認します。
- 遺産の把握 ⇒ 不動産、預貯金、有価証券、負債など、相続財産の全容を明らかにします。
- 遺産分割方法の協議 ⇒ 誰が何を相続するか話し合い、合意形成を行います。
- 遺産分割協議書の作成 ⇒ 合意内容を文書化し、相続人全員が署名・押印します。
- 必要書類の準備と手続き ⇒ 不動産登記や金融機関での相続手続きを行います。
2. 遺産分割協議書作成のポイント

遺産分割協議は、通例では、相続人全員が一同に会して行われますが、遠方の相続人がいる場合等は、電話や手紙などを使用して協議を進める方法もあります。
その場合、協議書の署名押印は?という事になりますが、相続人数分を作成した協議書を郵送等にて持ち回りで署名・押印する方法や同一内容を遺産分割協議証明書として作成し、各自が署名・押印するなどの方法もあります。
(1)遺産分割協議書作成の準備
遺産分割協議書の作成には、一般的に A4サイズの用紙 を使用します。ワープロで作成する場合、縦書き、横書きどちらでも問題ありませんが、一般的には、横書き で作成されています。
タイトルには「遺産分割協議書」と記載し、相続人情報や遺産の内容を詳細に記載できるレイアウトを選びます。
見やすさを重視し、10.5pt〜12ptのフォントサイズを使用します。一般的には MS明朝 や MSゴシック といった標準的なフォントが推奨されます。
(2)署名・押印の詳細
遺産分割協議書は、相続人全員の署名と実印を押印することが基本です。実印を押印した遺産分割協議書を印鑑証明書と合せて、相続手続に使用することになります。
各相続人が自筆で署名を行います。代筆や代理人による署名は認められていません。住所は、印鑑証明書に記載されている住所の通り記載します。
署名の後に 実印 を押すことが必要です。実印は、印鑑登録されたものを使用し、印鑑証明書と合わせて手続きを行います。相続人の方に未成年者・又は重度の認知症の方等がいる場合は、法定代理人等による署名・押印が必要です。
(3)遺産分割協議書の綴じ方
遺産分割協議書が複数ページにわたる場合の綴じ方にも注意が必要です。以下の方法でページをまとめることが一般的です。
遺産分割協議書が複数枚になる場合、ホチキスで2箇所程度止め、その後 契印 を押します。契印とは、各ページを接する部分に押印し、ページが変更されていないことを証明するための印です。
もし枚数が多い場合は、製本テープを使って協議書をまとめる方法もあります。この場合、表紙と裏表紙、および接するページの箇所に契印を押すことをお勧めします。
(4)実印や印鑑証明書について
遺産分割協議書の作成時には、実印 と 印鑑証明書 が必要となります。銀行手続きや公的手続きで有効にするため、まだ実印を登録していない場合は、この機会に実印を作成して印鑑登録をすることが勧められます。
3.遺産分割協議書の作成例
遺産分割協議証書
令和〇〇年〇月〇日 〇〇〇〇の死亡により開始した相続に関し、共同相続人 〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇は、民法908条に基づく遺言による分割の指定及び禁止のないことを確認したうえで、〇〇〇〇の遺産を協議により下記のとおり分割する。尚、本協議に参加した者の他に相続人は存在しない。
※誰がいつ亡くなったのか、相続人は誰か明確に記載します。相続人全員の協議が行われていない場合は、無効になります。
被相続人の最後の本籍 東京都 葛飾区〇〇 〇丁目〇番地〇
最後の住所 東京都 葛飾区〇〇 〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇
生年月日 昭和〇〇年 〇月 〇〇日
相続開始の日 令和 〇年〇月〇〇日
※被相続人(故人)を特定する為、上記のように記載します。
第1条 次の不動産は相続人〇〇〇〇が取得する。
1 不動産
(1)土地
所在 東京都 葛飾区〇〇 〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇 〇.〇〇平方メートル
(2)建物
所在 東京都 葛飾区〇〇 〇丁目 〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階〇〇.〇〇平方メートル 2階〇〇.〇〇平方メートル
※不動産については登記簿謄本を取得して間違いの無いよう記載します。
第2条 現金及び次の預貯金は相続人 〇〇〇〇、〇〇〇〇が2分の1ずつ取得する。
①〇〇銀行 〇〇支店 普通・口座番号〇〇〇〇〇〇〇
②〇〇銀行 〇〇支店 普通・口座番号〇〇〇〇〇〇〇
※預貯金・有価証券等の財産を特定できる様に記載します。
第3条 家財道具その他の動産で被相続人の所有に係わる一切の物は、相続人〇〇〇〇が取得する
第4条 被相続人の全ての債務(葬式費用の負担含む。)は相続人〇〇〇〇が承継する。
第5条 前各条により分割した遺産以外の財産及び将来発見されるべき財産については、相続人全員により別途協議をおこなうこととする。
※後から財産が発見された場合、どの様に分配するか記載しておきます。
以上のとおり協議が真正に成立したことを証するため、この協議書を3通作成し署名押印のうえ各自1通ずつ保管する。
※基本的には、相続人の人数分作成しますが、相続人が多い場合は、正副作成し代表者が保管する方法も考えられます。
令和 年 月 日
※協議が成立した日
相 続 人
住所:
氏名: ㊞
相 続 人
住所:
氏名: ㊞
相 続 人
住所:
氏名: ㊞
※相続人全員が自署捺印する必要があります。
※上記は参考例になります。実際に遺産分割協議書を作成される場合は、財産の内容、状況に合わせた遺産分割協議書を作成してください。もし、作成に不安がある場合は、当事務所にお気軽に問合せ下さい。
4.遺産分割Q&A
・ここでは、遺産分割に関連する問題をQ&A型式にて掲載致します。
Q1.遺産分割のやり直しは出来る?

遺産分割協議の内容に納得出来ません。もう一度やり直し出来ますか?

遺産分割協議は、相続人全員の合意により成立します。一度、成立すれば効力が生じ 無効や取消の原因がない限り 原則としてやり直しすることは出来ません。
遺産分割協議で相続人の1人が不動産を取得する代わりに、別の相続人に代償金を支払う。と約束していたのに、中々、履行してくれない。という様な場合であっても、遺産分割協議を解除して、やり直しを求めることは出来ないとされています。この場合は、調停や訴訟で実現を求めることになります。
遺産が後に新しく出てきた場合は、その遺産について新たに協議をする事になります。但し、漏れていた財産が、一部の相続人に隠匿されたものであったり、遺産全体の中で大部分を占めるときは、従前の遺産分割協議の無効を主張することができます。

一度 成立した遺産分割協議は、原則として解除できませんが、相続人全員の合意があれば、先の遺産分割協議を解除し、新たに遺産分割協議をすることができます。
Q2.遺産分割が金銭のみの場合は?

遺産が現金と預貯金だけですが、この場合 遺産分割は どうなりますか?

最高裁の判例では、遺産が金銭だけの場合においては、相続が開始と同時に、共同相続人は、遺産を協議等により分割するまでもなく法定相続分によって相続するという判例がありました。
しかし近年、判例の変更が行われ、当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象になると判示されました。
相続財産が金銭のみの場合、遺産分割協議は、特に必要なく、各相続人が直接、自己の相続分を金融機関等に請求すること出来ると考えられていました。
しかし、今回の判例変更により、金融機関等に請求する場合は、遺言書、遺言書がない場合は相続人全員の同意を示す書面(遺産分割協議書・銀行所定の用紙等)が必要と考えられます。
Q3.分割後の銀行手続は?

遺産分割協議の銀行手続はどうすれば良いの?

金融機関では、預貯金者の死亡を確認すると口座を閉鎖することになります。その為、相続人が預貯金を相続した場合は、名義変更、または払い戻しの請求が必要となります。
請求する際には、①相続人全員の実印、②印鑑証明書、③被相続人と相続人の戸籍謄本、④その他、銀行側に用意してある書類に全員が実印の押印などの手続等が必要になります。
相続人全員が手続きできない場合は、あらかじめ、金融機関に相談しておく必要があります。その他、葬儀費用・当面費用等が必要な為、事前にお金を引出す場合が有りますが、このお金は、相続財産に含まれますので注意が必要です。
Q4.一方的な遺産分割に従いたくない場合は?

一方的に送られてきた遺産分割協議案に対して、内容に納得できません。どうすれば良いですか?

内容に納得できなければ、まずは説明を求めましょう。又、財産目録を きちんと示してもらい、生前贈与や寄与分の問題があれば、その説明もしてもらいます。
基本的には、法定相続分に従って協議を進めることを要求してください。
不動産や預貯金など遺産の種類が複数ある場合、まとめて法定相続というより、不動産は誰、預貯金は誰とした方が分けやすいでしょう。
もし、相続人の間で話がまとまらなければ、亡くなった方の「最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に遺産分割協議の調停を申し立ててください。相手が弁護士を立てない限り立ない限り、出来るだけ相続人の間で話をしていきましょう。
Q5.協議の成立後に遺言書が出てきた場合

遺産分割協議後に遺言が見つかりました。どうすれば?

遺言書は開封せずに、家庭裁判所で検認手続をしてください。遺言書の内容が有効なものであれば、その内容が優先しますので、成立した遺産分割協議の内容は無効となります。
但し、遺言書の内容を明確に理解した全員の同意があれば、遺言書と違う遺産分割協議の内容であっても有効となります。もし相続人の中に1人でも遺言書の内容をもとに、遺産分割協議の内容に異議が出た場合には、遺産分割をやり直すこととなります。
Q6.協議の成立後に隠し子が現れたときは?

隠し子がいることがわまりました。どうすれば良いでしょう?

戸籍等により認知の事実が判明したときは、その隠し子は 相続権を得ることになります。
その場合、遺産分割協議はやり直しになりますが、遺産分割協議は既に終了しているので、隠し子は 相続分を金銭の支払いで求め、各相続人から支払いを受けることになります。
Q7.遺産分割協議が まとまらない場合は?

みんな自分勝手な意見を言って協議がまとまりません。どうするの?

相続人間で話合いが、まとまらない場合、家庭裁判所に調停・審判の申立てを行い、解決をゆだねる事になります。
相続税申告の必要がある時は、申告期限(相続開始から10ヶ月以内))に仮申告(法定相続分)と納税を行い、遺産分割の決定後に修正申告をします。
Q8. 遺産分割における「遺留分」とは?

遺産分割で「遺留分」という話がでてきましたが、なんのことですか?

遺留分とは、法定相続人に対して法律上保障された最低限の相続分のことです。
遺言書で相続分が指定されていても、遺留分を侵害する内容の場合、その相続人は遺留分侵害額請求を行うことができます。例えば、子どもが相続人の場合、法定相続分の1/2が遺留分として保障されます。
・遺留分とは?遺留分侵害額請求権とは?相続の権利について解説
Q9.遺産分割での「寄与分」とは?

寄与分とは何ですか?どういった場合に適用されますか?

寄与分とは、労務の提供、財産上の給付、療養看護などにより、故人の財産の維持や増加について貢献した人が、相続財産+寄与分を受取ることが出来ます。
寄与分は相続人が+で取得できる財産になりますが、相続人以外の親族(6親等内の血族、3親等以内の姻族)が無償で故人の療養看護等を行い、財産の維持等に貢献した方は「特別寄与料」を請求出来ます。
Q10.相続人が一人の場合、遺産分割は?

相続人が一人しかいない場合、遺産分割はどう進められますか?

相続人が一人の場合、その人物がすべての遺産を相続することになります。
相続人が1人の場合、遺産分割協議が不要となります。従って遺産分割協議書書を作成する必要もありません。但し、相続手続を行う際に、相続人が1人であることを証明する必要がありますので、故人の出生から死亡までの戸籍などを取得する必要があります。
なお、相続人1人の場合は、基礎控除額3000万円+600万円(相続人1人)=3600万円を超える相続財産がある場合は、相続税申告が必要になりますので、ご注意ください。
Q11.遺産分割で配偶者居住権を設定は?

遺産分割協議で配偶者居住権を設定することはできますか?

はい、できます。配偶者居住権は、遺産分割協議や遺言によって設定することが可能です。
配偶者居住権とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた自宅に、残された配偶者が一定期間または終身にわたって住み続けることができる権利です。民法改正で新設された制度で、主に以下のような場合に活用されます。
- 相続財産が自宅しかなく、配偶者が住み続けたいが、不動産を単独で相続すると他の相続人の取り分がなくなってしまう場合。
- 配偶者の老後の住居を確保しつつ、他の相続人との遺産分割のバランスを取る必要がある場合。
配偶者居住権は、遺言や遺産分割協議によって設定することができます。また、家庭裁判所の審判で認められることもあります。
Q12.未成年の相続人がいる場合、遺産分割協議は?

相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割協議はどうすればいいですか?

未成年者は 単独で遺産分割協議に参加することができません。
相続人が未成年者の場合、通常は 親権者が代理 しますが、親も相続人に含まれる場合(例えば、母と子が相続人になるケース)には、利益相反 となるため、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。
特別代理人が選任されると、その代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議を進めます。
Q13. 相続を放棄した人がいる場合、遺産分割の影響は?

相続人の1人が相続放棄をした場合、遺産分割はどうなりますか?

相続放棄をすると、その人は 最初から相続人ではなかったことになります。 そのため、遺産分割協議には参加しません。
相続放棄があった場合、遺産分割は残りの相続人で行うことになります。例えば、相続人が故人の妻(配偶者)と子2人(長男・次男)の場合に、長男が相続放棄をした場合、妻と次男で遺産分割協議を行うことになります。長男に子がいる場合も、長男が相続放棄すると、子も相続人になりません。(代襲相続は行われません。)
もし、妻と子2人の全員が相続放棄すると、相続権は次の相続人に移り、故人の両親(直系尊属)、兄弟姉妹に移ることになります。
Q14.使途不明金がある場合、遺産分割はどうする?

被相続人の預貯金の一部が不明になっています。どうすればいいですか?

使途不明金がある場合、まず 通帳の取引履歴を確認 しましょう。
故人の預貯金のうち使途不明金がある場合は、そのお金が何に使用されたか?確認が必要になります。もし、故人の医療費や生活費などに使用されものである場合は問題はありませんが、特定の相続人が婚姻費用や住宅購入費など、故人から生前贈与を受けていた場合は「特別受益」に該当する可能性があります。
特別受益があった場合には、その金額を合算し相続財産の総額(みなし相続財産)を算定し遺産分割協議を行うことになります。なお、特別受益があるかどうかは、相続人間の合意が必要ですが、争いが生じる場合は家庭裁判所での調停や審判を申し立てることになります。
Q15.代償分割・換価分割とは、どの様な方法ですか?

遺産分割には、どのような方法があるのですか?

現物分割、換価分割、代償分割などの方法があります。
ここでは、財産の分割方法について、代表的な3つの方法について解説させて頂きます。
現物分割は、不動産、預貯金など、個別の財産ごとに分割する方法です。例えば、自宅は妻が取得し、預貯金は子供が取得するなどの方法になります。状況に応じて、預貯金は、長男が1/2、次男が1/2取得するなど、個別の財産に割合を設定して取得する方法もあります。実際には、この分割方法で遺産分割を行われる方が多いかと思います。
1人の相続人が不動産を取得した場合など、他の相続人に不動産額に相当する金銭を支払い(相続分)調整する方法です。例えば、主たる財産が持家のみ、不動産価格が3000万円とした場合、相続人が妻と子供2人で妻が不動産を取得したとします。
- 法定相続分=妻1/2、子供1/2✕2人=1/4(子供1人)となります。
このケースで妻が不動産を取得した場合、3000万円✕1/2=1500万円(子供2人)✕1/2=750万円(子供1人あたり)になります。つまり、妻が不動産を取得し、現金で750万円ずつ2人の子供に代償金を支払う方法です。
この方法は資金に余裕がある場合などに行われる分割方法になります。余裕がない場合は別の方法での分割を選択することになります。
換価分割とは、遺産を売却し、その売却代金を相続人間で分配する方法です。例えば、不動産を売却し、その代金を相続人間で分ける形になります。売却には相続人全員の合意が必要であり、不動産売却時の税金も考慮しなければなりません。また、市場の状況によっては希望価格で売却できない可能性もあります。
その他、全部分割、一部分割、共有分割などの方法もありますが、現物分割か換価分割を選択される方が、一般的には多いかと思います。もし、どの様に分割したら良いか?わからない場合は、専門家に相談してから分割方法を決められてた方が良いかと思います。
5.遺産分割協議書作成のポイントとQ&A まとめ

遺産分割協議書の作成ポイント・作成例から遺産分割Q&Aなど、遺産分割に関することをまとめさせて頂きました。遺産分割行われる際の参考にして頂ければと思います。
当事務所では、遺言書作成のサポートから相続手続に関する、ご相談、手続代行について葛飾区を中心に行わせて頂いております。当事務所は、平成21年度開業の行政書士事務所で、これまで遺言書作成から相続手続の代行のご相談・ご依頼を多くいただいており、経験・実績豊富な事務所ですので安心して問合せ下さい。
相談だけでも大丈夫ですので、まずはお問合せから始めて下さい。
»» 次の記事:遺留分とは?遺留分侵害額請求権とは? »»
«« 前の記事:遺産分割協議を行う前に知っておきたいことは? ««
大塚法務行政書士事務所 大塚博幸

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)