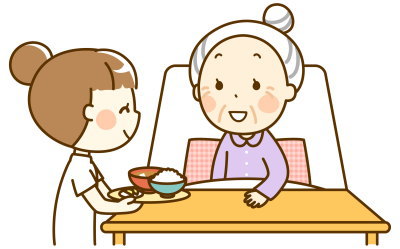・「相続が発生したけれど、何から始めればよいのかわからない」「手続きを放置して良いものか不安」といった声をよく耳にします。相続手続きは人生でそう何度も経験するものではないため、不安や疑問を感じるのは当然のことです。
この記事では、相続手続きの基本的な流れを丁寧にご紹介しながら、それぞれのステップでの注意点や必要な知識も補足いたします。相続に直面された方が、落ち着いてひとつずつ手続きを進められるように、ぜひご参考ください。
1.相続財産の確認
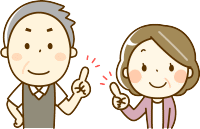
最初に行うべきは、故人(被相続人)の財産内容を把握することです。相続財産にはさまざまな種類があり、正しく把握しておくことで今後の手続きがスムーズになります。
財産調査のポイント
固定資産納税通知書や登記簿謄本などを確認し、所有していた土地や建物を把握します。また固定資産評価証明書も相続手続で必要になりますので都税事務所等から取得しておきましょう。なお、名寄帳も合せて取得しておくと同地区に故人が所有して不動産一式が記載された書類が発行されます。念の為、こちらも取得しておきましょう。
銀行口座の残高確認、タンス預金や金庫の中もチェックが必要です。故人が複数の金融機関を利用していた場合、すべて確認するようにします。もし銀行通帳から残高が確認出来ない場合は、通帳記帳するか残高証明書を取得します。同一の銀行に複数の口座を持っていた可能性がある場合は、残高証明書を取得するとその銀行の口座一式の残金が確認出来ます。
証券会社の取引明細や通知書から保有銘柄を特定します。証券の相続には名義変更や評価手続きも必要です。証券会社の特定後、相続発生の連絡をおこない手続きに必要な書類一式の確認をして下さい。
被相続人が契約をしていた生命保険の確認が必要です。保険証券の有無を確認し、契約がある場合は、生命保険会社に連絡をします。生命保険は契約者、被保険者、受取人の関係によって課税対象者が異なりますのでご注意下さい。生命保険が相続税の課税対象になる場合、法定相続人数✕500万円までは非課税とされています。
カードローン、住宅ローン、消費者金融からの借り入れなど、マイナスの財産も相続財産になります。銀行通帳等から定期的に引きおとしされているものや、郵便物の通知書等から把握していきます。慎重に調査を行ずに相続を進めると後で予想外の負担を負うことになりますのでご注意ください。もし、プラスよりマイナスの財産が多い場合は、相続放棄を検討しましょう。
病院・施設、公共料金等の未払金など見落とされがちな財産も確認しておきましょう。こちらも郵便物や銀行の通帳等から調査を行って行きましょう。
財産目録の作成
不動産、現金、預貯金、株券、生命保険等の故人の財産に関するものの調査が完了しましたら、関係する書類一式をファイルにまとめておきましょう。そしてその資料をもとに財産目録を作成します。それぞれの項目がごとに整理し、可能であれば金額も明記し、プラスとマイナスの財産を分けて記録すると、より相続財産が把握し易くなります。
相続税申告の目安
次に、相続財産が合計いくらになるのか?確認します。(不動産を所有している場合は、固定資産納税通知書も確認。)不動産の価格については、路線価等の価格が基準になりますが、正確には補正係数等を考慮して計算する必要がある為、まずは概算でどれくらいの金額か確認しておきましょう。(国税庁のHPで確認できます。https://www.rosenka.nta.go.jp/ )
現金、預金、証券等の有価証券、生命保険等を合計し、概算で基礎控除額を越えるかどうか確認します。
(葬儀費用、故人の入院治療費等は、相続税申告の額から控除できます。)
〇 基礎控除額=3,000万円+相続人1人600万円
例)相続人 妻、子2人の場合=3,000万円 + 600万円 × 3=4,800万円
上記、基礎控除額を明らかに超える場合は、相続税申告が必要になります。(相続開始日から10ヶ月以内)
※基礎控除額を越える方、合計額が正しいか?不安な方、基礎控除額ぎりぎりの方等は、早めに税理士に相談された方が良いかと思います。
2.関係先への連絡

故人が利用していた金融機関、公共機関等の各関係先に相続が発生したことの連絡を速やかに行います。金融機関に連絡すると口座が凍結され不正利用を防止することができます。
連絡すべき主な機関
相続が発生したことを伝えると口座が凍結されます。その後、連絡した各金融機関から相続手続に必要な書類が記載された「相続手続の案内」が郵送で届きます。その案内には銀行所定の届出用紙や具体的な手続の進め方など記載されています。
保有資産の確認、受取りに必要な書類の取り寄せも行います。証券の受取には、相続人が証券口座をもつ必要がありますが、他の証券会社では受取が出来ない場合がありますので、証券口座をお持ちでない場合は、事前に証券会社に確認した上で口座を開設して下さい。
契約者の名義変更や解約の手続が必要です。未払金がある場合は、相続のマイナス財産になりますので相続人が支払うことになります。その他、年金を受けている方が亡くなった場合、年金事務所への連絡も必要になります。
3.戸籍・住民票等の取得
相続手続きを進めるためには、故人の身分関係を証明するための公的書類が必要となります。
主に必要となる書類

故人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を取得し相続人を確定します。直系の親族であれば戸籍の広域交付制度が利用できますが、兄弟等の場合は管轄の市区町村に請求することになりますので、転籍が多い場合は戸籍の収集に時間が掛かる場合があります。
戸籍一式の取得により相続人全員の確定後、遺産分割協議を行います。そもそも遺産分割協議は相続人全員の参加が必要になりますので、その全員参加の証明として出生から死亡までの戸籍が必要になる訳です。
相続人全員の現在(最新)の戸籍が必要になります。こちらは相続発生時に相続人が生存していることの証明する書類といえます。もし、先に亡くなっている場合は、相続人が変動する可能性もあるため、その確認の意味でも必要になります。従って相続人の戸籍は、相続発生後に取得する必要があります。(事前に取得していた戸籍は使用できません。)
故人の最後の住所地を確認する書類として住民票の除票が必要になります。こちらの書類は死亡記載のある戸籍と同一人物であることを紐づけるため「本籍記載あり」で取得します。また故人の本籍が不明の場合は、除票を先に取得し、記載されている本籍に戸籍謄本を請求する方法もあります。
手続により相続人の住民票が求められる場合があります。戸籍を取得される際に住民票も取得しておいた方が二度手間にならずに済みますので合わせて取得しておきましょう。なお、法定相続情報一覧図を取得する場合、住所記載は任意ですが住所地も記載しておくと全ての手続きに対応できるため、住所記載の法定相続情報一覧図を取得することをお勧めします。
遺産分割協議書の押印や相続手続において相続人の印鑑証明書が必要になります。実印をお持ちでない場合は、この機会に作成し印鑑登録を行っておきましょう。印鑑証明書は、銀行等の相続手続きを行う際に有効期限(3か月~6ヶ月)が定められている場合があります。遺産分割協議に時間が掛かる場合などは時期をみて習得した方が良いかと思います。
上記の書類が相続手続きを行う場合の基本セットとも言えます。銀行の相続手続等、窓口申請ではなく郵送で手続きを行う場合、戸籍等、公的書類の原本を郵送することになりますので、一セットの戸籍謄本等では時間が掛かることになります。その場合、数セットを取得しておくか、又は、法定相続情報を取得しておくと便利です。(法定相続情報一覧図は無料で取得出来ます。)
不動産の相続登記を行う場合は、不動産の登記簿謄本、名寄帳、固定資産評価証明書も取得しておきましよう。
4.遺産分割協議書の作成
相続財産の把握、相続人の確定まで進みましたら、次に遺産分割協議を行います。
(1)遺産分割協議とは?
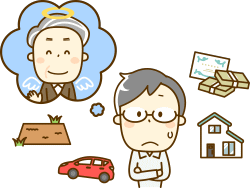
相続人全員の協議により、相続財産をどのように分配するか決定します。(遺言書がある場合は、その内容に従うことになり遺産分割協議は不要です。)法定相続分による分配、または、協議により一人の相続人が全ての相続財産を取得することも可能です。
上記により決定し内容について、遺産分割協議書を作成し、署名押印の上で、各自一通保存します。この遺産分割協議書は、銀行手続、不動産登記等の相続手続の際に必要になります。
法定相続人が1人でも欠けていると遺産分割協議が無効になります。必ず全員参加し合意することが必要です。
必ずしも法定相続分に従う必要はありません。相続人全員の合意があれば自由に分配内容を決めることができます。
相続人の話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行いましょう。
(2)遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が完了したら、その内容を記録した遺産分割協議書を作成します。特に決まった形式はありませんが、以下の項目は記載しておきましょう。
- 被相続人の情報(死亡者の氏名、死亡年月日、最後本籍地・住所地)
- 相続財産の内容(不動産、預貯金、有価証券等)
- 相続財産の分配方法
- 相続人全員の氏名・住所
- 作成年月日等
協議書作成後に各相続人が署名捺印(実印)します。書類は相続人の人数分用意し、各自保管します。相続人で作成することに不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。なお、この協議書は、相続登記や銀行預金の払戻し等の相続手続に必要になります。
遺産分割協議の基礎知識、協議書作成のポイントの詳細は、こちらを参考にして下さい。
・遺産分割協議を行う前に知っておきたいことは?行政書士が解説
・遺産分割協議書作成のポイントと遺産分割Q&A!
5.各種手続き
相続手続きに必要な書類、遺産分割協議書の準備が整いましたら、次は実際の手続きを行います。財産の種類によって様々な手続が必要になりますが、ここでは主な手続について解説させて頂きます。

銀行から郵送された書類に必要事項を記載し、関係書類と共に、銀行窓口又は郵送にて手続きを行います。実際の入金までには2週間程度かかる場合があります。
故人が不動産を所有されていた場合は、所有者変更登記を行います、司法書士に依頼するか、ご自身で法務局に行かれ手続きを行う方もおります。(3年以内の相続登記が義務化されています。)
相続税申告が必要な方は、相続開始日から10か月以内に行います。
年金・保険関係等
・相続で必要な各種届出や手続きについてのポイントと流れを解説
6.遺品の整理等
相続手続が進む中で、故人が所有していた家財道具やその他動産の整理ををする必要があります。
遺品整理の流れ
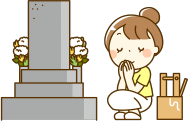
遺品は金銭的な価値のあるものだけでなく、思い出の品も多く含まれています。円満に整理を進めるには、段取りを整え、適切な配慮をもって行動することも大切です。
故人が住んでいた家の中を一通り確認し以下の様な仕分けを行います。
- 貴重品(現金・貴金属・通帳・証書など)
- 形見分けとなる思い出の品(写真・愛用品など)
- 残すべき書類(契約書、保険証券、公的証明書類など)
- 再利用・売却可能な家電・家具類
- 廃棄物対象となる品物
金銭的な価値のあるものは、相続財産として財産目録にも反映させる必要があるため慎重に確認する必要があります。また、契約書などの重要書類は相続手続にも必要になりますので保管しておきましょう。
形見分けや記念品などの分配は、遺族間で話し合いトラブルの原因とならないよう合意の上で進めることが大切です。特に故人との関係が深かった相続人にとっては、思い出の品に強い感情的価値があることが多い為、事前に十分は話し合いの時間を設けるなど慎重に進めましょう。
不要な家財道具などは次の方法で処分・売却を行うことができます。
- 自治体の粗大ごみ回収、一般廃棄物として処理
- リサイクルショップやネットオークションでの売却
- 専門の遺品整理業者への一括依頼
家財道具が多い場合や、遠方に住んでいて作業が難しい場合は、遺品整理業者を活用することで時間と労力の節約になります。
遺品整理業者は、遺品の仕分け・運搬・清掃・リサイクル・供養などを一括して依頼することも可能になります。但し、悪質な業者もおりますので、以下の点に注意して業者を選びましょう。
- 複数社から見積書を取得する(相場と費用の把握のため)
- 一般廃棄物処理の許可がある業者を選ぶ
- 遺品整理士などの有資格者の在籍を確認
- 会社の評判や口コミを確認
必ず事前に見積書を取得して費用の総額を確認した上で依頼する様にしましょう。もし、後から高額な請求をされた場合は、早めに、国民生活センター https://www.kokusen.go.jp/ などにご相談して下さい。
注意すべきポイント
遺品のうち価値が高いも(貴金属・宝飾品・美術品など)のは、遺産分割の対象になる可能性があります。勝手な判断により処分をsると、後に他の相続人とトラブルになる可能性があります。必ず相続人全員の話し合い合意のを得た上で対応しましよう。
相続放棄を検討されている方が遺品に手を付けると相続の意思があると判断される可能性があります。そのため、放棄を検討されている場合は遺品整理を行わないようにし、他の相続人にも伝えておきましょう。
遺品の中には、相続人の感情に大きく関わるものが含まれる場合もあります。無断で処分したり、勝手に持ち出したりすると、後々の対立につながる恐れがあります。整理の際は、必ず相続人間での合意とコミュニケーションを重視しましょう。
7.相続手続は何から始めれば? まとめ

ここまでご覧頂きまして有難うございました。相続はいきなり発生することがあります。しかし何から始めて良いか?わからない方も多いのではないでしょうか。この記事では相続手続について順をおって主にすべきことを解説させて頂きました。
その他、故人の状況に応じて更に行うべきことも多々あります。まずは、故人の財産の状況を確認し、その中から連絡先を一つずつ確認していきます。
相続人の方が1人で必要な書類を一式取得して、銀行手続、相続登記、相続税申告まで行うことは時間も労力も必要になります。もし、ご自身で行うことが難しい場合は早めに専門家にご相談された方が良いかと思います。
最後に...
当事務所は、平成21年度開業の葛飾区の行政書士事務所になります。遺言・相続のご相談から公正証書遺言のサポート、相続手続代行などのご依頼を頂いております。経験豊富な事務所ですのでご不明点等ありましたら、お気軽にお問合せ下さい。相談だけでも大丈夫です。
«« 前の記事:家族信託とは?わかり易く解説 ««
大塚法務行政書士事務所 大塚博幸

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)